「布団に入ってからなかなか寝つけない」「頭が冴えてしまってスマホをだらだら見てしまう」。そんな夜が続くと、明日の仕事や家事への不安も重なり、余計に眠れなくなってしまいますよね。
最近は、寝つきを良くする方法として「香り」や「アロマ」がたびたび紹介されています。ただ、なんとなく良さそうだと思いつつも、「本当に寝つき改善に効果があるのか」「どんな香りをどう使えばいいのか」「自分にも合うのか」など、わからないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、寝つきを改善する香りに興味があるものの、具体的な選び方や使い方がわからない方に向けて、「香りが睡眠に与える影響」「代表的な香りの特徴」「寝る前のアロマの取り入れ方」「やりがちなNGな使い方と対策」までを、順番にわかりやすく解説します。
最初に、この記事の結論を三つにまとめてお伝えします。
第一に、寝つきを改善する香りは「魔法の特効薬」ではありませんが、自律神経を落ち着かせたり、不安や緊張を和らげたりすることで、眠りに入りやすい土台づくりをサポートしてくれる可能性があるということです。
第二に、香り選びで大切なのは「世間で人気の香り」よりも「自分が心地よいと感じる香り」を優先し、適切な濃度と時間で使うことです。強すぎる香りや長時間の使用は、かえって寝つきを妨げることがあります。
第三に、寝つきを改善する香りは、寝室の環境づくりや就寝前のリラックス習慣と組み合わせることで、数週間〜数か月のスパンでじわじわと効果を実感しやすくなるという点です。
ここでお伝えする内容は、医療行為や治療を目的としたものではなく、あくまで日々の生活習慣やセルフケアの一つとしての一般的な情報です。つらい症状が続く場合や、病気が疑われる場合には、必ず医師や専門機関に相談するようにしてください。
この記事は、睡眠と生活習慣・アロマテラピーに関する取材・執筆経験を持つライターが、国内外の公的機関資料や専門書、専門家の解説などを参考にしながら、一般的な知識としてまとめたものです。医学的な診断や治療を行うものではなく、あくまで非医療の情報提供です。具体的な症状や持病がある方、妊娠中の方などは、自己判断に頼らず、必ず医師や専門家に相談することをおすすめします。
それでは、香りが寝つきにどう関わるのかという基本から、一つずつ見ていきましょう。
寝つきを改善する香りが注目される原因と睡眠の仕組みを理解する
まずは、なぜ「寝つきを改善する香り」が注目されているのか、その背景と睡眠の仕組みを簡単に整理します。仕組みを知っておくことで、香りを「なんとなく」ではなく、より納得感を持って暮らしに取り入れやすくなります。
寝つきと自律神経の関係
私たちのからだには、意識とは関係なく働く「自律神経」という仕組みがあります。簡単に言うと、昼間に活動モードにするアクセル役の「交感神経」と、夜にリラックスモードにするブレーキ役の「副交感神経」が、バランスを取り合っているイメージです。
寝つきが悪いと感じているときは、多くの場合、このバランスが崩れ、夜になっても交感神経が優位なままになっていると考えられます。仕事や勉強のプレッシャー、人間関係のストレス、スマホやパソコンからの情報の洪水などが続くと、心も身体も「緊張モード」から抜け出しにくくなります。
ここで香りが役に立つと言われるのは、好きな香りをかぐことで、呼吸がゆっくりになったり、筋肉のこわばりがゆるんだりして、結果的に副交感神経が優位になりやすくなると考えられているからです。香りそのものが睡眠薬のように眠らせるわけではなく、**「緊張モードからリラックスモードへの切り替えを手助けするスイッチ」**のような役割を担ってくれます。
香りが脳に届くまでのシンプルなメカニズム
香りの成分は、鼻から吸い込まれると、「嗅球(きゅうきゅう)」と呼ばれる部分を通って、感情や記憶に関係する脳の領域に届くと言われています。難しい専門用語は省きますが、ポイントは二つです。
一つ目は、香りの情報が「好き」「嫌い」「安心する」「落ち着かない」といった感情と結びつきやすいということです。過去の記憶ともつながりやすく、「子どもの頃に使っていた柔軟剤の香りで安心する」といった経験を持つ方も多いのではないでしょうか。
二つ目は、香りの刺激が、自律神経やホルモンの働きに間接的に影響を与える可能性があるという点です。たとえば、ラベンダーなどの香りは、緊張を和らげる方向に働きやすいと考えられており、その結果として寝つきが良くなったと感じる人もいます。
「香りで寝つきが改善する」のはどの程度期待できるか
ここで大切なのは、香りはあくまで「サポート役」であり、すべての人に劇的な効果が出るわけではないという点です。寝る直前までカフェインをとっていたり、極端に不規則な生活リズムだったりすると、香りだけで問題が解決することはあまり期待できません。
しかし、生活リズムや寝室環境を大きく変えるのはハードルが高くても、「寝る前に香りを変えてみる」「リラックスできるアロマを一本取り入れてみる」といった小さな一歩からなら始めやすい人も多いです。「香りで寝つきを改善する」ことは、睡眠の質を整える入り口の一つと考えると、現実的な期待値を持ちやすくなります。
寝つきを改善する香りの種類と選び方の方法
次に、寝つき改善に役立つとされる代表的な香りと、その選び方のポイントを整理します。ここでは、アロマオイル(精油)だけでなく、ルームスプレーやピローミスト、ハーブティーなど、さまざまな形で楽しめる香りをイメージしながら読んでみてください。
寝つき改善に使われる代表的な香り
寝つきを改善する香りとしてよく挙げられるのが、ラベンダー、カモミール、オレンジスイート、ベルガモット、ゼラニウムなどです。これらは一般的に、気持ちを落ち着かせたり、不安感を和らげたりする方向に働く香りとして知られています。
ラベンダーは、フローラルで少しハーブっぽい香りが特徴で、「アロマといえばラベンダー」というほどポピュラーです。カモミールは、りんごのような甘さを感じる香りで、ハーブティーとしても親しまれています。オレンジスイートは、みかんの皮をむいたときのような、親しみやすい柑橘の香りです。
ここで、代表的な香りの特徴と、寝つきを改善したい人にとってのポイントを、一覧表で整理してみます。この表は、「どの香りから試してみようか」を選ぶ際の参考マップとして活用してみてください。
| 香りの種類 | 香りのイメージ | 寝つき改善で意識したいポイント |
|---|---|---|
| ラベンダー | 花とハーブが混ざったような落ち着いた香り | 緊張や不安を感じやすいときのリラックスに向きやすい。香りが強く感じる人は濃度を薄めると使いやすい |
| カモミール(ローマンなど) | りんごのような甘くやさしい香り | イライラしやすい夜や、心をなだめたいときに。ハーブティーで取り入れると香りと温かさの両方で落ち着きやすい |
| オレンジスイート | みかんの皮をむいたときのような柑橘の香り | 気分を前向きにしつつ、肩の力を抜きたいときに。子ども部屋でも使いやすい穏やかな印象の香り |
| ベルガモット | 紅茶のアールグレイに使われる爽やかな柑橘系 | 日中の不安やモヤモヤを引きずりやすい人に。少し大人っぽい、上品なリラックス感がほしいときに向く |
| ゼラニウム | 甘さの中にハーブ感のあるフローラルな香り | 気分の波が気になるときや、イライラと落ち込みを行き来しやすいときのバランスづくりに役立つことがある |
表を見るときは、「効きそうな香り」を探すというよりも、「自分が心地よいと感じる香り」「嫌ではない香り」から選ぶことを意識してみてください。どんなにリラックスに向くとされていても、本人が苦手な香りでは、かえってストレスになってしまいます。
不安や緊張が強い人に合いやすい香りの考え方
日中から不安感が強かったり、夜になると考え事が止まらなくなったりするタイプの方は、「落ち着き」や「安心感」を重視した香りを選ぶとよいことが多いです。ラベンダーやカモミール、ゼラニウムなどは、こうしたシーンでよく使われます。
一方で、不安や緊張が強いときに、甘すぎる香りや、重たい香りを使うと気分が悪くなる人もいます。その場合は、オレンジスイートやベルガモットのような、軽めの柑橘系から試してみるのも一つの方法です。
大切なのは、「寝つきを改善する香りだから」と我慢して使い続けるのではなく、「香りをかいだ自分のからだの反応」をよく観察することです。深呼吸しやすくなる、肩の力が抜ける、まぶたが重くなるような感覚があれば、その香りはあなたの今の状態に比較的合っている可能性があります。
体質・好み別の香りの選び方
寝つきと香りの相性には、体質や性格、ライフスタイルも関係してきます。例えば、普段から刺激的な香水や強い香りが苦手な人は、アロマでもごく薄い濃度からスタートするのがおすすめです。アロマディフューザーではなく、ティッシュに一滴たらして枕元から少し離れた場所に置くなど、香りの量を控えめにして試すと安心です。
また、頭を使う仕事が多く、日中に緊張が続きやすい人は、ハーブ系やフローラル系の香りで「ほっと一息つく」時間をつくると、寝つきがスムーズになりやすい場合があります。逆に、日中にあまり動かず、夜もだらだらとスマホを見てしまう生活の人は、軽やかな柑橘系の香りを使って、「寝る前のスイッチ」を切り替える合図にするのも良いでしょう。
香りで寝つきを改善する具体的な使い方・習慣づくり
香りを選んだあとは、実際に「どのように使うか」が大切です。この章では、寝つきを改善する香りを生活の中に取り入れる具体的な方法と、習慣化のコツをお伝えします。
寝室で香りを使う基本的な方法
寝つきを改善したいときに、香りを取り入れる代表的な方法として、アロマディフューザー、アロマストーン、ピローミスト、ルームスプレーなどがあります。どの方法にも一長一短があるため、生活スタイルや部屋の広さに合わせて選ぶのがおすすめです。
アロマディフューザーは、水や専用の装置を使って香りを部屋全体に拡散させる方法です。広めの寝室でも香りが行き渡りやすく、タイマー機能がついているものもあるため、就寝前一時間ほどだけ香らせるといった使い方がしやすくなります。
アロマストーンや素焼きの小物に精油を一滴垂らして使う方法は、香りの広がりが穏やかで、狭い寝室や一人暮らしのワンルームにも向いています。ピローミストやルームスプレーは、寝具や空間に直接吹きかけることで、ほどよい残り香を楽しめます。いずれの場合も、香りが強くなりすぎない程度の量から試すことがポイントです。
寝る前のルーティンに香りを組み込む
香りを寝つき改善に活かすには、「なんとなく使う」よりも、「毎晩ほぼ同じタイミングで使う」ことが効果的です。例えば、就寝九十分前にお風呂から出たら、寝室の照明を少し落とし、アロマディフューザーのスイッチを入れる。あるいは、布団に入る前に、枕から少し離れた位置にピローミストをひと吹きする、といった流れを決めてしまいます。
このような**「香りのルーティン」**をつくることで、脳と身体が「この香りがすると、そろそろ眠る時間だ」と学習しやすくなります。はじめの一週間ほどは大きな変化を感じないかもしれませんが、二〜三週間続けることで、「気づいたら寝つきがスムーズになってきた」と感じる人もいます。
香りの強さ・時間・頻度の目安
寝つきを改善する香りを使うときの目安としては、「少し物足りないかな」と感じる程度の濃さから始めるのがおすすめです。強い香りは、一時的には心地よくても、頭が痛くなったり、気分が悪くなったりする原因になることがあります。
時間の目安としては、就寝の三十分〜一時間前から香らせ始め、眠りについた後は自動で切れるようにしておくと安心です。アロマディフューザーならタイマー機能を活用し、アロマストーンやピローミストなら、寝る前だけ使って、寝ついた後は自然に香りが薄らいでいくイメージです。
頻度については、毎日同じ香りを使う方法と、数種類を日替わりで使う方法のどちらも考えられます。飽きっぽい人は二〜三種類をローテーションし、安定感を重視したい人は、一つの香りを集中的に使うなど、自分の性格に合わせて調整してみてください。
ここで、香りの使い方別のメリットと注意点を整理した表を紹介します。この表は、自分に合った使い方を選ぶときの比較表として活用すると便利です。
| 香りの使い方 | メリット | 注意したいポイント |
|---|---|---|
| アロマディフューザー | 部屋全体に香りが広がりやすく、タイマー付きなら管理もしやすい | 水の交換や掃除が必要。香りが強くなりすぎないよう、精油の量を少なめから試す |
| アロマストーン・素焼き小物 | 香りが穏やかで、狭い寝室でも使いやすい。電源が不要で手軽 | 香りの広がりが控えめなので、物足りないと感じたら置き場所や滴下量を調整する |
| ピローミスト・ルームスプレー | 手軽に使え、寝具の「寝る前の香り」を好きなものにできる | 直接肌に触れる場合は刺激にならないか注意。寝具にシミがつかないようにテストしてから使う |
| ハーブティーなど飲み物 | 香りに加えて温かさでリラックスしやすい | カフェインを含まないものを選ぶ。寝る直前に大量に飲むと、夜中のトイレが増えることがある |
この表を見ながら、「自分の生活リズムや部屋の環境に合う方法はどれか」「まずはどれから試してみるか」をイメージしてみてください。
寝つきが悪い人がやりがちなNGな香りの使い方と対策
香りは使い方次第で寝つき改善に役立ちますが、使い方を間違えると、かえって睡眠の質を下げてしまうこともあります。この章では、寝つきが悪い人がやりがちなNGな香りの使い方と、その対策を整理します。
香りが強すぎる・種類が多すぎる場合の問題点
「せっかくならしっかり香らせたい」と思うあまり、精油をたくさん垂らしたり、複数の香りを混ぜすぎたりすると、かえって頭が冴えてしまうことがあります。特に狭い寝室や換気が少ない部屋では、強い香りがこもって不快感につながることもあります。
また、一度にたくさんの香りをブレンドすると、自分の好みがわからなくなり、「なんとなく落ち着かない」と感じる原因になることがあります。香りはシンプルに、一度に一〜二種類までにしておくと、自分の体調との相性も把握しやすくなります。
刺激の強い香り・カフェイン系の香りとの付き合い方
ミントやローズマリー、シナモンなどのスパイシーな香りは、日中のリフレッシュには向いていますが、寝る前には刺激が強すぎる場合があります。特に、頭をシャキッとさせたいときに使われる香りは、寝つきを改善したい時間帯には控えめにするのが無難です。
また、コーヒーの香りが好きな人も多いですが、寝る直前にコーヒーの香りを強くかぐと、人によっては「仕事モード」や「勉強モード」が思い出され、リラックスしづらくなることがあります。コーヒーの香りを楽しむなら、夕方までにとどめ、夜はリラックス系の香りに切り替えるなど、時間帯でメリハリをつけるとよいでしょう。
香りに頼りすぎないための視点と対策
「香りさえ使えば眠れるはず」と考えすぎると、思ったように寝つけなかったときに、「自分には効果がない」「また眠れなかった」と落ち込んでしまうことがあります。香りはあくまで、睡眠習慣を整えるためのサポート役と位置づけておくことが大切です。
ここで、寝つきが悪い人がやりがちなNGな香りの使い方と、その代わりに取りたい行動を、表にまとめてみます。この表は、自分の行動パターンを振り返るチェックリストとして活用できます。
| NGな香りの使い方 | なぜ寝つきに良くないか | 代わりに取りたい行動 |
|---|---|---|
| 精油を「香りがするまで」大量に垂らす | 香りが強すぎて頭が冴えたり、気分が悪くなることがある | 最初は少量から試し、物足りなければ少しずつ増やす。弱い香りでも十分リラックスできる場合が多い |
| 「よく眠りたいから」と、寝る直前から香りを使い始める | からだがリラックスモードに切り替わる前に布団に入ることになりやすい | 就寝九十分〜一時間前から、照明を落として香りを使い、少しずつ眠る準備を始める |
| 香りさえあれば生活習慣を変えなくてよいと考える | 寝る直前のスマホやカフェインなど、根本的な要因が放置される | 香りを「きっかけ」として、スマホ時間を減らす、寝室の環境を整えるなど、他の習慣も少しずつ見直す |
この表を見ながら、「自分はどのNGパターンに近いか」「今日から少し変えられそうな行動はどれか」を考えてみてください。
香りだけに頼らない睡眠習慣の整え方とセルフケア
香りは寝つきを改善するうえで心強い味方ですが、香りだけで全てが解決するわけではありません。この章では、香りと相性がよい睡眠習慣やセルフケアの例を紹介します。
寝室環境を整え、香りとの相乗効果を高める
寝つきを良くしたいときは、寝室の明るさ、温度、湿度、音など、環境そのものを見直すことも欠かせません。寝る前に照明を少し暗めにし、スマホ画面の明るさも抑えることで、香りのリラックス効果を感じやすくなります。
室温は、暑すぎず寒すぎない範囲(一般的には十七〜二十二度前後)、湿度は四十〜六十パーセント程度を目安にしつつ、自分が心地よいと感じる状態を探ってみてください。エアコンや加湿器、除湿機などを活用しながら、ベッドに入ったときに「気持ちいい」と感じる空気感をつくることが、香りとの相乗効果につながります。
呼吸法やストレッチと香りを組み合わせる
香りのリラックス効果を高めたいときは、呼吸法や簡単なストレッチと組み合わせるのがおすすめです。例えば、ラベンダーの香りをかぎながら、ゆっくりと鼻から息を吸い、口から細く長く吐く「腹式呼吸」を数分続けると、心拍数が落ち着き、からだの緊張が和らぎやすくなります。
布団の上でできる軽いストレッチも、寝る前のルーティンに向いています。首や肩、腰回りをやさしく伸ばしながら、香りを楽しむことで、「今日一日の終わり」をからだに伝える合図になります。ここでも大切なのは、「頑張りすぎない」ことです。汗をかくほどの激しい運動ではなく、気持ちよく伸びる程度で十分です。
日中の過ごし方と香りの使い分け
日中の過ごし方も、夜の寝つきに大きく影響します。日中にほとんど外に出ず、自然光を浴びない生活が続くと、体内時計がずれやすくなり、夜になっても眠気が来づらくなることがあります。朝や昼に、外の光を浴びながら軽く歩く習慣をつくることは、香りよりも強力な「体内時計調整法」と言えるかもしれません。
香りの使い分けという観点では、朝や日中はレモンやペパーミントなどのスッキリした香りで気分をしゃきっとさせ、夕方以降はラベンダーやオレンジスイートなどのリラックス系の香りに切り替える方法もあります。こうしたメリハリがあると、脳が「今は活動の時間」「今は休む時間」と区別しやすくなり、結果として寝つきの改善にもつながりやすくなります。
専門機関への相談を検討したい目安
ここまでお伝えしてきた内容は、あくまで生活習慣や環境の見直しとしての一般的な情報です。香りやセルフケアだけでは対応が難しいケースもあります。この章では、専門機関への相談を検討したい目安を整理します。
セルフケアだけでは改善が見られない場合
寝つきを改善する香りや、生活習慣の調整を数週間〜一か月ほど続けても、まったく変化を感じられない場合や、むしろ日を追うごとに悪化していると感じる場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。
具体的には、「寝つきの悪さが三か月以上続いている」「週の半分以上、布団に入ってから三十分以上眠れない状態が続いている」「夜中に何度も目が覚め、そのまま長時間眠れない」といった状態が続くときは、医療機関で相談する目安の一つになります。
日中の生活やメンタルに大きな影響が出ている場合
睡眠の問題が原因で、日中の眠気が強く、仕事や家事、育児、学業などに支障が出ている場合も、セルフケアだけに頼らず専門機関に相談した方がよいと考えられます。運転中の強い眠気や、会議中や授業中に何度も意識が落ちるなどの症状がある場合は、特に注意が必要です。
また、寝つきの悪さに加えて、気分の落ち込みが強い、何をしても楽しく感じられない、不安感が強くて外出がつらい、といったメンタルのサインがある場合も、心療内科や精神科などを含めた専門家に相談することが大切です。
相談先と受診の準備
相談先としては、かかりつけの内科、心療内科・精神科、睡眠外来、耳鼻科などが考えられます。「どこに行けばよいかわからない」という場合は、まずは普段から通っているクリニックや、地域の総合病院の外来で相談してみるのも一つの方法です。
受診の際には、「寝つきにどれくらい時間がかかっているか」「夜中に目が覚める回数」「起床時間と睡眠時間の長さ」「カフェインやアルコール、薬の使用状況」などを、メモにまとめておくと、医師が状況を把握しやすくなります。完璧な記録である必要はありませんので、思い出せる範囲で書き出して持参すると安心です。
よくある質問(Q&A)
ここでは、寝つきを改善する香りについて、よくある疑問にお答えします。気になるところだけ拾い読みしていただいても構いません。
Q1. 寝つきを改善する香りは、どのくらいで効果を感じられますか?
A. 個人差がありますが、数日試しただけで大きな変化を感じる人もいれば、二〜三週間続けてようやく「そういえば最近、寝つきが少し楽かも」と気づく人もいます。重要なのは、毎晩ほぼ同じタイミングで香りを使い、寝る前のルーティンとして定着させることです。一方で、数か月続けても全く変化がない場合は、香り以外の要因(生活リズムやメンタルの状態など)が大きく関わっている可能性もあります。
Q2. 子どもやペットがいる寝室でも、寝つきを改善する香りを使っても大丈夫ですか?
A. 子どもやペットは、大人よりも香りや成分に敏感な場合があります。特に、猫や犬など一部の動物は、アロマオイルの成分をうまく分解できないことがあるとも言われています。そのため、ペットがいる環境では、獣医師や専門家のアドバイスを受けるか、アロマオイルではなく、ごく穏やかなハーブティーや、香り付きの柔軟剤など、負担が少ない方法を検討した方が安心です。子どもの場合も、濃度を低くし、様子をよく観察しながら慎重に使うようにしてください。
Q3. 市販の「安眠グッズ」の香りでも効果はありますか?
A. 市販のピローミストや入浴剤、アロマキャンドルなどにも、「リラックス」「安眠」といった名前がついているものがたくさんあります。これらは必ずしも精油だけでできているわけではありませんが、「香り」と「自分の心地よさ」が合っていれば、寝つき改善のサポートとして役立つこともあります。重要なのは、原材料や注意書きを確認し、自分の体質や好みに合うかどうかを確かめることです。
Q4. 香りを使うときに気をつけるべき健康面のリスクはありますか?
A. 香りの感じ方や体への影響には個人差があります。頭痛や吐き気、目の痛み、肌荒れなどが出た場合は、すぐに使用を中止し、換気をして様子を見てください。持病がある方や妊娠中・授乳中の方は、使用する前に医師や専門家に相談することをおすすめします。また、アロマオイルを原液のまま肌に直接つけることは避け、使用方法を必ず守るようにしましょう。
Q5. 香水でも寝つきを改善することはできますか?
A. 自分にとって心地よい香水の香りが、リラックスのきっかけになることはありますが、香水はアルコールやさまざまな成分を含んでおり、寝る前に強くつけると、頭が冴えてしまったり、肌への刺激になったりする可能性があります。寝つき改善を目的にする場合は、香水よりも、穏やかで成分がシンプルなアロマオイルやピローミスト、ハーブティーなどを選ぶ方が、扱いやすい場合が多いです。
用語解説
最後に、本文で出てきた用語を簡単におさらいしておきます。
自律神経とは、心臓の鼓動や呼吸、体温調節など、私たちが意識しなくても体の状態を自動的に整えてくれる神経の働きのことです。昼間に働きやすい交感神経と、夜に働きやすい副交感神経があります。
寝つきとは、布団に入ってから実際に眠りに落ちるまでのプロセスや、そのスムーズさを指します。同じ睡眠時間でも、寝つきが悪いと、睡眠全体の満足度が下がりやすくなります。
**精油(エッセンシャルオイル)**とは、植物の花や葉、果皮などから抽出された、香り成分がぎゅっとつまった液体のことです。原液は濃度が高いので、使い方や量には注意が必要です。
ピローミストとは、枕や寝具に吹きかけて使うミスト状の香り製品のことで、寝る前のリラックスタイムに使われることが多いアイテムです。
ホワイトノイズとは、「サーッ」という一定の音のことで、周囲のさまざまな音をかき消すように働きます。人によっては、この音を流していると外の物音が気になりにくくなり、眠りやすくなる場合があります。
まとめ|全部を完璧にやらなくていい。まずは一つの香りから試してみる
この記事では、寝つきを改善する香りをテーマに、香りが睡眠に関わる仕組み、代表的な香りの特徴、具体的な使い方、NGな使い方とその対策、そして香りだけに頼らない睡眠習慣の整え方までを、幅広くお伝えしてきました。
大切なポイントをあらためて整理すると、第一に、寝つきを改善する香りは、神経の緊張をやわらげ、リラックスモードへの切り替えを助ける「サポート役」であるということ。第二に、世間の評判よりも、自分が心地よいと感じる香りを、適切な濃度と時間で使うことが何より重要であること。第三に、香りは寝室環境や生活リズムの調整と組み合わせることで、数週間〜数か月のスパンでじわじわと効果を実感しやすくなるということです。
そして何よりお伝えしたいのは、全部を完璧にやらなくていいという点です。香りの種類も、睡眠改善の方法も、本やインターネットを見ればきりがないほど紹介されていますが、それらを一度に取り入れようとすると、それ自体が新たなストレスになってしまいます。
まずは、「寝つきを改善する香りを一つだけ選んでみる」「就寝一時間前になったら、その香りをかぎながら深呼吸を三回する」といった、小さくて具体的な行動から始めてみてください。慣れてきたら、寝室の照明を少し暗くする、スマホ時間を五分だけ減らすなど、できそうなことを少しずつ増やしていけば十分です。
香りは、毎晩の「眠りへの入り口」をやさしく彩ってくれる存在です。完璧な睡眠を目指すのではなく、昨日より少し楽に眠りにつけた自分を認めながら、あなたのペースで心地よい眠りの習慣を育てていきましょう。
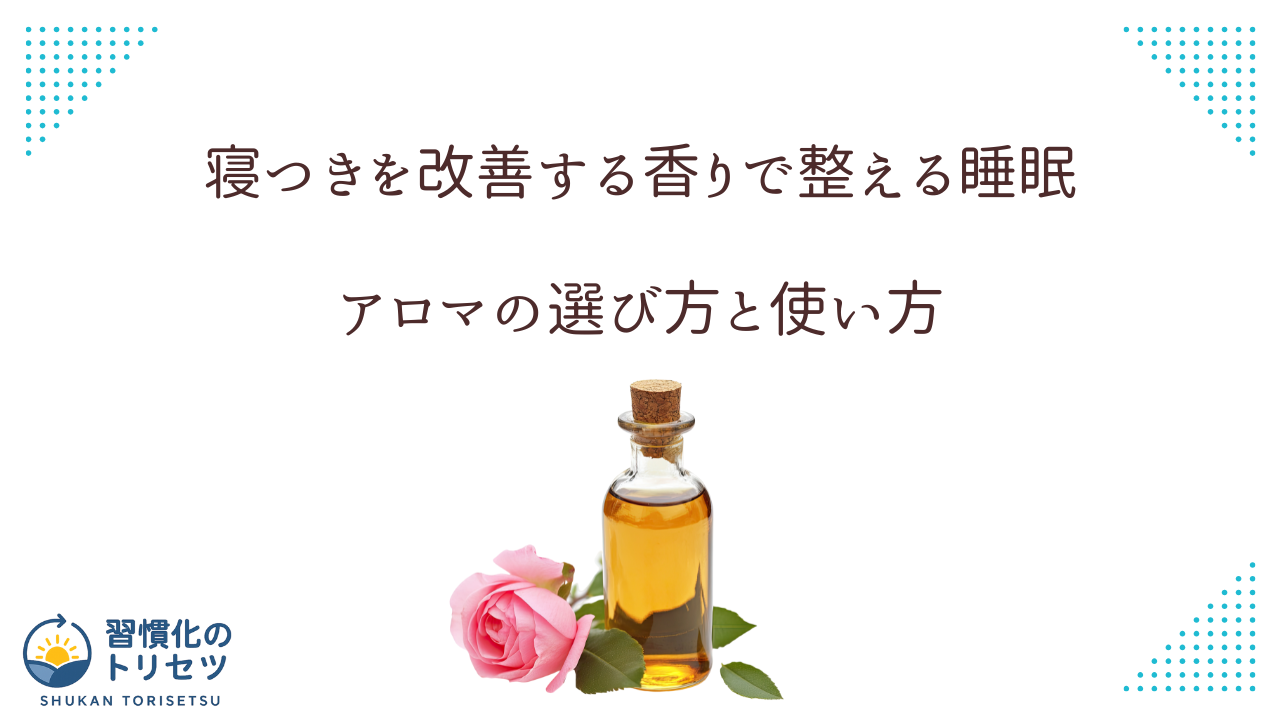
コメント