夜中にふと目が覚めてしまい、「あれ、もう朝かな」と時計を見ると、まだ眠っていたい時間。そこからなかなか眠れず、頭はどんどん冴えていく。ようやくうとうとし始めた頃には目覚ましの時間が近づいていて、翌朝はぐったり。そんな経験を、何度も繰り返していないでしょうか。
「夜中に起きた時にやるべき行動」「夜中に目が覚めたとき どうする」「中途覚醒 対処法」といったキーワードで検索している方は、夜中に起きること自体というよりも、「起きてしまった後にどう動けば、少しでも楽に、また眠れるようになるのか」を知りたいのだと思います。
まず最初に、このテーマの結論を三つにまとめてお伝えします。
一つ目の結論は、夜中に一度起きてしまうこと自体は、多くの人に起こる自然な現象であり、それだけで「おかしい」と思い込みすぎないことが大切だという点です。
二つ目の結論は、夜中に起きた時に「何をするか」「何をしないか」で、その後の再入眠のしやすさが大きく変わるため、ベッドの中での行動や、起きてからの過ごし方に簡単なルールを決めておくとよいという点です。
三つ目の結論は、その場しのぎのテクニックだけに頼るのではなく、日中の過ごし方や就寝前の習慣、寝室環境などを少しずつ整えていくことで、「夜中に起きても慌てなくてすむ状態」をつくりやすくなるという点です。
ここでお伝えする内容は、あくまで一般的なセルフケアの考え方です。症状が長く続く場合や、強い苦痛を伴う場合には、この記事の後半でお伝えするように、無理をせず専門機関への相談も検討してみてください。
この記事は、睡眠や生活習慣の改善に関するコンテンツ制作と、オンライン相談サービスの取材経験を持つライターが、国内外の公的機関の資料や専門書を参考にしながら、一般的な知識として解説しています。医学的な診断や治療を行うものではなく、あくまで非医療の一般的な情報提供です。具体的な症状や病気が心配な場合は、必ず医師や専門機関に相談することをおすすめします。
このあと、夜中に起きた時の状態を理解するための「考え方」、夜中に起きた時にすぐできる具体的な行動、やってはいけないNG行動と代わりの行動、再入眠を助ける生活リズムや寝室環境の整え方、専門機関への相談の目安、Q&Aと用語解説、そして最後に今日からできる一歩をまとめていきます。
夜中に起きた時の状態を理解する原因と考え方
最初に、「夜中に起きた時にやるべき行動」を考える前提として、そもそも夜中に目が覚めるのはどんな状態なのかを整理しておきましょう。原因を正確に特定することは難しくても、「どう捉えればよいか」を知っておくことで、必要以上に不安にならずにすみます。
夜中に起きるのは誰にでもある自然な現象
人の睡眠は、深い眠りと浅い眠りがいくつかのサイクルを繰り返す仕組みになっています。このサイクルの切り替わりのタイミングでは、もともと眠りが浅くなり、短時間だけ意識がはっきりすることもあります。翌朝にその記憶が残っていなければ、多くの人は「ぐっすり眠れた」と感じますが、たまたま意識がはっきりしたままになると、「夜中に起きてしまった」と感じやすくなります。
つまり、夜中に起きること自体は、必ずしも異常なことではありません。大切なのは、「どれくらいの頻度で起きているのか」「起きたあと、どのくらいの時間眠れない状態が続くのか」「翌日の生活にどれくらい影響しているのか」といった全体像です。ここを冷静に見ておくと、必要以上に自分を責めずにすみます。
焦りや不安が「眠れない連鎖」を生む仕組み
夜中に起きた時、「また眠れなくなったらどうしよう」「明日も忙しいのに」と考えれば考えるほど、心と身体は緊張していきます。この緊張が「交感神経」と呼ばれる活動モードの神経を刺激し、ますます目が冴えてしまいます。
本来であれば、夜はリラックスモードの「副交感神経」が優位になり、体温や心拍数が少し下がりながら眠りにつく流れになります。しかし、焦りや不安が強くなると、この切り替えがうまくいかず、「眠れないことを気にするほど、余計に眠れなくなる」という連鎖が起きてしまいます。この仕組みを知っておくと、「不安になることで、さらに寝づらくしてしまうかもしれない」と気づきやすくなります。
まずは「今できること」に目を向ける考え方
夜中に起きた瞬間、過去の失敗や明日の予定、長期的な悩みなど、さまざまな不安が頭に浮かぶことがあります。しかし、その多くは「一人で布団の中で考えても、今すぐ解決できないこと」です。それを夜中の暗い部屋で考え続けると、不安と孤独感が増し、眠れない時間がさらに長くなります。
逆に、「今の自分にできるのは、少しでも身体を休めること」「考えごとは明日、ノートに書き出して向き合えばいい」と区切りをつける考え方を身につけると、夜中の時間の質が変わっていきます。夜中に起きた時にやるべき行動を決めておくことは、こうした考え方の切り替えを助ける役割も持っています。
夜中に起きた時にすぐできる行動方法
ここからは、夜中に起きた瞬間から十五〜二十分程度の時間に焦点を当てて、「夜中に起きた時にやるべき行動」を具体的に整理していきます。完璧にできなくても構いませんので、自分が取り入れやすいものから一つずつ試してみてください。
ベッドの中でできる呼吸法とリラックス法
夜中に起きたとき、まず大切なのは「これ以上緊張を高めないこと」です。身体の力を抜きやすくするために、ベッドの中で簡単な呼吸法やリラックス法を試してみるのがおすすめです。
一つの目安として、「息を吸う時間よりも、吐く時間を少し長くする」呼吸を意識してみてください。例えば、鼻からゆっくり四つ数えながら息を吸い、口または鼻から六つ数えながら息を吐きます。呼吸の回数や秒数は、苦しくならない範囲でかまいません。大切なのは、呼吸をコントロールしようと頑張りすぎるのではなく、「自然な流れを少しだけゆっくりにする」イメージです。
身体の力を抜く方法としては、足先から順番に「少しだけ力を入れて、ふっと抜く」ことを繰り返す方法があります。足先、ふくらはぎ、太もも、お腹、肩、腕、手のひら、顔まわりと、身体の各部分に意識を向けながら行うと、緊張していた場所に気づきやすくなります。
十五〜二十分たっても眠れない時の過ごし方
ベッドの中で呼吸法やリラックス法を試しても、十五〜二十分ほどたってもまったく眠気が戻らない場合には、一度ベッドから出てみるのも一つの選択肢です。このときのポイントは、「再び眠れる確率を下げない行動だけを選ぶ」ことです。
照明は明るくしすぎず、できれば暖かみのある柔らかい光にとどめます。スマホやパソコンの強い光は避け、本を読む、白湯を飲む、軽くストレッチをするなど、刺激の少ない行動を選びます。ここでの目的は、「完全に目を覚ますこと」ではなく、「眠れないことへの焦りを少し落ち着かせること」です。
眠気が戻ってきたと感じたら、そのタイミングでベッドに戻ります。何度か繰り返すうちに、「眠れない時はこのルーティンでやり過ごせばいい」という安心感が少しずつ育ちやすくなります。
トイレや水分補給のちょうどよい範囲
夜中に起きた時、トイレに行きたい感覚がある場合は、無理に我慢する必要はありません。ただし、毎回じっくり明るい照明をつけてしまうと、その明かりの刺激で完全に目が覚めやすくなります。足元だけを照らす間接照明や、小さめのナイトライトを使うなど、最低限の明るさで済ませる工夫をしてみてください。
喉が渇いている場合は、一口から二口程度の水や白湯を飲むのは問題ないとされていますが、コップ一杯以上を何度も飲むと、結果的に夜間のトイレ回数が増えやすくなります。夜中に起きた時にやるべき行動としては、「必要な分だけ、ゆっくりと飲む」くらいの感覚がちょうどよいことが多いです。
夜中に起きた時に避けたいNG行動と代わりの対策
ここからは、「夜中に起きた時にやるべき行動」とセットで考えたい、「やらない方がよい行動」についても整理しておきます。どの行動が自分のクセになっているかを確認しながら、少しずつ置き換えていくイメージを持ってみてください。
スマホ・時計・仕事のことから距離を取る方法
夜中に起きた直後にやってしまいがちなのが、スマホで時刻を確認したり、通知をチェックしたりする行動です。また、天井を見つめながら、「明日の会議の準備が」「メールの返信を」と仕事のことを考え始めてしまう人も多くいます。
これらの行動は、光と情報の刺激によって脳を一気に活動モードに切り替えてしまうため、再入眠の妨げになりやすくなります。さらに、「あと何時間しか眠れない」と時刻を気にすることで、不安や焦りが増してしまいます。
ここで、一度整理として、「夜中に起きた時のNG行動」と「その代わりにできる行動」を表にまとめておきます。この表を見ながら、自分に当てはまりやすい項目を一つ選び、今夜から置き換えてみる意識を持ってみてください。
| 夜中に起きた時のNG行動 | なぜ避けた方がよいか | 代わりにやるべき行動の例 |
|---|---|---|
| すぐにスマホを開いてSNSやニュースを見る | 強い光と情報の刺激で脳が覚醒し、再び眠りにくくなる | スマホに触れず、目を閉じて呼吸に意識を向ける。どうしても起きるときは、暗い部屋で白湯を飲む程度にとどめる |
| ベッドで時刻を何度も確認する | 「あと何時間しか眠れない」という焦りが自分を追い込む | 時計が見えない位置に置き、時間ではなく「今できるリラックス」に意識を向ける |
| 仕事や悩みごとを頭の中で繰り返し考える | 不安や緊張が高まり、交感神経が優位になってしまう | 「考えごとは明日の朝ノートに書く」と決め、今は身体を休めることに集中する |
表の見方としては、「自分がついやってしまうNG行動はどこか」「その行動をやりそうになったとき、代わりに何をするか」をセットで決めておくことがポイントです。完璧にできなくても、少しずつ代替行動の回数を増やしていくことで、夜中の過ごし方の質は変わっていきます。
食べ物・飲み物でやりがちなことと見直し方
夜中に起きた時、「何か食べた方が落ち着くかも」と感じて、甘いお菓子やカップ麺などを口にしてしまうことがあります。しかし、糖分や脂質が多いものを夜中に食べると、消化活動が活発になり、身体は「休むモード」から遠ざかってしまいます。また、胃もたれや胸やけの原因になることもあります。
飲み物についても、コーヒーや紅茶、緑茶などカフェインを含むものは、覚醒を促す方向に働きやすくなります。アルコールも、一時的に眠気を感じさせることはあっても、その後の眠りを浅くし、夜中に何度も起きてしまう原因になることがあります。
どうしても何か口にしたい場合には、白湯やカフェインを含まないハーブティーなど、刺激の少ないものを少量とるにとどめるとよいでしょう。食べ物については、基本的には就寝前に必要なエネルギーをとれているかを見直し、夜中に空腹で目が覚める日が続く場合は、夕食の内容や時間を日中に調整してみることをおすすめします。
「眠らなきゃ」と自分を追い込まない考え方
夜中に起きた時、「絶対に眠らなきゃ」「また眠れなかったらどうしよう」と自分を追い込むほど、心と身体は緊張していきます。しかし、眠りは「頑張って努力するほど手に入るもの」ではなく、むしろ力を抜いたときに自然と訪れるものです。
ここで役立つのが、「眠れなくても、横になって目を閉じているだけでも身体はある程度休めている」というとらえ方です。もちろん、実際に眠れたときとまったく同じではありませんが、「今は身体を休める時間」と考えることで、余計な焦りを和らげることができます。
「夜中に起きた時にやるべき行動」は、眠ろうと頑張るための行動ではなく、「眠れない時間を、少しでも穏やかに過ごすための行動」と捉えると、心の持ち方も変わっていきます。
よく起きてしまう人のための生活リズムと習慣の整え方
夜中に起きた時の対処法がわかってきたら、次は「そもそも夜中に起きにくい状態をつくる」ための生活リズムや習慣についても触れておきましょう。ここでは、日中と就寝前の過ごし方に注目します。
朝と日中の過ごし方で夜の再入眠力を育てる
人の体には「体内時計」と呼ばれる仕組みがあり、朝にしっかり光を浴び、日中に適度に身体を動かし、夜に自然と眠気が訪れる流れをつくっています。このリズムが乱れると、夜の眠気が弱くなり、夜中に目が覚めてからも眠りに戻りにくくなります。
朝起きたらカーテンを開けて自然光を浴びる、ベランダや玄関先に少し出て外気に触れる、可能であれば十分〜三十分程度の散歩を取り入れるなど、「朝のスイッチ」を意識してみてください。日中は、デスクワーク中心の方も、一時間に一度は立ち上がって軽く身体を動かすだけでも、適度な疲労感と眠気につながりやすくなります。
就寝前九十分のルーティンを整える
夜中に起きた時の対処法と同じくらい大切なのが、「寝る前の九十分をどう過ごすか」です。この時間帯に強い光や刺激の多い情報に触れていると、眠りの入口が浅くなり、その後の睡眠全体にも影響が出やすくなります。
理想的には、寝る九十分前から徐々に照明を落とし、スマホやパソコンの使用を減らしていきます。ぬるめのお風呂に入る、簡単なストレッチをする、紙の本を読むなど、リラックスできる行動を自分なりに組み合わせて、「毎晩ほぼ同じ順番で行う」ことを意識してみてください。この繰り返しによって、身体と脳が「そろそろ寝る時間だ」と学習しやすくなります。
ここで、「夜中に起きやすい人の生活パターン」と「見直したいポイントの例」を表にまとめます。この表は、自分の一日の流れを振り返るチェックリストとして活用してみてください。
| 時間帯のイメージ | 夜中に起きやすい人の例 | 見直したいポイントの例 |
|---|---|---|
| 朝〜午前中 | 起きてもカーテンを開けず、すぐにスマホを見てしまう | まずカーテンを開けて自然光を浴びる。スマホを見るのはその後にする |
| 日中 | ほとんど座りっぱなしで、外に出る時間が少ない | 一時間に一度立ち上がる、昼休みに五〜十分だけ外を歩くなど、小さな活動を増やす |
| 夜〜就寝前 | 寝る直前まで明るい画面で動画やSNSを見続ける | 寝る九十分前から画面時間を減らし、照明を少し落としてリラックスできる行動に切り替える |
この表を使うときは、「全部できているかどうか」をチェックするのではなく、「今の自分が特に変えやすそうなところはどこか」を探す視点を持つと、挫折しにくくなります。
生活記録をつけて自分のパターンを知る
夜中に起きた時の行動や、日中の過ごし方、寝つきやすさなどを簡単にメモしておくと、自分なりのパターンに気づきやすくなります。例えば、「寝る直前まで仕事をしていた日は夜中に起きやすい」「夕食が遅い日は眠りが浅く感じる」といった傾向が見えてくることがあります。
記録は、スマホのメモ帳や手帳に「寝た時間」「起きた時間」「夜中に起きた回数」「日中の眠気の強さ」などを一言ずつ書いておくだけでも構いません。数週間続けてみると、感覚だけでは分かりにくかった違いが見えてきて、対策の優先順位を決めるヒントになります。
夜中に起きた時に役立つセルフケアと環境づくりの方法
次に、夜中に起きた時の行動を助けるための「環境」や「セルフケアアイテム」についても触れておきます。高価なものをそろえる必要はなく、自分に合った工夫を少しずつ積み重ねていくイメージが大切です。
寝室環境(光・音・温度)を見直す
まず、寝室の光環境です。街灯や看板の光がカーテンの隙間から差し込んでいたり、スマホの通知の光が枕元で光っていたりすると、眠りが浅くなりやすくなります。遮光カーテンを使う、スマホは別の場所で充電する、ベッドサイドの照明は柔らかい電球色にするなど、「夜は暗めで落ち着いた光」に整えることを意識してみてください。
音については、完全な無音が落ち着く人もいれば、わずかな物音が気になってしまう人もいます。耳栓を使う、静かな環境音やホワイトノイズを流すなど、自分にとって心地よい音のレベルを探ってみるとよいでしょう。
温度や湿度も重要です。暑すぎても寒すぎても、身体は無意識に目を覚ましやすくなります。一般的な目安としては、室温十七〜二十二度前後、湿度四十〜六十パーセント程度が挙げられますが、最終的には「自分が一番楽に感じる状態」を探すことが大切です。
再入眠を助けるアイテムとの付き合い方
アイマスクや耳栓、リラックス効果をうたうハーブティーやアロマオイルなど、睡眠をサポートするアイテムはさまざまあります。これらは、適切に使えば夜中に起きた時の不快感を減らし、再び眠りやすくする助けになることもあります。
ただし、「このアイテムがないと眠れない」と依存してしまうと、旅行や出張など環境が変わった時に不安が強くなることもあります。あくまで「眠りやすい環境づくりを手伝ってくれる道具」として、無理のない範囲で取り入れてみるのがおすすめです。
家族がいる場合のコミュニケーションと工夫
家族と同じ部屋やベッドで眠っている場合、相手のいびきや寝返り、夜中のトイレなどが原因で目が覚めてしまうこともあります。そのとき、相手を責めたくなる気持ちが強くなると、関係性のストレスが増え、さらに眠りにくくなってしまいます。
可能であれば、日中の落ち着いている時間帯に、「最近、夜中に目が覚めやすくて困っていること」「こういう工夫ができるか相談したいこと」を穏やかに話し合ってみてください。別々の布団にする、寝る時間を少しずらす、耳栓を試してみるなど、互いに無理のない範囲でできる工夫を一緒に考えることが大切です。
専門機関への相談を検討したい目安
ここまでお伝えしてきたのは、夜中に起きた時にやるべき行動や、生活習慣・環境の工夫といった、主にセルフケアの視点からの対策です。ただし、中には自己判断だけでは対応が難しく、医療機関や専門家への相談が必要になる場合もあります。
三か月以上続く中途覚醒と日常生活への影響
夜中に起きる状態が週の半分以上の頻度で三か月以上続き、日中の強い眠気や集中力の低下、仕事や家事・育児への支障を強く感じている場合は、一度医療機関に相談することをおすすめします。セルフケアを続けても改善が見られない場合は、別の要因が関わっている可能性もあります。
また、「夜中に起きた時にやるべき行動」をいくつか試してみても、まったく楽になった実感が得られない場合は、「自分のせい」と考えすぎず、専門家の視点を借りるタイミングだと考えてよいでしょう。
呼吸・いびき・気分の変化が気になる場合
家族から「いびきがとても大きい」「寝ている間に呼吸が止まっているように見える」と言われたことがある場合や、自分で寝ている最中に息苦しさを感じる場合には、睡眠時の呼吸に関する病気が隠れていることもあります。また、気分の落ち込みや不安感が強く、朝の憂うつ感が続いている場合には、メンタルヘルスのサポートが必要になることもあります。
こうした状態は、ネットの情報だけで自己判断するのが難しい領域です。少しでも「気になる」「不安だ」と感じる点があれば、早めに相談しておく方が、結果的に安心につながることが多いです。
相談先の選び方と受診時に伝えたいポイント
相談先としては、かかりつけの内科、心療内科・精神科、睡眠外来、耳鼻科などが考えられます。どこに行けばよいか分からない場合は、まずかかりつけ医に「夜中に起きる状態が続いていること」「日中の生活への影響」「自分なりに試した対策」などをまとめて伝えるとよいでしょう。
その際、睡眠の記録を簡単で構わないので持参すると、医師が状況を把握しやすくなります。寝る時間、起きる時間、夜中に起きた回数や時間帯、日中の眠気の程度など、この記事で紹介した視点をもとにメモをつけておくと役立ちます。
よくある質問(Q&A)
ここからは、「夜中に起きた時にやるべき行動」に関して、よくある疑問とその考え方をいくつか取り上げます。
一つ目の質問は、「夜中に起きたとき、すぐにベッドから出た方がいいのか、それとも横になったままの方がいいのか」というものです。目安としては、ベッドの中でリラックスを試して十五〜二十分ほど経ってもまったく眠気が戻らないと感じる場合には、一度ベッドから出て、暗めの照明のもとで静かに過ごしてみる方法がよく紹介されています。一方で、まだぼんやりしていて、身体の力もある程度抜けているように感じる場合には、無理に起き上がらず、そのまま横になって呼吸法などに集中するのも一つの選択肢です。
二つ目の質問は、「夜中に起きたときに音楽を聞いてもいいのか」という疑問です。静かで穏やかな音楽や環境音は、安心感を高めるのに役立つことがあります。ただし、歌詞付きの音楽やテンポが速い曲は、かえって意識をはっきりさせてしまう場合があります。スマホから流す場合でも、画面を見ないように工夫したり、タイマー機能を使って自動的に音が止まるように設定したりするなど、刺激を最小限にすることがポイントです。
三つ目の質問は、「夜中に起きたときにストレッチやヨガをしてもいいのか」というものです。軽いストレッチや深い呼吸を伴う動きは、緊張を和らげるのに役立ちます。ただし、汗をかくほど激しい運動や、難しいポーズに挑戦するようなヨガは、かえって身体を活動モードにしてしまう可能性があります。あくまで「気持ちよく伸びをする」「呼吸を整える」といった穏やかな動きを意識するとよいでしょう。
四つ目の質問は、「睡眠アプリやスマートウォッチで夜中に起きた回数を細かくチェックした方がよいか」という点です。これらのツールは傾向をつかむには便利ですが、毎日の数値に一喜一憂すると、かえって不安が増えてしまうことがあります。参考情報として活用しつつ、「数値が悪い日があっても、自分を責めすぎない」というスタンスを大切にしてください。
五つ目の質問は、「市販の睡眠サポートサプリを飲めば、夜中に起きてもすぐに眠れますか」というものです。サプリメントの効果や安全性は成分や体質によって異なるため、一概には言えません。自己判断で量を増やしたり、複数を組み合わせたりするのは避け、必要だと感じる場合には、あらかじめ医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
用語解説|この記事で出てきた主な言葉
体内時計という言葉は、人の体が一日のリズムをつくるために持っている「時間の感覚」を指します。朝に光を浴びることや、日中の活動、食事の時間などの影響を受けながら、「今は活動する時間」「今は休む時間」といった切り替えを行っています。
交感神経とは、緊張したり集中したりしているときに働きやすい、自律神経の一つです。心拍数を上げたり、血圧を高めたりして、身体を活動モードにします。ストレスや不安で強く働きすぎると、夜になっても心身が休まりにくくなります。
副交感神経とは、リラックスしているときや眠る前に働きやすい自律神経の一つです。心拍数をゆるやかにし、消化を促し、身体を回復モードに導きます。夜はこの副交感神経が優位になることで、自然な眠気が訪れやすくなります。
中途覚醒という言葉は、寝ついたあとから起床までの間に何度も目が覚めてしまい、その後の眠りに戻りにくい状態を指します。「夜中に起きた時にやるべき行動」を考えるとき、この中途覚醒への対応が大きなテーマになります。
ホワイトノイズとは、「サーッ」という一定の音が続く雑音のことで、周囲の物音をマスクして気になりにくくする目的で使われることがあります。人によって合う・合わないがあるため、自分が落ち着くかどうかを試しながら使うことが大切です。
まとめ|全部を完璧にやらなくていい。まずは一つだけ今夜から試してみる
ここまで、夜中に起きた時にやるべき行動というテーマで、夜中に起きる状態の捉え方、ベッドの中や起きた直後にできる具体的な行動、避けたいNG行動とその代わりの行動、生活リズムや寝室環境の整え方、専門機関への相談の目安、Q&Aや用語解説までを一通り整理してきました。
あらためて大切なポイントを三つにまとめると、第一に、夜中に起きてしまうこと自体は多くの人に起こる自然な現象であり、「起きてしまった自分」を責めすぎないことです。第二に、夜中に起きた時に何をするか、何をしないかという小さな選択の積み重ねが、その後の再入眠のしやすさや、翌朝の気分に影響してくるということです。第三に、その場のテクニックだけでなく、日中の過ごし方や就寝前のルーティン、寝室環境などを少しずつ整えることで、「夜中に起きても慌てない自分」を育てていけるということです。
そして、ここまで読んでくださったあなたに、最後にお伝えしたいのは、全部を完璧にやらなくていいというメッセージです。この記事に書かれていることを一度にすべて実践しようとすると、それ自体が新たなプレッシャーになってしまいます。
大切なのは、「まずは○○から一つ選んでやってみる」ことです。例えば、「今夜は寝る三十分前からスマホを触らないようにしてみる」「夜中に起きたら時計を見ないと決めてみる」「朝起きたら必ずカーテンを開ける」など、自分にとって取り組みやすいものを一つだけ選んでみてください。
その小さな一歩が、夜中に起きた時の不安や焦りから少しずつ距離を取り、自分らしい眠りを取り戻していくための、確かなスタートになります。焦らず、自分のペースで、一緒に整えていきましょう。
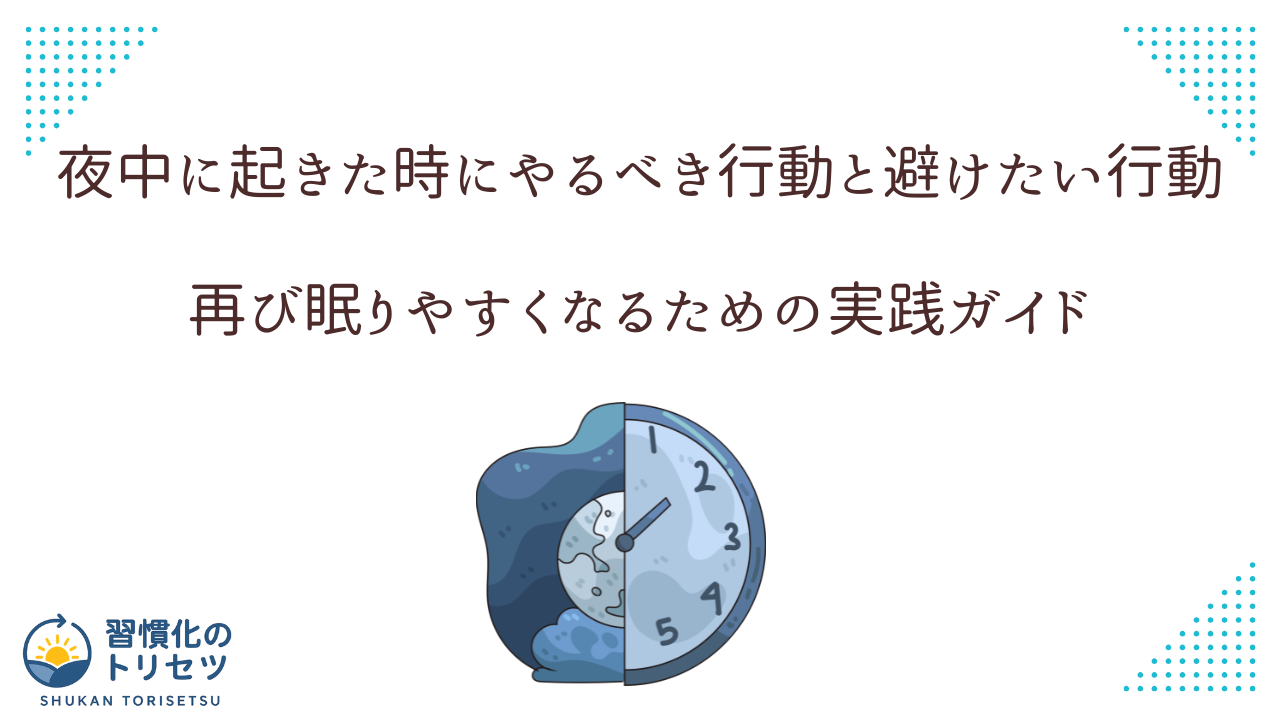
コメント