夜中に目がさえてしまって、時計ばかり気にしてしまう。早く眠らなきゃと思えば思うほど、ますます眠れなくなっていく。「また眠れない夜が来てしまった…」と落ち込むことはありませんか。
「眠れない時 やってはいけないこと」「不眠 時のNG行動」「寝れない とき 対処法」などのキーワードでこの記事にたどり着いた方は、つらい夜をどう乗り切ればいいのか、そして翌日にできるだけ影響を残さないために、具体的に何をやめて何をすればいいのかを知りたいと感じているはずです。
まず最初に、この記事の結論を三つにまとめてお伝えします。
① 眠れない時にやってはいけないことは、「スマホやテレビを見続ける」「アルコールやカフェインでごまかす」「ベッドの中で無理に寝ようと戦い続ける」といった、脳と体をさらに興奮させる行動です。
② 不眠を悪化させないためには、「眠れないからこそやらないこと」を決めたうえで、静かな読書や軽いストレッチなど、リラックスにつながる行動にそっと切り替えることが効果的です。
③ 完璧に眠ろうとするほど眠れなくなるため、「眠れない夜もあるもの」と捉えながら、今日からできる小さな工夫を積み重ねていくことが、長期的に睡眠の質を整える近道です。
この記事は、睡眠や生活習慣、メンタルケアに関する情報発信とオンライン相談サポートの経験を持つライターが、国内外の公的機関の資料や専門書など複数の情報源をもとに、一般的な知識として解説しています。医学的な診断や治療を行うものではなく、あくまで非医療の一般的な情報提供です。具体的な症状や病気が心配な場合は、必ず医師や専門機関に相談することをおすすめします。
ここから、まず「眠れない時にやってはいけないこと」の背景にある考え方と原因を整理し、そのうえで代表的なNG行動と影響、代わりにできる具体的な対処法、タイプ別の工夫、専門機関への相談目安、よくある質問、用語解説、そして明日からの一歩を後押しするまとめ、という順番で解説していきます。
眠れない時にやってはいけないことの原因と考え方を整理する
最初に、「なぜ眠れない時にやってはいけない行動があるのか」という考え方を整理しておきます。これが分かっていると、「なぜスマホが良くないのか」「なぜベッドで粘らない方がいいのか」が感覚ではなく理由として理解でき、行動を変えやすくなります。
「早く寝なきゃ」という焦りが不眠を悪化させる原因
眠れない時、多くの人の頭の中には「早く寝ないと明日に響いてしまう」という焦りが浮かびます。この焦りはごく自然なものですが、問題はその焦りが強くなりすぎることです。
「あと〇時間しか眠れない」「また眠れなかったらどうしよう」と時計を見続けるうちに、心拍数が上がり、呼吸も浅くなり、体はどんどん「戦闘モード」に近づいていきます。本来、眠るときに働いてほしいのは、リラックスを担当する副交感神経ですが、焦りや不安が強くなると、活動モードの交感神経が優位になり、眠気が遠のきやすくなります。
つまり、眠れない時にやってはいけないことの一つは、「早く寝なきゃ」と自分を追い込む考え方を強めすぎることだと言えます。考え方そのものを止めることは難しくても、「あ、いま焦っているな」と気づくことが、悪循環を断ち切る第一歩になります。
ベッドの中で戦うほど眠れなくなる理由
眠れない時、「とにかく布団から出ずに目を閉じていればいつか眠れるだろう」と考え、ベッドの中で長時間粘ってしまう人は少なくありません。しかし、これも不眠を長引かせる原因の一つになり得ます。
人の脳は、「場所」と「状態」を結びつけて覚える性質があります。本来、ベッドは「眠る場所」として脳にインプットされているのが理想的ですが、眠れないまま何時間もベッドの上でイライラしたりスマホを見続けたりしていると、「ベッド=眠れない場所・悩む場所」として学習されてしまうことがあります。
その結果、布団に入った瞬間に「また眠れないかも」という緊張が生まれ、さらに眠りにくくなる、という悪循環が生まれやすくなります。これが、「眠れない時にやってはいけないこと」の中でも特に注意したいポイントです。
眠れない時は「何をするか」より「何をしないか」が重要
眠れない夜を前にすると、多くの人は「どうすれば眠れるか」というテクニックを探しがちです。もちろん、呼吸法やストレッチ、環境づくりなど役立つ方法はたくさんあります。
ただ、同じくらい重要なのが「眠れない時にやってはいけないことを減らす」という視点です。強い光を浴びる、刺激物を摂る、自分を責め続ける、といった行動をやめるだけで、何か新しいことを足すよりも、かえって眠りやすい状態に近づくことがあります。
このように、眠れない時には「やることリスト」ではなく、「やらないことリスト」を持っておくことが、不眠の悪化を防ぐシンプルで現実的な対策になります。
眠れない時にやってはいけない代表的なNG行動とその影響
ここからは、具体的に「眠れない時にやってはいけないこと」を見ていきます。ただし、ただ禁止するのではなく、「なぜ良くないのか」「代わりに何ができるのか」までセットで説明します。
スマホ・テレビ・PCを見るのがNGと言われる理由
眠れない時、つい手が伸びてしまうのがスマホやテレビ、パソコンです。SNSを眺めたり動画を見たりしていると、「暇つぶしになる」「気を紛らわせられる」と感じるかもしれません。
しかし、画面から出る光は、眠気を促すメラトニンというホルモンの分泌に影響を与えやすいと考えられています。特に、スマホやPCのように顔との距離が近い画面は、目に入る光の量も多くなります。また、SNSやニュースの内容が感情を揺さぶり、心がざわついてしまうこともあります。
その結果、「時間は過ぎているのに眠気は遠のく」「布団の中でもずっと画面のことを考えてしまう」という状態になりやすくなります。眠れない時ほどスマホやテレビに頼りたくなりますが、それがさらに「眠れない状態」を長引かせてしまうという点が、やってはいけない行動と言われる理由です。
アルコールやカフェインに頼る対処法の落とし穴
「眠れないからお酒を飲んで寝てしまおう」「夜でもコーヒーを飲んで作業して、眠くなったら寝ればいい」といった発想も、短期的には楽な選択肢に感じられるかもしれません。しかし、長い目で見ると、これも眠れない時にやってはいけない対処法の代表例です。
アルコールは、確かに一時的に気分をリラックスさせることがありますが、睡眠の後半で目が覚めやすくなったり、浅い眠りが増えたりする傾向があると言われます。そのため、「飲めば寝つきは良いが、夜中に何度も目が覚める」というパターンにはまりやすくなります。
カフェインを含む飲み物(コーヒー、緑茶、エナジードリンクなど)も、眠気を覚ます働きがあるため、夜遅い時間に摂ると、睡眠のリズムを後ろにずらしやすくなります。「自分はカフェインに強いから大丈夫」と感じていても、知らないうちに眠りの質に影響していることがあります。
夜中の間食・喫煙・激しい運動が睡眠に与える影響
眠れない時間が長引くと、つい何かを食べたり、タバコを吸ったり、気分転換のつもりで激しく体を動かしてしまうこともあります。しかし、これらも眠れない時には控えたい行動です。
夜中の間食は、消化器官を再び活動モードにし、体温も上げやすくなります。特に脂っこいものや甘いものを多く摂ると、体が休息モードに入りにくくなり、かえってだるさを残すことがあります。
喫煙は、ニコチンという成分の刺激で一時的にスッキリした感覚を与えますが、これは眠気を遠ざける方向に働くことが多くなります。さらに、呼吸器にも負担がかかりやすく、長期的には睡眠の質を下げる要因にもなり得ます。
激しい運動は、日中であればストレス解消や睡眠の質向上につながることがありますが、眠れない深夜に突然始めると、心拍数や体温が上がりすぎて、眠りモードから遠ざかってしまいます。
ここで、よくあるNG行動とおすすめの代替行動を表に整理しておきます。この表は、「自分がやってしまいがちなパターン」を見つけて、どの行動から変えるかを決めるヒントとして使ってみてください。
| 眠れない時のNG行動 | なぜやってはいけないか | 今日からできる代替行動 |
|---|---|---|
| 布団の中でスマホやSNSを長時間見る | 光と情報刺激で脳が興奮し、メラトニン分泌が抑えられやすい | いったんベッドから出て、明るさを落とした部屋で紙の本や雑誌を静かに読む |
| 寝酒としてアルコールを飲む | 寝つきは良くても眠りが浅くなり、夜中の覚醒が増えやすい | 温かいノンカフェイン飲料(白湯やハーブティーなど)に置き換える |
| 夜中にカップラーメンやお菓子を食べる | 消化活動で体温が上がり、体が休息モードに入りにくくなる | 「口が寂しい」ときは少量の水を飲む、または深呼吸で気を紛らせる |
| 眠れないイライラを紛らわせるために激しい筋トレをする | 心拍数と体温が上がり、さらに目が冴えやすくなる | 軽いストレッチや、首・肩を回す程度の運動にとどめる |
この表を見ると分かるように、「やってはいけないこと」をゼロにするのではなく、「その場でできる現実的な代替行動を用意しておく」ことが、無理のない対策になります。
眠れない時にやってはいけない考え方とマインドセットの対策
行動面だけでなく、考え方のクセもまた、「眠れない時にやってはいけないこと」に含まれます。ここでは、代表的な思考パターンと、その手放し方のヒントを紹介します。
「今眠れないと明日が終わる」と決めつけない
眠れない時、多くの人は「明日大事な予定があるのに」「このままでは仕事でミスをする」と、最悪の未来を想像してしまいます。この「明日が終わる」といった決めつけは、不安をさらに強め、眠れない状態を長引かせてしまいます。
もちろん、睡眠不足が続けば日中の集中力に影響が出ることはありますが、一晩の眠れなさが、そのまま明日のすべてを台無しにするとは限りません。実際には、緊張や工夫で何とか乗り切れる日も多くあります。
ここで大切なのは、「眠れない夜がある=すべてがダメになる」と結びつけすぎないことです。眠れない時にやってはいけないことは、「まだ起きてもいない未来を、頭の中で何度も最悪の形でリハーサルする」ことだと言えます。
自分を責める思考パターンを手放す
「また眠れなかった自分はダメだ」「睡眠のことすら上手くできないなんて」と、自分を責める言葉が頭の中に浮かぶこともあります。しかし、自分を責めるほど、心と体は緊張し、眠りから遠ざかってしまいます。
ここで試してみたいのは、「責める言葉」を「観察する言葉」に置き換えることです。例えば、「また眠れなかった。ダメだ」ではなく、「今日はなかなか眠れない日なんだな」と状況をそのまま言い表してみます。たったこれだけでも、自分との距離の取り方が少し変わり、心の圧迫感が和らぐことがあります。
完璧な睡眠を求めすぎない習慣づくり
睡眠に関する情報が世の中に増えたことで、「八時間眠らないといけない」「夜中に一度でも起きてはいけない」など、理想の睡眠像に縛られてしまう人もいます。しかし、実際の睡眠は日によって揺らぐものであり、完璧である必要はありません。
完璧主義的な睡眠観は、「少しでも理想から外れると不安になる」という状態を生み、かえって不眠を助長することがあります。**眠れない時にやってはいけないことの一つは、「理想の睡眠から少し外れただけで、自分を厳しく評価してしまうこと」**です。
「今日は少し短かったけれど、まあ何とかなる範囲かな」「この一週間は忙しかったから眠りも乱れやすいよね」といった柔らかい捉え方を練習することで、心の緊張がゆるみ、結果的に眠りやすい土台が整っていきます。
眠れない時に「代わりにやってよいこと・おすすめの過ごし方」
ここまで「やってはいけないこと」を中心に見てきましたが、「では代わりに何をすればいいのか」が分からないと、結局スマホやアルコールに戻ってしまいます。この章では、眠れない時に比較的取り入れやすい過ごし方を紹介します。
ベッドから一度出て静かな行動に切り替える方法
眠れない状態でベッドの中で長く過ごし続けることは、先ほど説明したように「ベッド=眠れない場所」と脳が覚えてしまう原因になります。そのため、「眠れない時にやってはいけないこと」を避ける一つの方法として、「眠れない状態が続くときはいったんベッドから出る」という選択肢があります。
目安としては、体感で二十分〜三十分ほど眠れない状態が続いたと感じたら、いったんベッドから出て、別の部屋か、同じ部屋でも椅子や床など別の場所に移動してみます。そのうえで、少し暗めの照明の下で、紙の本を読む、日記をつける、窓の外をぼんやり眺めるなど、穏やかな行動を選びます。
再び眠気を感じてきたら、そこでベッドに戻ります。「眠れないベッドにとどまり続ける」のではなく、「眠くなってきたらベッドに戻る」というルールを設定することで、ベッドと眠りの結びつきを少しずつ取り戻していくイメージです。
呼吸法や軽いストレッチなど身体をゆるめる方法
眠れない時にやってはいけないことが「興奮を高める行動」であるならば、代わりに選びたいのは「体と呼吸をゆるめる行動」です。ここでは、比較的取り入れやすい例を紹介します。
例えば、背もたれにもたれかかるか、ベッドの縁に座った状態で、ゆっくりと息を吐くことから始めます。四秒かけて鼻から息を吸い、六秒かけて口から細く長く吐き出していきます。このとき、「息を吐く時間を長めにする」ことがポイントです。数分続けるだけでも、心拍数が落ち着きやすくなります。
ストレッチであれば、首をゆっくり左右に傾けて、片側ずつ伸びる感覚を味わったり、肩をすくめてストンと落とす動きを繰り返したりするだけでも構いません。大切なのは、「痛いほど伸ばさないこと」「呼吸を止めないこと」です。
光と環境を整える具体的な工夫
眠れない時にやってはいけないことの一つに、「眩しい光を浴び続ける」というものがあります。逆に言えば、光と環境を少し整えるだけでも、体は眠りモードに入りやすくなります。
照明は、できるだけ暖色系で明るさを落としたものに切り替えます。天井の強い照明は消し、スタンドライトや間接照明だけにするのも一つの方法です。カーテンの隙間から外の光が入って気になる場合は、できる範囲で遮光カーテンやアイマスクを活用してみてください。
また、眠れない時に焦って時計を何度も確認してしまうと、不安が増幅しやすくなります。可能であれば、時計の表示が目に入らない位置に置き直し、「時間ではなく、自分の体の感覚」に意識を向けてみることも一つの工夫です。
ここで、「眠れない時に避けたい環境」と「おすすめの環境」を表に整理します。この表は、自分の寝室の状況を見直すチェックリストとして活用してみてください。
| 眠れない時に避けたい環境 | なぜ避けたほうがよいか | おすすめの環境の工夫 |
|---|---|---|
| 白く明るい天井照明をつけたまま過ごす | 脳が「まだ昼」と判断し、眠りモードに切り替わりにくい | 暖色系のスタンドライトや常夜灯だけにして、部屋全体を少し暗めにする |
| 枕元にスマホと大きく光る目覚まし時計を置く | 光と時間の情報が不安や焦りを強めやすい | スマホはベッドから手の届かない場所に置き、時計は見えない位置に移動する |
| 部屋が散らかっていて、仕事の書類やPCが視界に入る | 「やらなきゃいけないこと」を思い出し、頭が休みにくい | 寝る前に数分だけ片付けタイムを取り、「寝室は休むための場所」に近づける |
すべて完璧に整える必要はありません。まずは一つだけ、「今の環境でいちばん変えやすいポイント」を選び、一〜二週間試してみることから始めてみてください。
タイプ別に見る眠れない時のやってはいけないことと対策方法
眠れない理由は人それぞれです。同じ「眠れない時にやってはいけないこと」でも、当てはまり方はタイプによって変わります。ここでは、いくつかの代表的なタイプに分けて、注意したいことと対策の方向性を整理します。
仕事ストレスや考えごとで眠れない人の場合
仕事の締め切り、人間関係、将来の不安など、考えごとが頭の中をぐるぐる回って眠れないタイプの方は多くいます。このタイプの方にとって、「やってはいけないこと」の一つは、布団の中で考えごとの続きをし続けることです。
ベッドに入った後に重要なメールを読み返したり、明日のプレゼン内容を頭の中で何度もシミュレーションしたりすると、脳はますます活動モードになってしまいます。代わりに、「考えごとは布団に入る前に紙に書き出す」「明日のToDoリストを寝る前に作り、続きは明日の自分に任せる」といった習慣を取り入れてみてください。
また、「考えないようにしよう」と強く思うこと自体がプレッシャーになります。考えが浮かんできたら、「また仕事のことを考えているな」と気づき、意識を呼吸や体の感覚に戻す練習を少しずつ重ねていくことが大切です。
スマホ依存気味で眠れない人の場合
布団に入ってからもSNSや動画を長時間見てしまい、「気づいたら深夜になっていた」という経験が続く場合、眠れない時にやってはいけないことの中心は、スマホの使い方になります。
このタイプの方には、「気合でやめる」よりも、「物理的に届きにくくする」工夫が役立ちます。例えば、スマホを寝室の外で充電する、ベッドから立ち上がらないと手が届かない位置に置くなどの方法です。アラームが必要な場合は、シンプルな目覚まし時計を使うことも検討できます。
また、寝る前のスマホ時間をいきなりゼロにするのが難しい場合は、「就寝予定時刻の三十分前になったら画面をオフにする」「二十二時以降は動画ではなく音だけのコンテンツにする」といった、段階的なルールを作ると現実的です。
生活リズムの乱れが原因で眠れない人の場合
平日と休日で起きる時間や寝る時間が大きく違う人、シフト勤務で日によって生活リズムが変わる人は、「眠くなる時間そのもの」が不安定になりやすくなります。このタイプの方にとっての「眠れない時にやってはいけないこと」は、「休日に昼過ぎまで寝てしまうこと」や「眠れない夜にずっとベッドで横になり続けること」です。
生活リズムを整えるためには、「起きる時間」をまず安定させることが重要です。たとえ前の晩に眠れなくても、起床時間を大きくずらさないことが、体内時計を前に進め続けるポイントになります。そのうえで、どうしても眠い日は短い昼寝で補い、夜にまとめて帳尻を合わせようとしないことが大切です。
ここで、タイプ別に「やってはいけないこと」と「おすすめの対策」を表にまとめます。自分に近いタイプを探しながら読んでみてください。
| タイプ | 眠れない時にやってはいけないこと | おすすめの対策の方向性 |
|---|---|---|
| 考えごと・仕事ストレス型 | 布団の中で仕事のメールを読み返す、明日の予定を頭の中で繰り返しシミュレーションする | 就寝前に「頭の中のToDo」を紙に書き出し、続きは明日に回す習慣を作る |
| スマホ依存型 | ベッドの中でSNS・動画・ゲームを延々と続ける | スマホを寝室の外で充電する、就寝三十分前に画面をオフにするなど物理的なルールを決める |
| 生活リズム乱れ型 | 眠れない夜に朝までベッドでだらだら過ごし、翌日に昼過ぎまで寝てしまう | 起床時間を一定に保ち、必要に応じて短い昼寝で調整する。夜に眠くなければ一度ベッドから出て静かに過ごす |
この表は、自分の傾向を「ラベル化」するためのものではなく、「だからこそ、どの工夫が合いそうか」を考えるための材料として使ってみてください。
専門機関への相談を検討したい目安
ここまでお伝えしてきた「眠れない時にやってはいけないこと」「代わりにできること」は、あくまで生活習慣や環境の工夫として、多くの人が試しやすい一般的な方法です。一方で、セルフケアだけでは対応が難しいケースもあります。
この記事は医療行為や診断を行うものではなく、非医療の一般的な情報提供にとどまります。その前提のうえで、「そろそろ専門機関への相談も検討したほうが良いかもしれない」目安を整理しておきます。
期間と頻度から見る相談のタイミング
生活習慣や光環境、スマホの使い方などを見直してもなお、「週の半分以上で眠れない日が続く」「眠りに入るまで一時間以上かかる状態が一か月以上続いている」といった場合は、一度専門家に相談してみる価値があります。
一時的なストレスや環境の変化による不眠は、ある程度時間とともに落ち着いてくることもありますが、長期化している場合は、からだ・心・生活環境を包括的に見直す必要があるかもしれません。
日中の生活への影響が大きい場合
眠れない状態が、夜だけでなく日中の生活にも強く影響している場合も、相談を考えたいサインです。たとえば、強い眠気で運転中にヒヤリとすることが増えた、仕事や勉強のミスが明らかに増えた、人と話すのがつらく引きこもりがちになっている、といった変化です。
また、「何をしても楽しく感じない」「理由もなく気分が落ち込む日が続く」といった心の状態の変化が気になる場合も、睡眠とメンタルの両面から専門家と一緒に整理していくことが役立つことがあります。
自分だけで抱え込まないための考え方
眠れないことは、とても個人的な問題に感じられますが、実際には多くの人が経験するものです。「このくらい我慢しなきゃ」「弱音を吐いてはいけない」と自分だけで抱え込むほど、不安や孤独感が強まってしまうことがあります。
相談することは、決して「弱さの証」ではなく、「自分の状態をきちんと知ろうとする前向きな一歩」です。セルフケアと専門家のサポートをうまく組み合わせていくことで、長い目で見たときに、より自分を大切にできる土台が整っていきます。
眠れない時にやってはいけないことに関するよくある質問(Q&A)
ここでは、「眠れない時 やってはいけないこと」について、よくある疑問とその答えをまとめます。自分の状況に近いものがあれば、参考にしてみてください。
Q1. 眠れない時にどうしてもスマホを触ってしまいます。完全にやめられないと意味がありませんか。
A1. 完全にゼロにできれば理想的ですが、現実的には「減らすだけ」でも意味があります。例えば、「布団に入ってからは触らない」「就寝予定時刻の三十分前に電源を切る」など、自分にとって実行しやすいルールを一つ決めてみてください。それだけでも、光と情報の刺激が減り、眠りやすさが変わってくる可能性があります。
Q2. 眠れない時にお酒を飲むと、すぐに眠れるのでやめづらいです。
A2. 寝酒が習慣化すると、「お酒がないと眠れない」という状態になりやすく、長期的には眠りの質の低下や健康への負担につながる可能性があります。いきなりやめるのが難しい場合は、量を少しずつ減らしたり、飲む時間を早めたりすることから始めてみてください。同時に、温かい飲み物やストレッチなど別のリラックス方法を増やしていくと、少しずつ「お酒に頼らない寝る準備」がしやすくなります。
Q3. どうしても眠れない時、薬局で買える睡眠改善薬を飲んでもいいのでしょうか。
A3. 市販の睡眠改善薬は、一時的な不眠に対して利用されることがありますが、自己判断で長期間続けることは避けたほうが良いとされています。使用前には必ず説明書を読み、不安や疑問がある場合は薬剤師や医師に相談してください。この記事では、薬の使用について具体的な指示は行いません。あくまで一般的な情報として、「長く続く不眠や強い不調がある場合は、早めに専門機関に相談する」ことをおすすめします。
Q4. 眠れない時に、朝まで起きていてもいいですか。
A4. 一晩だけであれば、どうしても眠れずに朝を迎えてしまうこともあります。その場合でも、翌日に昼過ぎまで寝続けてしまうと、体内時計がさらに後ろにずれやすくなります。可能であれば、翌日はいつもより少し早め〜同じ時間に起き、必要であれば短い昼寝でしのぎつつ、夜に眠気を取り戻していくほうが、長期的にはリズムを整えやすくなります。
Q5. 眠れない時に本を読むのは、やってはいけないことには入らないのでしょうか。
A5. 紙の本や雑誌を、弱い照明の下で静かに読むことは、多くの場合「やってはいけないこと」には含まれません。ただし、内容があまりにも刺激的だったり、つい読み続けてしまうようなもの(スリラー小説や仕事の専門書など)は、かえって興奮を高める可能性があります。できれば、物語の進みが緩やかな本や、心が落ち着く内容のエッセイなどを選ぶと良いでしょう。
用語解説|眠れない時と睡眠を理解するためのキーワード
ここでは、本文に出てきた専門用語や紛らわしい言葉を、眠れない時の対処というテーマに沿って簡単に整理しておきます。
不眠とは、「寝つきにくい」「途中で何度も目が覚める」「朝早く目が覚めてその後眠れない」「眠った気がしない」といった状態が、一定期間続いていることを指す言葉です。原因や程度は人によって異なり、一時的なものから、専門的な対応が必要なものまでさまざまです。
自律神経とは、心臓の鼓動や呼吸、消化、体温調節などを自動的にコントロールしている神経の仕組みです。活動モードの交感神経と、休息モードの副交感神経があり、ストレスや生活リズムの乱れによってバランスが崩れると、眠れない感覚につながることがあります。
メラトニンとは、主に夜になると分泌が増えるホルモンで、「眠りのスイッチ」のような働きを持つとされています。夜に強い光を浴びると、このメラトニンの分泌が抑えられやすいと考えられています。
寝つきとは、「布団に入ってから実際に眠るまでの時間」を指す言葉です。寝つきの良し悪しは、その日の心身の状態や環境によっても変わります。寝つきが悪い日があったとしても、それだけで自分を責める必要はありません。
睡眠の質とは、「何時間眠ったか」という量だけでなく、眠りの深さ、途中で目が覚めにくいかどうか、朝の目覚めのスッキリ感など、眠り全体の中身を表す言葉です。眠れない時にやってはいけない行動を減らし、環境や習慣を整えることは、この睡眠の質を支える土台づくりにつながります。
まとめ|全部を完璧にやらなくていい。まずは「やらないこと」を一つ決めてみる
ここまで、眠れない時にやってはいけないことをテーマに、焦りや考え方の悪循環、スマホやアルコールなどのNG行動、代わりにできる穏やかな過ごし方、タイプ別の工夫、専門機関への相談目安、よくある質問、用語解説まで幅広くお伝えしてきました。
あらためて重要なポイントを整理すると、第一に、眠れない時には「何をするか」以上に「何をしないか」が睡眠の質を守るカギになるということです。スマホを見続ける、寝酒に頼る、ベッドの中で考えごとを続ける、といった行動を少し減らすだけでも、長い目で見れば眠りやすさに違いが出てきます。
第二に、眠れない夜があること自体は、誰にでも起こり得る自然な揺らぎだということです。一晩眠れなかったからといって、明日が完全に終わるわけではありませんし、自分の価値が下がるわけでもありません。「今日はたまたまそういう日なんだな」と捉えることができれば、その夜のつらさは少し和らぎます。
そして第三に、全部を完璧にやらなくていいということを、最後にもう一度お伝えしたいと思います。生活環境や仕事、家族の状況によって、理想どおりの睡眠習慣を一気に整えることは難しいのが普通です。その中で、「今日はこれだけはやらない」「この行動だけは別のものに置き換えてみる」と、できる範囲の一歩を選ぶことが、現実的で優しいやり方です。
もし、この記事の中から今日一つだけ選ぶとしたら、何を「やらない」と決めるのがいちばん負担が少なそうでしょうか。布団の中でのスマホかもしれませんし、寝る直前のカフェインかもしれません。あるいは、「眠れない自分を責めることをやめてみる」という選択でも構いません。
**大切なのは、「まずは一つだけ選んで、今夜から試してみる」ことです。**小さな「やらない」を積み重ねていくうちに、「以前より眠れない夜のつらさが軽くなってきた」「眠れる日が少しずつ増えてきた」と感じられる日が、きっと少しずつ増えていくはずです。あなたの生活リズムや心の状態に合ったペースで、無理なく取り組める工夫を、一緒に育てていきましょう。
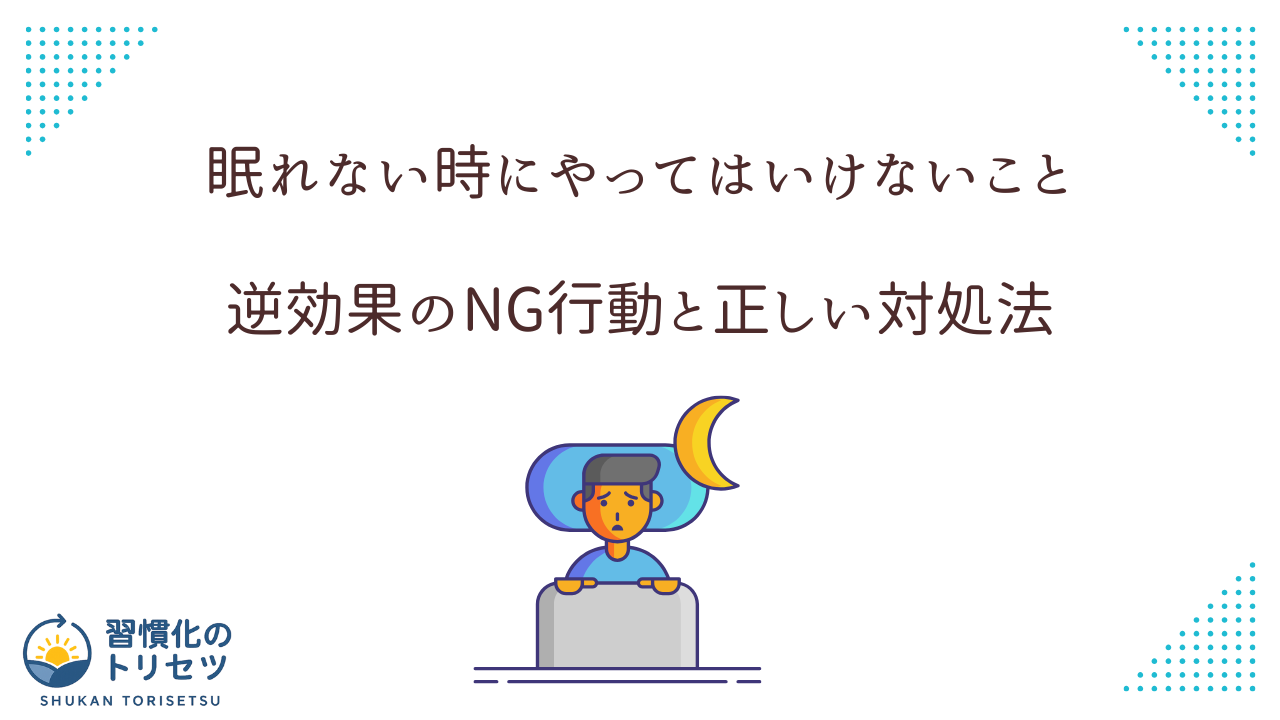
コメント