目覚ましは鳴っているのに、朝スッキリ起きられない。何度もスヌーズを押してしまい、慌てて飛び起きてバタバタと家を出る。そんな朝が続くと、「自分は朝が弱いタイプだから仕方ない」とあきらめたくなってしまいますよね。
とはいえ、「朝 スッキリ 起きる 方法」「生活リズム 整え方」などと検索してここにたどり着いたということは、どこかで今のままではつらい、と感じているはずです。仕事や家事、育児、通学のパフォーマンスを上げたい、休みの日もダラダラせずに有意義に過ごしたいなど、朝のスタートを変えたい理由も人それぞれだと思います。
まずお伝えしたいのは、朝スッキリ起きる力は「生まれつきの才能」ではなく、生活リズムと環境の整え方で大きく変えられる部分が多いということです。夜更かしが続いている人でも、少しずつ生活リズムを調整していくことで、「前より起きやすくなった」と感じられる可能性は十分にあります。
この記事の結論を先にまとめると、ポイントは次の3つです。
① 朝スッキリ起きられない原因は、体内時計のズレ・寝る前の習慣・起き方のパターンの3つに分けて考えると整理しやすい
② 生活リズムの整え方は、「起きる時間をそろえる」「朝の光と動きを増やす」「夜の刺激と光を減らす」というシンプルな方法から始めると続けやすい
③ 完璧な早寝早起きを目指すよりも、自分の生活に合わせて小さな対策を1つずつ増やしていくことで、数週間〜数か月かけて体内時計が整ってくる
この記事では、朝スッキリ起きるための生活リズムの整え方を、非医療の範囲で、自分で実践しやすい行動レベルの方法に落とし込んで解説します。今日から「どの時間帯に、何を少し変えてみるか」が見えるように書いていきますので、気軽に読み進めてみてください。
朝スッキリ起きられない原因を理解する|生活リズムが乱れる3つのポイント
朝スッキリ起きるための生活リズムを整えるには、まず**「なぜ今、朝がつらいのか」という原因を大まかに把握すること**が大切です。何となく「夜更かししているから」「年齢のせいだから」とまとめてしまうと、対策がぼんやりしてしまい、どこから変えればいいか分からなくなってしまいます。
ここでは、朝スッキリ起きられない原因を、「体内時計のズレ」「夜の過ごし方」「朝の起き方」の3つの視点から整理します。自分に当てはまりそうな部分にチェックを入れるつもりで読んでみてください。
体内時計の乱れが原因で朝スッキリ起きられないケース
人には、からだの中に**「体内時計」と呼ばれるざっくりとした時間のリズム**があります。本来は、朝になると活動モードに、夜になると休息モードに切り替わるように働いていますが、このリズムがずれると、朝になってもからだが起きる準備を整えられず、スッキリ目が覚めにくくなります。
体内時計が乱れる原因としては、夜遅くまで明るい光を浴び続けている、平日と休日で起きる時間が大きく違う、日中あまり外に出ず光を浴びていない、といった生活リズムのクセが関係しやすいと考えられています。
「平日は早起き、休日は昼まで寝てしまう」生活を続けていると、体内時計は毎週末ごとにずれていくイメージになります。その結果、月曜日の朝が特につらく感じられたり、週の後半までだるさが残ったりしやすくなるのです。
夜の過ごし方が原因で生活リズムが乱れているケース
朝スッキリ起きるためには、言うまでもなく前日の夜にしっかり眠れていることが前提になります。ところが、寝る直前までスマホやパソコンの画面を見ていたり、仕事や家事をギリギリまで続けていたりすると、からだは「まだ活動する時間だ」と判断しやすくなります。
特に、寝る直前の強い光と情報量の多いコンテンツは、脳を興奮させて生活リズムの切り替えを遅らせる原因になりやすいと考えられています。布団の中でSNSをチェックする、動画を見始めたら止まらなくなる、といった習慣が続いている場合、「眠る時間を削っている」という意識がなくても就寝時刻は少しずつ遅くなっていきます。
また、夕食が寝る時間ギリギリになってしまう、夜遅くにカフェインやアルコールをとる頻度が高い、といった習慣も、眠りの深さや質に影響し、結果的に朝スッキリ起きられない原因につながりやすくなります。
朝の起き方のパターンが原因でスッキリ感を失っているケース
生活リズムが整っていないと、「目覚ましを何個もかけているのに起きられない」「スヌーズを何度も繰り返してしまう」「ギリギリまで布団から出られない」といった起き方のクセがつきやすくなります。
こうした起き方を続けていると、脳が「アラームが鳴っても、どうせすぐには活動を始めない」と学習してしまい、目覚ましに対する反応が鈍くなることがあります。結果として、アラームが鳴ってもぼんやりしたままスマホを止めるクセがつき、朝スッキリ起きるきっかけを逃してしまいやすくなります。
また、起きてすぐにスマホを見てベッドの中でしばらく過ごす、カーテンを開けずに暗い部屋のままで準備を始める、といった朝の習慣も、体内時計に「今は朝だ」と伝える合図が弱くなり、生活リズムが整いにくくなる原因となります。
朝スッキリ起きるための生活リズムの基本|一日の流れを設計する方法
原因のイメージがつかめたところで、ここからは朝スッキリ起きるための生活リズムをどう整えていくかを、1日の流れという視点で解説していきます。
大切なのは、「早寝早起き」という一言で片付けるのではなく、「朝」「日中」「夜」のそれぞれの時間帯を、体内時計のリズムに合わせた過ごし方に少しずつ近づけていくことです。
朝の過ごし方を整える生活リズムの方法
朝スッキリ起きるためには、「目覚めた直後の30分〜1時間」をどう使うかが非常に重要です。この時間帯に光を浴びる・からだを動かす・一定のルーティンをこなすことで、生活リズムを整えるスイッチが入りやすくなります。
まず意識したいのは、起きたらできるだけ早くカーテンを開ける、もしくは部屋の照明をつけて明るくすることです。光は体内時計にとって強いリセット信号となるため、「今が朝だ」とからだに伝える意味があります。
ベッドの中で長時間スマホを見る習慣がある場合は、「アラームを止めたらそのまま起き上がる」「スマホに触るのは顔を洗った後」といったルールを一つだけ決めてみるのも効果的です。朝一番の光と動きを優先することで、生活リズムが少しずつ整っていきます。
可能であれば、起きてから1時間以内に軽いストレッチや短い散歩を取り入れると、**血流が良くなり、脳も目覚めやすくなります。**家の中でできる範囲で構わないので、「毎朝同じ順番の動き」を繰り返すことで、朝のリズムを固定しやすくなります。
日中の活動で生活リズムを支える方法
朝スッキリ起きるための生活リズムは、夜だけでなく**日中の過ごし方にも支えられています。**特に、「どれくらいからだを動かしているか」「どの時間帯に光を浴びているか」は、夜の眠気に大きく影響しやすいポイントです。
日中ほとんど動かないままデスクワークだけで終わってしまうと、からだは「体力を使い切っていない」と感じ、夜になっても眠気が訪れにくくなることがあります。仕事や家事の合間に意識して立ち上がる、短時間の散歩を取り入れる、階段を使う回数を増やすなど、小さな動きを積み重ねるだけでも生活リズムは少しずつ変わっていきます。
また、日中にまったく外へ出ない日が続くと、自然光を浴びる時間が不足し、体内時計が後ろ寄りにずれていきやすくなります。可能であれば、昼休みに数分だけ外を歩く、窓際で軽く体を伸ばすなど、光を浴びる時間を意識的に確保することが、朝スッキリ起きるための土台づくりになります。
夜の過ごし方を整える生活リズムの方法
夜は、「眠るための助走」をつける時間帯と考えると、生活リズムの整え方がイメージしやすくなります。寝る直前だけでなく、寝る2〜3時間前から穏やかに過ごすことを意識すると、自然と眠気が訪れやすくなります。
夕食の時間は、可能であれば就寝の2〜3時間前までに終えることを目安にしてみてください。寝る直前の重い食事や大量の間食は、消化にエネルギーが使われ、からだが「休むモード」になりきれず、翌朝まで疲れが残りやすくなります。
また、夜遅い時間のカフェインやアルコールも、眠りの質に影響する可能性があります。寝る4〜6時間前からはカフェインを控える、アルコールを飲む場合は量や時間を見直すなど、「翌朝の自分がスッキリ起きやすい選択かどうか」で判断する癖をつけていくと、徐々に生活リズムが朝型に近づいていきます。
ここで、朝スッキリ起きられない人がやりがちな生活リズムのNGパターンと、それをどう変えると良いかを表にまとめておきます。この表は、「自分の生活のどこから整えればいいか」を見つけるヒントとして活用してください。
| 現在の生活リズムのNGパターン | 朝スッキリ起きるために変えたい生活リズムの整え方 |
|---|---|
| 平日は早起きだが、休日は昼まで寝てしまう | 休日も「平日よりプラス1〜2時間まで」の起床時間にとどめるよう意識する |
| 起きてもすぐにカーテンを開けず、暗い部屋のままスマホを見る | 起きたら最初にカーテンを開けるか照明をつけて、光を浴びてからスマホを見るよう順番を変える |
| 日中ほとんど外に出ず、座りっぱなしで過ごしている | 昼休みや休憩時間に数分だけでも外を歩く、階段を使うなど、日中の光と動きを意識して増やす |
| 寝る直前まで動画視聴やSNSチェックを続けている | 寝る60分前からは画面を見る時間を減らし、照明を落として静かな時間をつくる |
| 就寝直前に重い食事や夜食をとることが多い | 夕食は寝る2〜3時間前までに済ませ、遅くなる日は内容を軽めに調整する |
この表の見方としては、自分に当てはまるNGパターンを一つ選び、その右側の「整え方」だけをまず実践してみるのがおすすめです。一度にすべて変えようとすると負担が大きくなるため、生活リズムの整え方は「一点集中」で少しずつ進めていくイメージを持つと続けやすくなります。
朝スッキリ起きるための具体的な対策|起き方・寝方・準備の方法
ここからは、朝スッキリ起きるために今日から取り入れやすい具体的な対策を、「起き方」「寝方」「前日の準備」の3つの切り口で紹介していきます。
大掛かりなことをする必要はなく、生活リズムを少しだけ朝型に寄せるための小さな方法を組み合わせていくことがポイントです。
起き方の対策|朝スッキリ起きるトリガーを増やす方法
起き方の対策として、まず意識したいのは「アラームの扱い方」と「布団から出るまでの流れ」です。朝スッキリ起きるためには、アラーム=活動開始の合図という習慣をからだに覚えさせることが重要になります。
一つの方法として、アラームを「起きる時間の1回だけ」にするのではなく、「起床5〜10分前の予告」と「実際に起きる時間」の2段階に分けるやり方があります。予告のアラームで一度意識を浮上させ、本番のアラームで起き上がるイメージです。
また、スマホや目覚まし時計は、手を伸ばせばすぐ止められる場所ではなく、ベッドから少し離れた位置に置くと、起き上がるきっかけを作りやすくなります。立ち上がってアラームを止め、そのままカーテンを開けたり洗面所に向かったりする流れを習慣にすると、生活リズムの切り替えがスムーズになります。
寝方の対策|夜のスイッチを切り替える方法
朝スッキリ起きるための生活リズムづくりは、夜のスイッチの切り替え方にも大きく左右されます。ここでは、「寝る前90分の過ごし方」と「寝室の環境」の2点に絞って考えてみましょう。
寝る前90分は、スマホやパソコンの画面・強い光・情報量の多いコンテンツを少しずつ減らしていく時間として捉えるとよいでしょう。理想としては、寝る30〜60分前には画面から離れ、照明を少し落として静かに過ごす時間をつくることです。
その代わりに、軽いストレッチや深呼吸、翌日の持ち物の準備、手帳に簡単な日記を書くなど、頭を使い過ぎない穏やかな行動に切り替えていきます。これにより、「ここから先は休む時間」という合図を体内時計に送ることができ、眠りに入りやすくなります。
寝室の環境も、朝スッキリ起きるための大事な土台です。明るすぎる、暑すぎる・寒すぎる、騒音が多いといった環境は、眠りの質を下げる原因になります。遮光カーテンやアイマスク、耳栓、寝具の素材の見直しなど、一度整えてしまえば毎晩の睡眠に良い影響が期待できる部分から手をつけてみましょう。
前日の準備の対策|翌朝の自分を助ける生活リズムの工夫
朝スッキリ起きるためには、「翌朝の自分をどれだけラクにしてあげられるか」という視点も大切です。朝にやることを減らし、迷いを減らす準備をしておくと、起きるハードルが下がります。
例えば、翌日の服を前日の夜に決めておく、カバンの中身を準備して玄関付近に置いておく、朝食のメニューを簡単なものに決めておく、といった工夫があります。朝起きてから「何を着よう」「何を持っていこう」と考える手間を減らすことで、生活リズムの始動がスムーズになりやすくなります。
また、「起きたら最初にすること」を一つだけ決めておくのも効果的です。例えば、「カーテンを開ける」「コップ1杯の水を飲む」「ベランダに出て空気を吸う」といったシンプルな行動を毎朝同じ順番で行うことで、からだと心が徐々に朝モードに切り替わっていきます。
ここで、起き方・寝方・準備の対策をタイプ別に整理した表を紹介します。この表は、自分がどの対策から始めると朝スッキリ起きやすくなりそうかを選ぶヒントとして活用してください。
| 悩みのタイプ | 朝スッキリ起きるために優先したい対策 | 具体的な生活リズムの整え方 |
|---|---|---|
| アラームを止めて二度寝してしまう | 起き方の対策を優先する | アラームをベッドから離して置き、起床5〜10分前と本番の2段階に分けてセットする |
| 布団に入ってもなかなか眠れない | 寝方の対策を優先する | 寝る90分前から画面を見る時間を減らし、照明を落としてストレッチや深呼吸の時間をとる |
| 朝の準備に時間がかかり、起きるのが億劫になる | 前日の準備の対策を優先する | 服・カバン・朝食を前日に決めておき、起きたらやることを一つだけ固定する |
表の活用方法としては、自分の悩みに近い行を選び、その中の「優先したい対策」から1つだけ具体策を試してみることです。生活リズムの整え方は、細かくやろうと思えばいくらでも増やせますが、まずは「一つをしっかり続ける」方が、結果として朝スッキリ起きられる実感につながりやすくなります。
朝スッキリ起きる生活リズムを定着させるコツ|マインドセットと継続の方法
生活リズムの整え方は、知識よりも継続がカギになる部分です。ここでは、朝スッキリ起きる習慣を定着させるための考え方と、続ける工夫についてお伝えします。
完璧主義を手放すことが生活リズムの安定につながる
「毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる」「夜は必ず画面を見ないで過ごす」といった理想を高く設定しすぎると、少し崩れただけで「もういいや」と投げ出したくなってしまいます。
大切なのは、生活リズムを整えることを「白か黒か」で判断しないことです。仕事の繁忙期や家族の予定、体調の変化など、生活にはどうしても揺らぎがあります。そんな中で、常に完璧な生活リズムを保とうとするのは、現実的に見ても難しいものです。
そこで、「7割できていれば十分」「崩れてもまた戻せばいい」という柔らかい基準を自分の中に持っておくと、続けやすくなります。例えば、平日のうち3〜4日でも起きる時間をそろえられていれば、それだけでも体内時計には良い影響が積み重なっていきます。
小さな変化を記録してモチベーションを維持する方法
朝スッキリ起きる感覚は、ある日突然劇的に変わるというより、少しずつ「そういえば前よりマシかも」と感じる積み重ねで実感しやすくなります。そのためにも、変化に気づける工夫として「記録」を取り入れてみるのも一つの方法です。
難しいものでなくて構いません。起床時間・就寝時間・その日の体調や気分を、簡単なメモやスマホのアプリに残しておくだけでも、1〜2週間後に振り返ったとき、「ここを変えた日から少し楽になったかもしれない」といった気づきが生まれます。
記録はうまくいかなかった日も含めて、そのまま残しておくことが大事です。「昨日は夜更かししてしまったから、今日は少し早めに画面から離れてみよう」など、生活リズムを微調整するヒントとして使っていきましょう。
自分に合った朝時間の目的を決める方法
朝スッキリ起きる生活リズムを続けるには、「なぜ朝型になりたいのか」という目的を、自分の言葉で持っておくと支えになります。
例えば、「静かな時間にゆっくりコーヒーを飲みたい」「出社前に少し読書をしたい」「子どもが起きる前に一人の時間を確保したい」など、自分にとってワクワクする朝時間の使い方を一つ決めてみてください。
目的があると、「ただ早く起きなければならない」から「その時間を楽しみにしたい」に意識が変わります。これが、結果として生活リズムを整えやすくし、朝スッキリ起きる力を支えてくれます。
専門機関への相談を検討したい目安|生活リズムの工夫だけではつらいと感じるとき
ここまで、朝スッキリ起きるための生活リズムの整え方を中心に、非医療の範囲でできる対策をお伝えしてきました。ただし中には、自分なりに工夫をしてもなかなか変化が出ない場合や、心身の負担が大きくなっている場合もあります。
このセクションでは、どのような状態になってきたら専門機関への相談を検討した方がよいか、一般的な目安の考え方を紹介します。あくまで一つの参考として読みつつ、「何となく気になるな」と感じたときは、早めに誰かに相談するきっかけにしてみてください。
期間と生活リズムの乱れ方から見る相談の目安
誰でも、仕事やプライベートの事情で、しばらく生活リズムが乱れてしまう時期はあります。短期間の夜更かしや、数日の寝不足であれば、状況が落ち着くと自然に戻っていくことも少なくありません。
一方、朝スッキリ起きられない状態が数週間〜数か月と長く続き、生活リズムを整えようと工夫してもほとんど変化が感じられない場合は、専門機関への相談を検討しても良いタイミングです。
特に、起きられないことで遅刻が増えたり、学校や職場に行けない日が続いたりする場合は、自分一人の意思や努力だけで解決しようと抱え込まず、周囲のサポートも視野に入れて考えていくことが大切です。
日中の活動への影響が強く出ている場合の目安
朝スッキリ起きられないだけでなく、日中も強い眠気やだるさが続き、仕事・家事・学業・対人関係などに影響が出ている場合も、相談を検討するサインの一つです。
例えば、運転中に眠気が強く危険を感じる、会議や授業で集中力が続かない、簡単な家事さえ負担に感じるなど、日中の活動に支障が出ているときには、自分を責めるよりも「今はサポートが必要な状態かもしれない」と考えてみることが大切です。
また、生活リズムの乱れに加えて、気分の落ち込みが続いている、何をしても楽しく感じられない、人と会うのがおっくうになっている、といった心の変化が目立つときも、早めに相談先を探しておくと安心です。
気になるサインが重なってきたときの考え方
生活リズムが乱れて朝スッキリ起きられない状態とあわせて、食欲の大きな変化、体重の急な増減、強い不安や焦りの感覚が続く、眠ろうとしてもほとんど眠れない日が何日も続くなど、気になるサインがいくつも重なっているときは、一人で抱え込まずに専門的なサポートを検討することも、自分を守る大切な方法です。
大切なのは、「これくらい我慢すべきだ」と自分を追い込まないことです。生活リズムを整える努力をしてもつらさが続くときには、「頑張りが足りない」のではなく、「頑張り続けるには助けが必要な状況」になっているのかもしれません。
よくある質問(Q&A)|朝スッキリ起きる生活リズムについての疑問
ここでは、「朝 スッキリ 起きる」「生活リズム 整え方」で検索する人が抱きやすい疑問を、Q&A形式でまとめました。自分の状況に近いものがあれば、参考にしてみてください。
Q1. 休日くらいは思い切り寝てもいいですか?
休日に睡眠時間を多めにとること自体は悪いことではありません。ただし、平日との起床時間の差が大きくなると、体内時計が毎週リセットされてしまい、月曜日の朝が特につらくなりやすいと考えられます。
目安としては、平日と休日の起きる時間の差を「プラス1〜2時間以内」におさめておくと、生活リズムが極端に乱れにくくなります。どうしても眠気が強いときは、朝いったん起きて光を浴びてから、短時間の二度寝をするなど工夫してみてください。
Q2. 夜型の生活リズムでも問題がなければ直さなくていいですか?
夜型の生活リズムでも、日中の活動や体調に大きな問題が出ていなければ、必ずしも無理に変える必要はない場合もあります。ただし、社会的な活動時間(仕事や学校、役所の窓口の時間など)とのズレが大きくなると、生活上の不便やストレスが増えやすいという面はあります。
朝スッキリ起きる必要性をどこまで感じるかは人それぞれですが、「日中のパフォーマンスを上げたい」「休日をもっと有効に使いたい」と感じる場合は、少しずつ生活リズムを前倒ししていく工夫を取り入れてみる価値があります。
Q3. 朝スッキリ起きるために運動はどのくらい必要ですか?
特別な運動を長時間行う必要はありません。日常生活の中で「少し息が弾む程度の動き」を毎日〜週に数回取り入れるだけでも、生活リズムの安定に役立つと考えられます。
例えば、通勤時に一駅分多く歩く、エレベーターではなく階段を選ぶ、昼休みに10分だけ散歩をするなど、無理のない範囲でからだを動かす習慣を増やしてみてください。続けやすい運動量を見つけることが、結果として朝スッキリ起きる力を支えてくれます。
Q4. 昼寝をすると朝スッキリ起きられなくなりますか?
昼寝は、取り入れ方によっては体力の回復に役立ちますが、時間帯や長さによっては夜の眠気を減らし、生活リズムを乱す原因になることもあります。
夜の寝つきや朝の目覚めに影響しにくい目安としては、「午後の早い時間帯に15〜30分程度」とされています。夕方以降の長い昼寝は避け、どうしても眠いときは椅子にもたれて目を閉じる程度にとどめておくと、夜の睡眠とのバランスをとりやすくなります。
Q5. どのくらいの期間、生活リズムの工夫を続ければ効果が出ますか?
生活リズムの整え方は、1〜2日で劇的な変化が出ることもあれば、**数週間〜数か月かけて少しずつ朝スッキリ起きられるようになっていく場合もあります。**体内時計が新しいリズムになじむには時間がかかることも多いため、少なくとも1〜2週間は同じ工夫を続けてみることをおすすめします。
そのうえで、「この方法は自分に合っていそうだ」と感じたものは継続し、「あまり変化を感じない」と思うものは別の方法に入れ替えるなど、柔軟に調整していくと、自分だけの生活リズムの整え方が見つかりやすくなります。
用語解説|朝スッキリ起きるために知っておきたい言葉
本文で登場した、生活リズムや睡眠に関する言葉を簡単に整理しておきます。専門用語というより、「こういうイメージの言葉なんだ」と気軽に確認するつもりで読んでみてください。
体内時計
人のからだの中にある、「今は起きて活動する時間」「今は休んで眠る時間」をざっくり決めているリズムのことです。光を浴びる時間や食事の時間、寝起きの時間などによって影響を受け、生活リズムの土台になっています。
朝型・夜型
生活リズムの傾向を表す言葉で、活動しやすい時間帯が主に朝寄りか夜寄りかを指します。生まれつきの傾向もありますが、生活習慣によってもある程度変化します。自分の生活に合った形で、無理のない範囲で調整していくことが大切です。
スヌーズ
目覚ましアラームを止めても、数分後に再びアラームが鳴る機能のことです。便利な反面、何度も繰り返すことで「アラームが鳴ってもすぐ起きなくていい」というクセがつき、かえって朝スッキリ起きにくくなる場合もあります。
スリープルーティン
眠る前に毎日同じように行う、**「眠る準備のための一連の行動」**です。例えば、スマホをやめる→歯を磨く→ストレッチをする→照明を落とす→布団に入る、という流れを毎晩続けることで、からだが「この順番の後は眠る」と覚えやすくなります。
睡眠の質
眠った時間の長さだけでなく、どれくらい深く休めているか、朝どれだけスッキリ起きられるか、といった睡眠全体の状態を指す言葉です。生活リズムを整えることは、睡眠の質を高めるための土台づくりとも言えます。
まとめ|朝スッキリ起きる生活リズムは、小さな一歩から整えていける
ここまで、朝スッキリ起きるための生活リズムの整え方について、原因・具体的な対策・継続のコツ・相談の目安まで、幅広くお話ししてきました。
改めて大切なポイントを整理すると、まず、朝スッキリ起きられない原因は一つではなく、体内時計のズレ、夜の過ごし方、朝の起き方のパターンが重なっていることが多いということです。「自分は根本的に朝が弱い」と決めつけるのではなく、「生活リズムのどこが今いちばん崩れていそうか」を見つめ直すところから始めてみてください。
次に、生活リズムの整え方は、「起きる時間をそろえる」「朝の光と動きを増やす」「夜の刺激と光を減らす」というシンプルな方法から取り入れると続けやすいという点です。起床時間の固定、朝一番のカーテンを開ける習慣、寝る前90分の画面オフなど、小さな工夫でも続けることで体内時計に少しずつ影響していきます。
そして何より、全部を完璧にやろうとしないことが、長い目で見たときにいちばんの近道です。生活リズムは、仕事や家族の予定、体調などさまざまな要素に左右されます。理想通りにいかない日があって当たり前、と考えたうえで、「崩れてもまた戻せる」と自分に許可を出しておくことが大切です。
今日からできることを一つ選ぶとしたら、どれが一番取り入れやすいでしょうか。例えば、**「明日の朝は、アラームを止めたらすぐカーテンを開ける」「今夜は寝る30分前にスマホをやめてみる」「休日の起きる時間を平日プラス1時間以内にしてみる」**など、負担の少ないものからで構いません。
その小さな一歩を1週間続けてみるだけでも、朝の感覚がわずかに変わるかもしれません。もしうまくいかなかったとしても、それは「自分には別の整え方のほうが合いそうだ」と分かったという一つの収穫です。
生活リズムを整えることは、短距離走ではなくマラソンのようなものです。完璧さではなく、「昨日より少しだけ朝が楽になったかも」を積み重ねていくことが、結果として朝スッキリ起きられる自分に近づいていく一番の近道です。
全部を完璧にやる必要はありません。まずは、一つだけ「これならできそう」と思える対策を選び、今日から気軽に試してみてください。その一歩が、これからの朝時間と一日の過ごし方を、少しずつ変えていくきっかけになるはずです。
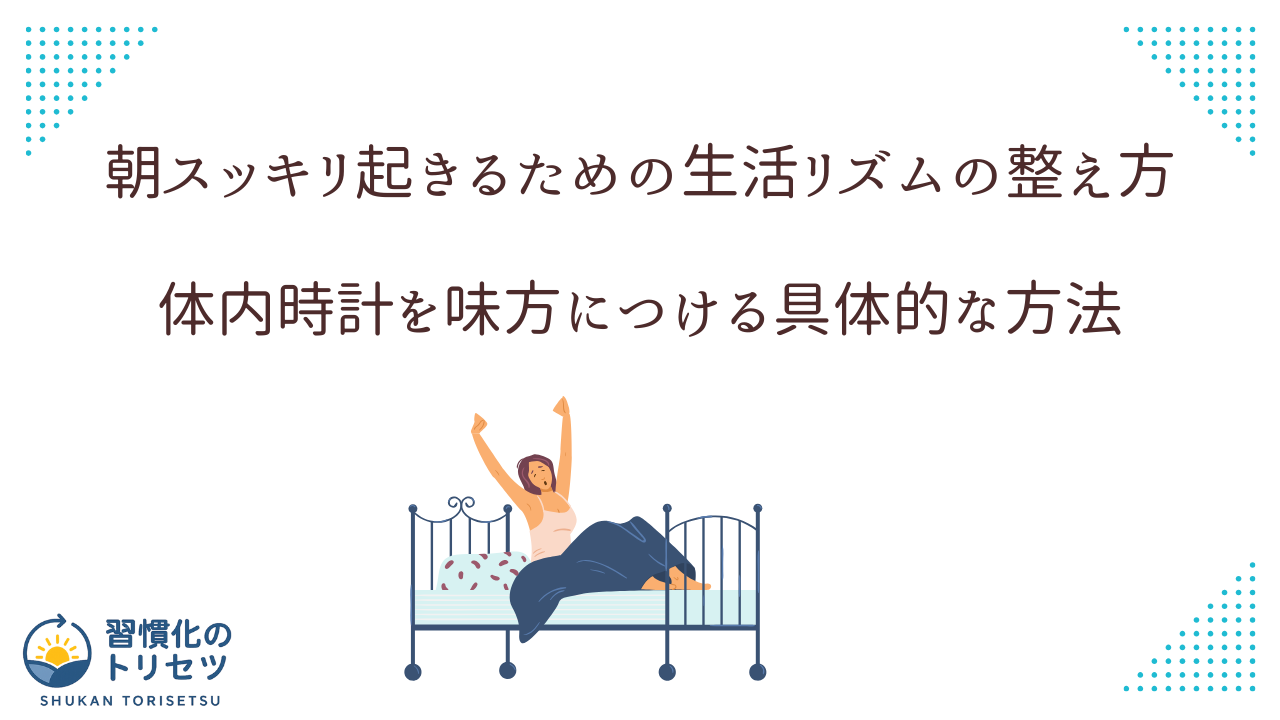
コメント