布団に入ってもなかなか眠れない、夜中に何度も目が覚める、朝起きてもスッキリしない。そんな状態が続くと、「自分は眠る力が弱いのかも」「体がどこか悪いのでは」と不安になりますよね。仕事や家事、育児に追われる日々の中で、ぐっすり眠れない人の多くは、実は病気というよりも生活パターンそのものが「眠りにくいリズム」になっていることが少なくありません。
この記事では、「ぐっすり眠れない人の生活パターン」に注目しながら、どんな習慣や時間の使い方が眠りを妨げているのか、そして今日から現実的に変えられる具体的なステップを、できるだけわかりやすく解説していきます。
先にこの記事の結論をまとめると、ぐっすり眠れない人が見直したいポイントはおおきく次の3つです。
① 「起きる時間」と「光の浴び方」をそろえて、体内時計のリズムを整えること
② 夜遅くのスマホ・カフェイン・長すぎる昼寝など、「眠りを邪魔する生活パターン」を減らすこと
③ 完璧主義で一気に変えようとせず、「一日の流れ」を少しずつ現実的なパターンに組み替えていくこと
この3つをベースに、朝・日中・夜それぞれの時間帯でどんな行動を選ぶと眠りやすくなるのか、「ぐっすり眠れない人の生活パターン」の具体例とともに詳しく見ていきます。
【注意書き・専門性について】
この記事は、睡眠や生活習慣の改善に関する取材・執筆経験を持つライターが、信頼性の高い公的機関の情報や専門書などをもとに、一般的な知識としてまとめたものです。医師や医療専門職による個別の診断・治療を代わりに行うものではなく、あくまで生活習慣を見直すための一般的な情報提供です。強い不調がある場合や心身の状態に不安がある場合には、必ず医療機関や専門家に相談してください。
ぐっすり眠れない人の生活パターンに共通するサインを知る
自覚しにくい「なんとなく不調」と睡眠の関係
ぐっすり眠れない人の多くは、「明らかな病気」とまでは感じていませんが、日常の中でさまざまな小さな不調を抱えています。例えば、朝起きても頭がぼんやりしている、午前中に強い眠気がくる、夕方になると一気に疲れが押し寄せるといった状態です。
こうした「なんとなく調子が悪い」「いつも疲れている」という感覚は、実は睡眠の質が落ちているサインであることが少なくありません。睡眠時間の長さだけを見ると足りているように見えても、生活パターンの乱れによって、眠りが浅くなっていたり、睡眠のリズムがバラバラになっていたりするケースも多いです。
ぐっすり眠れないと起きやすい日中の変化
ぐっすり眠れない生活パターンが続くと、日中の過ごし方にも共通した変化があらわれます。例えば、仕事中に集中力が続かない、ささいなことでイライラしやすくなる、甘いものやカフェインに頼る回数が増えるなどです。これらは単に性格や意志の問題ではなく、「体と脳が休めていないサイン」と考えた方が自然な場合もあります。
さらに、日中の疲れや眠気をカバーするために、帰宅後にダラダラとスマホや動画を見続けてしまう、夕方以降に何杯もコーヒーを飲んでしまう、といった行動につながりやすくなります。これがまた夜の眠りを妨げ、「眠れない→日中つらい→また夜更かし」の生活パターンが固定化されてしまうのです。
生活リズムが乱れる典型的なパターン
ぐっすり眠れない人に共通する生活リズムとして、多く見られるのが次のようなパターンです。
平日は仕事や家事で疲れ切っているのに、帰宅後にスマホや動画視聴で夜更かししてしまい、気づけば午前0〜1時を過ぎている。それでも翌朝は無理やり起きて出勤するため、慢性的な睡眠不足になる。一方、休日は平日の寝不足を取り戻そうとして昼近くまで寝てしまい、日曜日の夜になると目が冴えて眠れない。この「平日と休日の睡眠時間・起床時間の差」が広がるほど、体内時計は乱れやすくなります。
こうした生活パターンが続くと、本人としては「仕事が忙しいから仕方ない」「夜しか自分の時間がない」と感じがちですが、体と脳は確実に疲れをため込み、ぐっすり眠れない状態が定着してしまいます。
ぐっすり眠れない原因を生活パターンから見直す
朝〜日中の過ごし方に潜む原因
睡眠の話というと「寝る前に何をするか」に注目しがちですが、実は朝〜日中の過ごし方もぐっすり眠れるかどうかに大きく影響します。特に重要なのが、起きる時間と光の浴び方です。
起床時間が日によってバラバラだと、体内時計が毎日リセットされず、「今日は何時に眠ればいいのか」が体の中であいまいになります。さらに、起きてすぐにカーテンを開けず薄暗い部屋でダラダラ過ごしたり、在宅勤務で一日中ほとんど外に出なかったりすると、体内時計を調整する強い光を浴びる機会が減ってしまいます。その結果、夜になっても体が「まだ夜だ」と認識しきれず、眠気が訪れにくくなるのです。
また、日中に座りっぱなしでほとんど動かない状態が続くと、体が適度に疲れず、夜になっても「寝るほど疲れていない」状態になりがちです。運動不足が直接不眠の原因とは言い切れませんが、体を適度に使わない生活パターンは、眠りの深さを浅くしやすいと考えられます。
夕方〜夜のNG習慣が眠りを邪魔する
ぐっすり眠れない人の生活パターンで特に多いのが、夕方〜夜の時間帯の「なんとなくの習慣」です。仕事終わりにカフェラテやエナジードリンクを飲む、帰宅後に明るい画面でSNSや動画を延々と見る、夜遅い時間にお腹いっぱい食事をとる、といった行動は、知らず知らずのうちに眠りを遠ざけてしまいます。
カフェインは人によって効き方が違いますが、飲んでから数時間は眠気を感じにくくする働きがあります。夕方以降に何杯もコーヒーやお茶を飲む習慣があると、布団に入っても体内ではまだ「覚醒モード」が続いていることがあります。また、スマホやPCの強い光は、脳に「まだ昼間だ」と錯覚させ、眠りを促すホルモンが出にくくなると考えられています。
さらに、夜遅い時間のドカ食いは、消化の負担が大きくなり、寝ている間も胃腸がフル稼働し続ける状態を招きます。これもまた、深い睡眠に入りにくくなる一因です。
休日の過ごし方と「社会的時差ボケ」
平日の寝不足を休日に取り戻そうとして、昼近くまで寝だめをする人は少なくありません。しかし、この習慣は「社会的時差ボケ」とも呼ばれ、体内時計を大きく乱す原因になります。たとえば、平日は7時起床なのに休日は11時まで寝ていると、体内時計にとっては「4時間の時差がある場所に移動した」のと似た状態になります。
この生活パターンが定着すると、日曜日の夜に眠れない、月曜日の朝に極端にだるい、といった不調が起きやすくなります。ぐっすり眠れない状態から抜け出すには、平日と休日の起床時間の差をできるだけ小さくし、「毎日ほぼ同じ時間に起きて光を浴びる」ことが重要なポイントになります。
今日から変えられる一日の過ごし方の基本パターン
ここからは、ぐっすり眠れない人が現実的に取り入れやすい「一日の基本パターン」をイメージしながら、時間帯ごとのポイントを紹介します。「全部を一気にやる」のではなく、できそうなところから一つずつ試してみてください。
朝のスタートを整える生活パターン
まず意識したいのは、「起きる時間」と「光」です。毎日まったく同じ時間に起きるのが難しければ、「平日は6時〜6時30分の間」「休日も7時までには起きる」といったように、ある程度の幅を持たせつつも大きくずらさないことを目標にします。
起きたらできるだけ早くカーテンを開け、窓の近くで数分間過ごしたり、ベランダに出たりして、朝の光を浴びるようにします。天気が悪い日でも、室内の照明より外の光の方が体内時計を整える刺激になります。朝食はパン一枚でもいいので何か口にすることで、「一日のスタート」を体に伝えることができます。
日中の集中と休憩のリズムをつくる
日中は、長時間座りっぱなしにならないように意識することがポイントです。デスクワークが中心の場合でも、1〜2時間に一度は立ち上がり、数分間歩いたり軽くストレッチしたりするだけでも構いません。体を少し動かして血流を良くすることで、夜の「適度な疲労感」が得られやすくなります。
また、午後の強い眠気に対しては、15〜20分程度の短い昼寝はプラスに働くことがありますが、1時間以上ソファで寝てしまうような長い昼寝は、夜の睡眠を妨げやすくなります。どうしても眠い場合は、昼寝の前にカフェインを少量とり、目覚ましをかけて短時間で切り上げるなど、「夜の睡眠を残しておく」意識を持つとよいでしょう。
夜の「緩やかにスイッチを切る」ルーティンをつくる
ぐっすり眠るためには、夜に「一気に電源オフにする」のではなく、「徐々に暗く静かなモードに切り替えていく」イメージが大切です。理想は、眠りたい時間の1〜2時間前から、脳と体をゆるめる準備を始めることです。
例えば、21時以降はできるだけ仕事や難しい作業を切り上げ、あたたかい飲み物を飲みながら読書をしたり、ストレッチや軽い深呼吸をしたりする時間にします。スマホやPCの使用は、眠りたい時刻の1時間前までに区切りをつけることをひとつの目安にしてみてください。
ここで、ぐっすり眠れない人にありがちな一日の流れと、少し整えた生活パターンの例を、イメージしやすいように表で整理します。
【現在のパターンと改善パターンのイメージ比較】
| 時間帯 | ぐっすり眠れない人によくあるパターン | ぐっすり眠るために意識したい生活パターン |
|---|---|---|
| 朝 | ギリギリまで寝て慌てて起床。カーテンを開ける余裕もなく、朝食は抜きがち。 | 平日・休日ともに大きくずれない時間に起床。起きたらまずカーテンを開けて光を浴び、簡単でも朝食をとる。 |
| 日中 | ほぼ座りっぱなし。強い眠気が来ると、甘いお菓子やカフェインに頼る。 | 1〜2時間ごとに少し立ち上がって歩く。必要なら短時間の昼寝を活用し、夕方以降のカフェインは控える。 |
| 夜 | 帰宅後はずっとスマホや動画を見続け、夜遅くにドカ食い。気づいたら日付が変わっている。 | 眠りたい時間の1〜2時間前から照明をやや落とし、スマホは時間を決めて使用。軽めの夕食とストレッチで体をゆるめる。 |
| 休日 | 昼近くまで寝だめ。夜になっても目が冴え、日曜の夜は特に眠れない。 | 平日より1〜2時間程度の範囲で起床。昼間の活動量を増やし、夜は平日と同じ時間帯に寝床に入る。 |
この表はあくまで一例ですが、自分の一日を思い返しながら、「どの時間帯を少し変えてみるとよさそうか」を考える手がかりとして活用してみてください。一度に全部を変える必要はなく、まずは朝・夜のどちらか一か所から始める方が続けやすくなります。
ぐっすり眠るための環境づくりとデジタル機器との付き合い方
寝室環境をととのえるポイント
生活パターンと同じくらい、ぐっすり眠れるかどうかに影響するのが寝室の環境です。寝具の硬さや枕の高さ、部屋の明るさや温度、音の有無などが、少しずつ積み重なって睡眠の質に影響します。
まず見直したいのは、寝室の明るさです。ブライトな照明のまま布団に入るよりも、眠る30分〜1時間前から間接照明などで少し暗めの環境にすることで、体は「そろそろ夜だ」と感じやすくなります。カーテンから街灯の光が差し込む場合は、遮光性の高いカーテンを検討するのもひとつの方法です。
また、夏場はエアコンの設定温度が高すぎると寝苦しさにつながり、冬場は乾燥しすぎると喉の不快感で目が覚めやすくなります。快適と感じる温度や湿度は人それぞれですが、「寝ている間に暑さ・寒さ・乾燥で目が覚めないか」をひとつの基準に、少しずつ調整してみてください。
スマホ・PC・テレビとの距離感を決める
ぐっすり眠れない人の生活パターンの中で、最も大きな存在になりやすいのがスマホやPC、テレビなどのデジタル機器です。ベッドに入ってから延々とSNSや動画を見てしまうと、時間が過ぎるだけでなく、画面の光によって脳が「まだ活動時間だ」と勘違いし、眠りのスイッチが入りにくくなります。
一気にゼロにするのが難しい場合は、「〇時になったらスマホは充電器に置いて、ベッドには持ち込まない」といった、ルールを一つだけ決めるところから始めてみましょう。ベッドの近くにスマホを置かず、目覚まし時計を別に用意するだけでも、夜のダラダラ閲覧を減らしやすくなります。
動画やSNSの代わりに、紙の本や雑誌を読む、静かな音楽を流す、日記やメモで一日を振り返るなど、心が落ち着く行動を「寝る前の定番」として用意しておくと、自然と眠りにつながるパターンを作りやすくなります。
カフェイン・アルコールとの付き合い方
コーヒーやお茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、眠気を和らげる働きがあります。午前中の眠気覚ましとしては有効なことも多いですが、夕方以降に何杯も飲む習慣があると、夜になってもカフェインの効果が残り、眠りにつきにくくなる場合があります。
カフェインの影響がどれくらい続くかは個人差がありますが、「夕方〇時以降はカフェイン入りの飲み物を控える」といったマイルールを設けると、自分の生活パターンに合ったバランスを見つけやすくなります。どうしても温かい飲み物が欲しい時は、カフェインレスのコーヒーやハーブティー、白湯なども試してみてください。
また、アルコールは一見「寝つきをよくする」ように感じられることがありますが、実際には睡眠の後半を浅くしてしまうことが多いとされています。眠る直前まで飲酒を続けるのではなく、「眠りたい時間の数時間前までに切り上げる」「量を控えめにする」など、少しずつ付き合い方を調整していくことが、ぐっすり眠れる生活パターンにつながっていきます。
タイプ別・ぐっすり眠れない人の生活パターンと対策
ぐっすり眠れないと言っても、その背景にある生活パターンは人によってさまざまです。ここでは、よく見られるいくつかのタイプに分けて、それぞれの特徴と対策の方向性を整理してみます。
仕事が忙しくて寝る時間がバラバラなタイプ
残業やシフト勤務などで毎日の帰宅時間が一定しない人は、「寝る時間」をそろえるのが難しく、結果的に就寝時刻がバラバラになりやすい傾向があります。このタイプの人は、「何時に寝るか」よりも先に、「何時に起きるか」をある程度固定する意識が大切です。
例えば、どうしても帰宅が遅くなる日は、睡眠時間を削らざるを得ないこともありますが、それでも起床時間を大きく動かさないことで、体内時計を大きく崩さずに済みます。日によって睡眠時間が短くなってしまった場合は、翌日に早く寝ようとするよりも、数日かけて少しずつリズムを戻すイメージの方が、無理なく続けやすくなります。
帰宅後ダラダラスマホで夜更かしするタイプ
「あと5分だけ」と思いながら、気づけば1時間以上スマホを触っている。このタイプの人は、強い意志で我慢しようとするよりも、「ダラダラを誘発するきっかけを減らす」環境づくりが有効なことが多いです。
例えば、帰宅したらすぐに充電器のある場所にスマホを置き、リビングではなく玄関近くなどベッドから離れた位置で充電するようにします。通知をオフにする、特定のアプリは夜間に使えない設定にするなど、「スマホに触るまでの一手間」を増やすことで、なんとなく触ってしまう回数を減らせます。
代わりに、夜の時間を埋めてくれる「ゆるい楽しみ」を用意することも大切です。録画した番組を決まった時間だけ見る、紙の本を読む、日記を書く、軽いストレッチをするなど、スマホ以外の夜の定番を育てると、少しずつ生活パターンが変わっていきます。
「眠らなきゃ」と意識しすぎて緊張してしまうタイプ
布団に入ると、「今日こそは眠らなきゃ」「また眠れなかったらどうしよう」と考えてしまい、かえって目が冴えてしまうタイプの人もいます。この場合、生活パターンというよりも、眠りに対する考え方や気持ちの持ち方が影響していることが少なくありません。
このタイプの人にとっては、「布団に入ったら絶対に眠らなければならない」という考えから少し距離を置き、「布団は休む場所。眠れなくても横になっているだけで体は回復に向かっている」と柔らかく捉え直すことが大切です。眠れない時間が続いてつらい場合は、一度布団から出て、暗めの明かりの下で静かな読書や深呼吸をし、眠気が戻ってから布団に入る方法もあります。
ここで、タイプ別に「よくある生活パターン」と「意識したい対策の方向性」を表にまとめます。
【タイプ別・生活パターンと対策の方向性】
| タイプ | よくある生活パターン | 意識したい対策のポイント |
|---|---|---|
| 忙しくて寝る時間がバラバラ | 日によって就寝時間が大きく違う。休日は昼まで寝ていることも多い。 | まずは起床時間をそろえることを優先。平日と休日の差を1〜2時間以内にし、朝の光をしっかり浴びる。 |
| スマホ夜更かし | 帰宅後すぐスマホを触り始め、そのまま布団の中でもSNSや動画を見続けてしまう。 | スマホの置き場所や使用時間を決め、夜は紙の本やストレッチなど別の習慣で時間を埋める。 |
| 眠りを意識しすぎて緊張 | 布団に入ると「今日も眠れないかも」と不安が高まり、余計に目が冴える。 | 眠れない自分を責めない姿勢を意識し、「横になって休むだけでもよい」と考え方を柔らかくする。 |
自分がどのタイプに近いかをイメージしながら、「対策ポイント」の中からできそうなことを一つ選んで試してみてください。タイプを決めつけることが目的ではなく、自分の生活パターンを客観的に眺めるきっかけとして活用するのがおすすめです。
専門機関への相談を検討したい目安
ここまでお伝えしてきた内容は、あくまで生活パターンを整えるための一般的な情報です。ぐっすり眠れない状態が長く続いていたり、日常生活に支障が出ていたりする場合には、自己判断だけで対応しようとせず、専門機関への相談も検討することが大切です。
受診を考えたい具体的なサイン
次のような状態が続いている場合は、生活習慣の見直しと並行して、医療機関などに相談する目安と考えられます。
数週間〜数か月にわたってほとんどぐっすり眠れず、日中の強い眠気やだるさで仕事・家事・学業に大きな影響が出ている。夜なかなか寝つけないだけでなく、早朝に目が覚めてそのまま眠れない日が続き、気分の落ち込みや意欲の低下が強くなっている。寝ている間に大きないびきや息が止まるような様子を家族から指摘される。心配事や不安で頭がいっぱいになり、布団に入ると動悸や息苦しさを感じることが多い。
これらのサインがあるからといって、必ずしも重い病気というわけではありませんが、自分だけで抱え込まずに専門家に相談することで、安心材料や具体的な対処法が得られる可能性があります。
どこに相談すればよいか
ぐっすり眠れない状態について相談できる場所はいくつかあります。まずは、かかりつけの内科や地域のクリニックなど、普段から利用している医療機関で相談してみる方法があります。症状の内容によっては、睡眠に関する専門外来、心療内科、精神科などへの受診を勧められることもあります。
仕事のストレスや働き方との関係が大きいと感じる場合は、職場に産業医や保健師がいる場合、相談窓口として活用できることもあります。学校に通っている場合は、養護教諭やスクールカウンセラーなどに話してみるのも一つの方法です。
どこに相談すべきか迷う場合は、地域の保健センターや自治体の相談窓口で、「眠れない」「生活リズムが乱れてつらい」と伝えると、適切な窓口を案内してもらえることがあります。
相談するときに整理しておきたいこと
専門機関に相談する際は、次のような点をメモにまとめておくと、自分の状態を相手に伝えやすくなります。
眠れない・ぐっすり眠れないと感じ始めた時期と、その前後にあった出来事(仕事の変化、家庭の変化など)。平日・休日それぞれの就寝時間・起床時間のおおまかなパターン。夜中に何度くらい目が覚めるか、朝の目覚めはどうか。日中の強い眠気、集中力の低下、気分の変化など、生活への影響。思い当たるストレス要因や、逆に支えになっていること。
すべてを完璧に書き出す必要はありませんが、「最近の生活パターン」と「つらいと感じていること」を簡単に整理しておくだけでも、相談の時間を有効に使いやすくなります。
よくある質問(Q&A)
Q1. ぐっすり眠れない生活パターンを変えるには、どれくらいの期間が必要ですか?
A. 個人差がありますが、起床時間や寝る前の習慣などを少しずつ整えていくと、数日〜数週間で「なんとなく前よりマシかもしれない」と感じ始める人もいます。体内時計のリズムを安定させるには、まずは2週間〜1か月程度、できる範囲で新しいパターンを続けてみることがひとつの目安になります。
Q2. 平日は睡眠時間が短くなってしまいます。休日に寝だめをするのはやめた方がよいでしょうか?
A. 慢性的な寝不足を補うために、休日に少し長めに眠ること自体が必ずしも悪いとは言えません。ただし、平日との起床時間の差が大きくなるほど体内時計が乱れやすく、日曜の夜に眠れない原因になりがちです。休日の起床時間は、平日から1〜2時間以内の差に収めることを目標にし、その上で昼間の軽い昼寝やリラックス時間で疲れをとる方法も検討してみてください。
Q3. 寝る前にどうしてもスマホを触ってしまいます。完全にやめなければいけませんか?
A. いきなり完全にやめようとすると、かえってストレスになる場合があります。まずは、「眠りたい時間の1時間前になったら、ベッドの中ではスマホを触らない」など、具体的なルールを一つだけ決めてみてください。寝る前のスマホ時間を少しずつ短くしていくことで、現実的な範囲で睡眠への影響を減らしていくことができます。
Q4. 夜中に目が覚めることが多く、そこから眠れません。どうしたらいいですか?
A. 夜中に一度目が覚めること自体は、誰にでも起こりうる現象です。ただ、そこから長時間眠れずに焦りが強くなると、ますます眠りにくくなってしまいます。そんなときは、「眠れない自分を責めない」ことと、「一度布団から出て暗めの明かりのもとで静かに過ごし、眠気が戻ったらまた布団に入る」方法を試してみるのも一案です。頻度が多い場合や日中の不調が強い場合は、専門機関への相談も検討してください。
Q5. 運動不足がぐっすり眠れない原因になりますか?
A. 運動不足が直接の原因とまでは言い切れませんが、体をほとんど動かさない日が続くと、夜になっても「体がほどよく疲れていない」状態になり、眠りにつきにくいと感じる人もいます。激しい運動でなくても、日中に少し歩く距離を増やす、階段を使う、軽いストレッチをするなど、無理のない範囲で体を動かす習慣を取り入れることで、睡眠の質が変化する人もいます。
用語解説
体内時計
体の中にある「時間を感じる仕組み」のことです。朝の光や活動量、食事のリズムなどの影響を受けながら、一日の眠気と覚醒のリズムをつくっています。
睡眠の質
単に「何時間寝たか」という量だけでなく、寝つきの良さ、夜中に起きる回数、朝の目覚めの感覚などを含めた、睡眠全体の状態を指します。
社会的時差ボケ
平日と休日で睡眠時間帯が大きくずれることで、体内時計が時差ボケのような状態になることを指す言葉です。月曜の朝のだるさなどにつながりやすくなります。
カフェイン
コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれる成分で、眠気を和らげたり集中力を高めたりする働きがあります。夕方以降に多くとると、夜の睡眠に影響することがあります。
睡眠衛生
ぐっすり眠るために、生活習慣や寝室環境を整える考え方のことです。生活パターンや環境を見直すことで、睡眠の質を高めようとする取り組み全般を指します。
まとめ:ぐっすり眠れない生活パターンは「少しずつ組み替えれば」必ず変えられる
ぐっすり眠れないと、「自分の体質のせい」「メンタルが弱いせい」と自分を責めてしまいがちです。しかし、多くの場合、「眠りにくい生活パターン」がいつの間にか出来上がっているだけということも少なくありません。
この記事では、ぐっすり眠れない人の生活パターンに共通するサインや、朝・日中・夜それぞれの時間帯で見直したいポイント、タイプ別の対策、専門機関への相談の目安まで、できるだけ具体的にお伝えしました。
すべてを一度に完璧にこなす必要はありません。むしろ、「これならできるかも」と感じることを一つだけ選び、まずは2週間続けてみるくらいの気持ちがちょうどよいペースです。例えば、「毎朝同じ時間に起きてカーテンを開ける」「寝る前1時間はスマホをベッドに持ち込まない」といった、シンプルなルールから始めても構いません。
もし生活パターンを整えてもつらさが続く場合や、日常生活に支障が出ていると感じる場合は、一人で抱え込まずに、医療機関や相談窓口に頼ることも大切な選択肢です。あなたの眠りを支えてくれる専門家やサービスは必ず存在します。
ぐっすり眠れる生活パターンは、一日で完成するものではありませんが、小さな一歩を積み重ねることで、少しずつ確かな変化が生まれていきます。今日できそうなことを一つだけ選び、自分のペースで取り組んでみてください。それが、明日のあなたの眠りをやさしく支える第一歩になります。
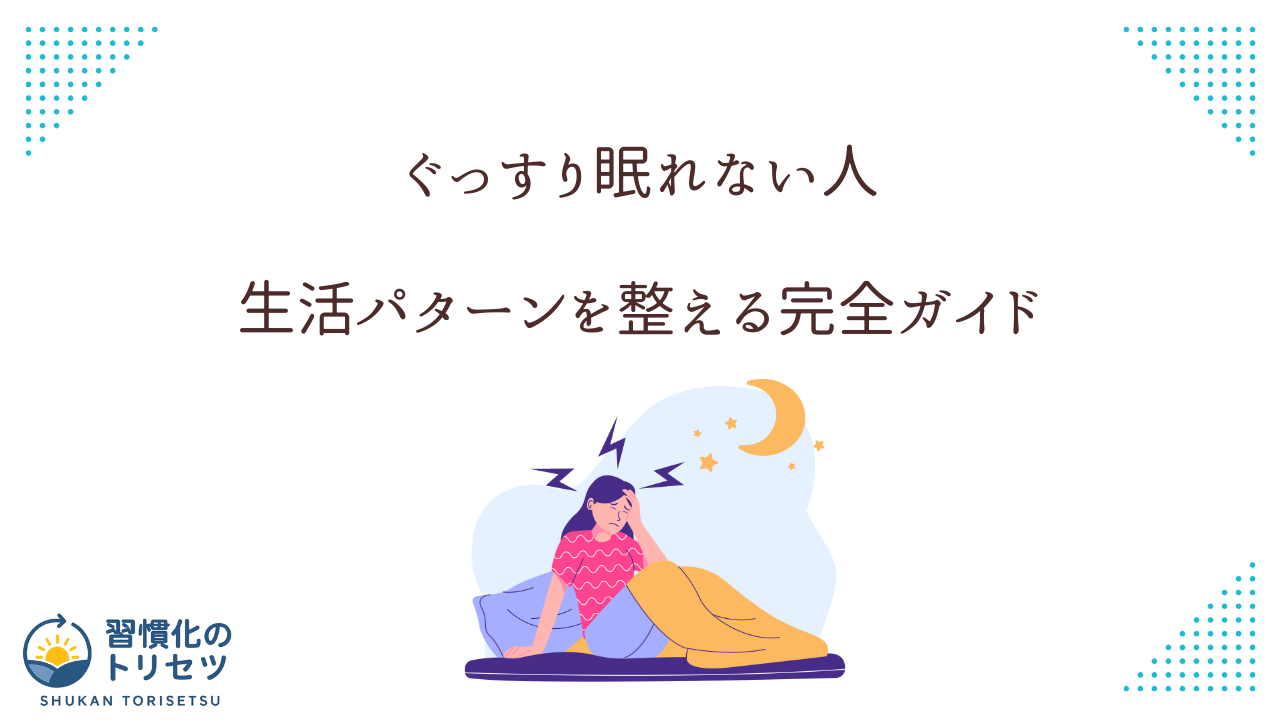
コメント