仕事や家事を終えて「さあ寝よう」と布団に入っても、なかなか寝つけずにスマホを見続けてしまう。眠れない不安から「寝る前に何か温かい飲み物でも飲めばいいのかな」と考えたことがある方は多いのではないでしょうか。
寝る前に飲むものは、意外なほど睡眠の質に影響します。ちょっとした飲み物の選び方やタイミングの違いで、「ぽかぽかして自然にまぶたが重くなる夜」にもなれば、「トイレに何度も起きてしまう夜」「頭がさえて眠れない夜」にもなり得ます。
この記事では、寝る前に飲むと良い飲み物が知りたい方に向けて、「睡眠と飲み物の関係」「実際におすすめしやすいドリンク」「避けたい飲み物とその理由」「体質別の選び方」「専門機関に相談した方がよい目安」までを、できるだけやさしい言葉で、しかし浅くなりすぎないように丁寧に解説します。
最初に、この記事のポイントを三つにまとめます。
第一に、寝る前に飲むと良い飲み物は、体温や自律神経をゆるやかに整え、眠りに入りやすい状態をつくる「サポート役」であり、魔法のような即効薬ではないということです。
第二に、「何を飲むか」だけでなく、「どのくらいの量を、いつ飲むか」がとても重要で、少しの飲みすぎやタイミングのずれが、夜中のトイレや胃もたれにつながるという点です。
第三に、寝る前に飲むと良い飲み物は、生活リズムや寝室環境、スマホとの付き合い方などと組み合わせることで、数週間単位でじわじわ効果を感じやすくなるということです。
ここでお伝えする内容は、医療行為や診断・治療を目的としたものではなく、あくまで日常生活の中でできる一般的なセルフケアの一つとしての情報です。強い不眠や体調不良が続く場合は、自己判断に頼らず、必ず医師や専門機関に相談するようにしてください。
この記事は、睡眠や生活習慣、栄養に関する取材・執筆経験を持つライターが、公的機関の資料や専門家による一般的な解説を参考にしながら、非医療の範囲でわかりやすく整理したものです。医学的な診断や治療を行うものではなく、具体的な症状や持病がある方、妊娠中・授乳中の方、薬を服用している方は、自己判断に頼らず必ず医師や専門家に相談することをおすすめします。
それでは、まずは「なぜ寝る前の一杯が睡眠に影響するのか」という原因から見ていきましょう。
寝る前に飲むと良い飲み物が睡眠に影響する原因を知る
寝る前の飲み物が睡眠に関係する理由を理解しておくと、「なんとなく身体によさそうだから」ではなく、納得感を持って選べるようになります。
体温のリズムと寝る前の温かい飲み物
人の体は、眠りに入る前に、深部体温と呼ばれる身体の内部の温度が少しずつ下がることで、自然な眠気を感じやすくなります。これは、からだが「活動モード」から「休息モード」に切り替わるサインのようなものです。
寝る前に適度に温かい飲み物を飲むと、一時的に体の表面付近が温まり、その後、手足などから熱が放出されていきます。その過程で深部体温が緩やかに下がり、「ふわっと眠気が訪れる」きっかけになると考えられています。入浴後にぽかぽかしたあと眠くなる感覚に少し似ています。
ただし、熱すぎる飲み物を大量に飲むと、胃腸に負担がかかったり、かえって汗ばみすぎて不快になったりすることもあります。「少しぬるめ〜ほどよく温かい」くらいが目安と考えるとよいでしょう。
自律神経とリラックス感を高める飲み物
私たちのからだの状態を自動的に調整しているのが、自律神経です。日中に優位な交感神経はアクセル、夜に優位になってほしい副交感神経はブレーキの役割を持つ、とイメージするとわかりやすいかもしれません。
寝る前に、温かい飲み物をゆっくりと味わいながら飲む時間をつくることは、「今日の活動を終える合図」として、副交感神経を優位にしやすくすると考えられています。特に、カフェインを含まないハーブティーやホットミルクなどは、「安心感」や「ホッとする感覚」を得やすい人も多く、心の緊張をゆるめるサポートになります。
逆に、カフェインやアルコールは、一時的にリラックスしたように感じても、夜間の睡眠を浅くしたり、途中で目が覚めやすくしたりする要因になることがあります。飲み物選びの段階で、ある程度「自律神経に優しいドリンクかどうか」を意識しておくと、寝つきの改善につながりやすくなります。
水分バランスと夜中の目覚め
一日の終わりに水分をとることは大切ですが、寝る直前に大量の水分をとると、夜中にトイレへ行きたくなって目が覚めてしまうことがあります。特に、冷たい飲み物や利尿作用が強い飲み物(カフェインを含むお茶類など)は、夜間の中途覚醒につながりやすくなります。
そのため、寝る前に飲むと良い飲み物であっても、量はマグカップ一杯程度、時間は就寝の三十分〜一時間前までにとどめておくのが、目安として現実的です。寝る直前は、口をうるおす程度の少量にとどめると、夜中のトイレで何度も起きるリスクを減らしやすくなります。
寝る前に飲むと良い飲み物の種類と選び方の方法
ここからは、実際に「寝る前に飲むと良い」とされる飲み物の種類と、その選び方の方法を整理していきます。ここで紹介するのは一般論であり、合うかどうかは体質や好みによって変わるため、「試してみて心地よいかどうか」を必ずご自身の感覚で確かめてください。
白湯・常温水でからだをやさしく温める
一番取り入れやすいのが、白湯や常温水です。白湯とは、水を一度沸騰させてから、飲めるくらいまで冷ましたものを指します。カフェインや糖分を含まず、胃腸への負担も比較的少ないため、寝る前の一杯として始めやすい飲み物です。
白湯を飲むときのポイントは、「熱すぎない」「ごくごく飲まず、ゆっくり味わう」「一気に大量に飲まない」という三つです。目安としては、二百ミリリットル前後を、十分ほどかけてゆっくり飲むイメージです。常温水の場合も同様に、「冷たすぎない」ことを意識すると、からだがリラックスモードに入りやすくなります。
ホットミルクと乳製品を取り入れるときの考え方
寝る前の飲み物としてよく挙げられるのがホットミルクです。温かいミルクには、「安心する」「子どもの頃を思い出してホッとする」といった心理的な効果を感じる人も多く、寝る前のリラックスタイムに向いていると言えます。
一方で、牛乳や乳製品は、人によってはお腹がゆるくなったり、重たく感じたりすることもあります。また、甘味を加えすぎると、血糖値の変動が大きくなり、かえって眠りが浅くなる人もいます。そのため、ホットミルクを試す場合は、少なめの量から始める、砂糖や甘味料は控えめにする、豆乳など他の選択肢も検討する、といった工夫が大切です。
ハーブティー・ノンカフェイン飲料の上手な選び方
カフェインを含まないハーブティーは、寝る前に飲むと良い飲み物として選ばれる代表格です。たとえば、カモミールティーは、りんごのようなやさしい香りで、気持ちを落ち着かせたい夜に向いているとされます。ルイボスティーや麦茶(カフェインゼロのもの)なども、ノンカフェインで寝る前に飲みやすい飲み物です。
選ぶ際のポイントは、「ノンカフェイン」または「カフェインゼロ」と明記されているかを確認することです。同じお茶でも、緑茶やウーロン茶、ほうじ茶、ジャスミン茶などはカフェインを含むことが多く、寝る前には控えた方が安心な場合があります。
ここで、寝る前に飲むと良いと言われやすい飲み物と、その特徴・目安量を表にまとめます。この表は、「まず何から試してみようか」を決めるときの地図のようなものとして活用してください。
| 飲み物の種類 | 特徴 | 目安量・タイミング |
|---|---|---|
| 白湯・常温水 | カフェインや糖分がなく、胃腸への負担が比較的少ない。どんな人でも試しやすい | マグカップ一杯(二百ミリリットル前後)を、就寝三十分〜一時間前までにゆっくり飲む |
| ホットミルク・ホット豆乳 | 温かさとやさしい甘みで安心感を得やすい。人によってはお腹が緩くなることも | カップ半分〜一杯程度から試す。砂糖は控えめにし、就寝一時間前までに飲み終える |
| カモミールティー | りんごのような香りでリラックスしやすい人が多い。ノンカフェイン | ティーカップ一杯を、読書やストレッチをしながらゆっくり飲む。寝る三十分前までが目安 |
| ルイボスティー・麦茶(カフェインゼロ) | ノンカフェインで日中から夜まで飲みやすい。クセが少なく続けやすい | 夕食時から少しずつ飲み、寝る前は多くても一杯程度にとどめる |
| 白湯+レモン一切れ(レモン白湯) | すっきりした味わいで「飲んだ満足感」を得やすい。胃が敏感な人は様子を見ながら | 少量からスタートし、刺激を感じたら無理に続けない。就寝一時間前までを目安に飲む |
就寝前のドリンク習慣を整える具体的な方法
どんなに「寝る前に飲むと良い飲み物」を知っていても、毎晩バラバラのタイミングで飲んでいたり、量が極端に変わったりすると、からだがリズムをつかみにくくなります。この章では、飲み物を使った就寝前の習慣づくりの方法を具体的に紹介します。
就寝九十分前からのドリンクスケジュール
一つの目安として、就寝予定時刻の九十分前から、「今日の終わりのルーティン」を始めてみる方法があります。たとえば、二十三時に寝たい場合は、二十一時三十分ごろから、仕事や家事をゆるやかに切り上げ、照明を少し落とし、スマホからも少し距離を置き始めます。
その後、二十二時ごろにお風呂から上がり、二十二時十五分〜三十分ごろに白湯やハーブティーなど、寝る前に飲むと良い飲み物をゆっくりと味わいます。この流れを繰り返すことで、からだが「この時間帯は休む準備をする」と覚えやすくなり、寝つきが徐々に整っていきやすくなります。
マグカップ一杯の「おやすみルーティン」を決める
毎晩違うことをしようとすると、どうしても続けるのが難しくなります。そこで、「寝る前のマグカップ一杯」を一つの合図にするのもおすすめです。お気に入りのマグカップを一つ決め、白湯やノンカフェインティーを入れ、その一杯を飲み終えたらスマホを手放し、布団に向かう、という流れを習慣にしてしまいます。
このとき大切なのは、飲みながら「今日の振り返り」や「反省会」をしすぎないことです。考え事が増えると、交感神経が高まりやすくなり、せっかくの飲み物のリラックス効果が薄れてしまいます。できれば、心地よい音楽を流したり、ぼんやりと湯気を眺めたりしながら、「何もしない時間」を味わうようにしてみてください。
季節別の飲み物の工夫
季節によって、寝る前に飲むと良い飲み物の選び方も少し変わります。夏場は冷たい飲み物を飲みたくなりますが、キンキンに冷えたドリンクを一気に飲むと、胃腸がびっくりしてしまい、かえって寝つきが悪くなることがあります。冷房で冷えやすい人は、夏でも常温か少し温かい飲み物を選ぶ方が、からだには優しい場合が多いです。
冬場は、ホットミルクやホット豆乳、白湯などで身体を温めたくなりますが、寝る直前に大量に飲むと、夜中のトイレが増えたり、布団の中で暑くなりすぎたりすることがあります。特に冷え性の方は、「量よりもタイミング」を意識して、就寝一時間前までに飲み終えるようにすると、ほどよく温まりつつも寝つきやすい状態を保ちやすくなります。
寝る前に避けたい飲み物とその対策
寝る前に飲むと良い飲み物がある一方で、「寝る前は控えた方がよい」とされる飲み物もあります。この章では、代表的なものと、その理由、そして代わりにとれる対策を整理します。
カフェイン飲料の影響と対策
コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、眠気を抑え、頭をシャキッとさせる働きがあることで知られています。日中には便利な一面もありますが、寝る前に飲むと、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になりやすくなります。
カフェインの影響がどのくらい続くかは個人差がありますが、一般的には、摂取から数時間は体内にとどまると考えられています。寝つきが悪いと感じている人は、まずは夕方以降のカフェイン飲料を減らし、できれば就寝六時間前くらいから控えることを目標にするとよいでしょう。
アルコール・糖分の多い飲み物
「寝酒をすると眠りやすい」と感じる人もいますが、アルコールは寝つきを早くする一方で、夜半から明け方にかけて眠りを浅くし、途中で目が覚めやすくすることがあると言われています。また、利尿作用もあるため、夜中のトイレが増えやすくなります。
甘いジュースや砂糖を多く含むドリンクも、血糖値の急上昇と急降下を招きやすく、その変動が眠りの浅さにつながる場合があります。寝る前に甘い飲み物を習慣的に飲んでいると、虫歯や体重増加のリスクも高まるため、できる範囲で見直したいポイントです。
「健康飲料」でも量とタイミングに注意
ヨーグルト飲料や栄養ドリンク、スポーツドリンクなど、一見健康によさそうに見える飲み物でも、糖分やカフェインを含んでいるものがあります。また、「疲労回復」「目覚めスッキリ」などと書かれている飲料は、そもそも日中の活動をサポートする目的で作られていることが多く、寝る前には向かない場合があります。
ここで、寝る前には避けたい飲み物と、その理由、代わりに選びたい飲み物を整理した表を紹介します。この表は、自分の夜の飲み物をチェックするときの参考として活用してみてください。
| 寝る前に避けたい飲み物 | 睡眠に良くない主な理由 | 代わりにおすすめの飲み物 |
|---|---|---|
| コーヒー・紅茶・緑茶などカフェイン飲料 | 覚醒作用で寝つきを悪くしたり、眠りを浅くしたりする可能性がある | ノンカフェインのハーブティー、白湯、カフェインレスコーヒーなど |
| アルコール飲料(ビール・ワイン・チューハイなど) | 寝つきを早める一方で中途覚醒を増やし、睡眠の質を下げることがある。利尿作用も強い | 夕食時の量を少なめにし、寝る前は白湯や麦茶などアルコールゼロの飲み物に切り替える |
| 甘いジュース・加糖乳飲料 | 血糖値の急な変動やカロリー過多につながり、体重や健康への影響も気になる | 甘さ控えめのホットミルクやホット豆乳、無糖のハーブティーに置き換える |
| エナジードリンク・栄養ドリンク | カフェインや糖分が多く、身体を「活動モード」に切り替える方向に働きやすい | 寝る前は控え、必要なら日中の早い時間帯に少量だけ利用する |
体質別・ライフスタイル別に合う寝る前の飲み物の選び方
同じ「寝る前に飲むと良い飲み物」でも、体質や生活スタイルによって合う・合わないが変わります。この章では、よくあるタイプ別に、選び方の考え方を紹介します。
冷えやすい人に合う飲み物
手足が冷えやすい人は、寝る前にからだをほんのり温めることで、寝つきが楽になることがあります。白湯やホットミルク、ホット豆乳などは、冷えやすい体質の人にとって心強い味方です。ただし、熱すぎる温度や飲みすぎは避け、少しぬるめにして、ゆっくり飲むことが大切です。
また、ショウガを入れた飲み物なども人気ですが、刺激が強すぎると胃に負担がかかる人もいます。生姜入りのドリンクを試す場合は、ごく少量から始め、胃の不快感や胸やけがないかをよく観察しながら調整してください。
夜中にトイレで起きやすい人の飲み方
夜中にトイレで何度も起きてしまう人は、「何を飲むか」以上に「いつ、どのくらい飲むか」が重要です。寝る直前まで水分を取り続けていると、どうしても夜間尿が増えやすくなります。
対策としては、日中〜夕方にかけてこまめに水分補給をしておき、寝る前はマグカップ半分〜一杯程度にとどめるようにする方法があります。また、利尿作用のあるカフェイン飲料やアルコールは、特に夕方以降の量を減らすことで、夜中のトイレ回数が落ち着いてくる場合があります。
ダイエット中・胃が弱い人の注意点
ダイエット中の人は、「寝る前の飲み物のカロリー」と「糖分の量」に注意が必要です。甘いココアや加糖の乳飲料を毎晩飲んでいると、知らないうちにカロリーが積み重なり、体重管理が難しくなることがあります。できる限り、無糖の飲み物や、自然な甘みの範囲にとどめる工夫が大切です。
胃が弱い人は、乳製品や酸味の強い飲み物、刺激のあるスパイス入りのドリンクなどで、胃もたれや胸やけを起こしやすいことがあります。その場合は、白湯や薄めのハーブティーのような、シンプルで刺激が少ない飲み物から始め、自分の胃の反応を見ながら少しずつレパートリーを広げていくと安心です。
専門機関への相談を検討したい目安と対処方法
ここまでご紹介した内容は、あくまで生活習慣や環境を整えるための一般的な情報です。寝る前に飲むと良い飲み物や就寝前の工夫だけでは対応が難しいケースも存在します。この章では、医療機関や専門家への相談を検討した方が良い目安について整理します。
寝つきの悪さや中途覚醒が長期間続く場合
寝る前の飲み物や生活リズムを見直しても、「布団に入ってから一時間以上眠れない状態がほぼ毎日のように続く」「夜中に何度も目が覚めて、そのまま長時間眠れない」といった状態が、数週間から数か月以上続く場合は、一度医療機関に相談することをおすすめします。
睡眠の問題は、ストレスや生活習慣だけでなく、体の病気や心の不調が背景にある場合もあります。専門家に相談することで、自分では気づきにくい要因や、適切な対処法が見つかることがあります。
日中の眠気や集中力低下が強い場合
夜眠れないことによって、日中の眠気が非常に強く、仕事や家事、運転、勉強などに支障が出ている場合も、セルフケアだけに頼らず専門機関への相談を検討したいサインです。特に、運転中や重要な会議中に眠気で意識が落ちそうになるような場合は、安全面から見ても早めの相談が大切です。
また、「気分の落ち込みが続く」「何をしても楽しいと感じられない」「不安感が強くて眠るのがこわい」といったメンタル面のサインがある場合は、心療内科や精神科など、心の専門家に相談することも視野に入れてください。
受診時に伝えておきたい情報
受診するときには、「寝る前に飲む飲み物」も含めて、普段の生活についてわかる範囲で整理しておくと、医師が状況を把握しやすくなります。具体的には、就寝・起床の時刻、寝つきにかかる時間、夜中に目が覚める回数、一日に飲むカフェイン飲料やアルコールの量、寝る前のドリンクや食事の内容などです。
完璧な記録である必要はありませんが、二〜三日分でもメモしておくと、「どのあたりを見直せばいいか」を一緒に考えやすくなります。医師から提案された対処法や治療方針についても、不安や疑問があれば遠慮なく質問し、納得したうえで進めることが大切です。
寝る前に飲むと良い飲み物に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、寝る前に飲むと良い飲み物について、よくある疑問にお答えします。気になる部分だけ拾い読みしていただいても構いません。
Q1. 寝る前のホットミルクは本当に寝つきを良くしますか?
A. ホットミルクを飲むと、温かさや甘みから「安心する」「ほっとする」と感じる人が多く、その心理的なリラックスが寝つきを後押しすることは考えられます。ただし、ホットミルクそのものに強い睡眠薬のような作用があるわけではなく、人によってはお腹が重く感じたり、乳糖不耐症でお腹がゆるくなったりすることもあります。まずは少量から試し、自分のからだに合うかどうかを確認することが大切です。
Q2. ノンカフェインコーヒーやデカフェなら、寝る前に飲んでも大丈夫ですか?
A. カフェインを大幅に減らしたノンカフェインコーヒーやデカフェは、一般的なコーヒーよりも寝る前に飲みやすい選択肢と言えます。ただし、商品によっては完全にゼロではない場合や、コーヒーの香りそのものが「仕事モード」を思い出させて頭がさえるという人もいます。寝つきが気になる場合は、白湯やハーブティーなど、より刺激の少ない飲み物と組み合わせながら様子を見るとよいでしょう。
Q3. 水分不足がこわくて、寝る直前にたくさん水を飲んでしまいます。
A. 水分不足を防ぐことは大切ですが、寝る直前に大量の水を飲むと、夜中のトイレが増えやすくなり、結果として睡眠の質が下がることがあります。日中からこまめに水分をとり、寝る前はマグカップ半分〜一杯程度にとどめるなど、時間帯ごとのバランスを意識するとよいでしょう。特に心臓や腎臓に持病がある方は、水分のとり方について必ず主治医に相談してください。
Q4. ハーブティーなら、どれだけ飲んでも大丈夫ですか?
A. ノンカフェインのハーブティーは寝る前に飲みやすい飲み物ですが、量が多すぎると、やはり夜中のトイレが増える可能性があります。また、ハーブの種類によっては体質に合わない場合や、妊娠中・授乳中の方には注意が必要なものもあります。基本的には一〜二杯程度を目安にし、体調や生活リズムに合わせて調整することが大切です。
Q5. 寝る前の飲み物だけで、睡眠の質はどのくらい変わりますか?
A. 寝る前に飲むと良い飲み物は、睡眠の質を整えるための要素の一つにすぎません。照明、室温、寝具、スマホの使用時間、ストレスや運動習慣など、さまざまな要素が組み合わさって睡眠の質が決まります。飲み物だけで劇的に変化するケースは多くはありませんが、「寝る前の一杯」をきっかけに、他の生活習慣も少しずつ見直していくことで、全体としての睡眠の質がじわじわと良くなっていくことが期待できます。
用語解説
ここでは、本文中に出てきた用語を、あらためて簡単に確認しておきます。
自律神経とは、心臓の鼓動や呼吸、体温調節、消化などを自動的にコントロールしている神経の仕組みです。昼間に働きやすい交感神経と、夜や休息時に働きやすい副交感神経のバランスが重要とされています。
深部体温とは、体の表面ではなく、内臓などの身体内部の温度のことです。眠りに入る前には、この深部体温が少し下がることで、自然な眠気が訪れやすくなると考えられています。
ノンカフェイン飲料とは、カフェインを含まない飲み物の総称です。ハーブティーや一部の麦茶、カフェインレスコーヒーなどが含まれます。「カフェインレス」「デカフェ」などの表記もありますが、完全にゼロではない製品もあるため、気になる場合は表示をよく確認することが大切です。
中途覚醒とは、眠っている途中で何度も目が覚めてしまうことを指します。トイレに行きたくなる、物音で起きてしまう、夢見が悪いなど、原因はさまざまです。
寝つきとは、布団に入ってから実際に眠りに落ちるまでの時間やスムーズさのことです。同じ睡眠時間でも、寝つきが良いと睡眠全体の満足度が上がりやすくなります。
まとめ|全部を完璧にやらなくていい。まずは「寝る前の一杯」を一つ決めてみる
この記事では、寝る前に飲むと良い飲み物をテーマに、睡眠との関係、具体的なドリンクの種類や選び方、避けたい飲み物と対策、体質別の工夫、専門機関への相談の目安、そしてよくある質問までを幅広くお伝えしてきました。
あらためて大切なポイントを整理すると、第一に、寝る前の飲み物は、体温や自律神経を穏やかに整えることで、眠りに入りやすい状態をサポートする存在であって、単独で不眠を治す「特効薬」ではないということです。第二に、「何を飲むか」だけでなく、「どのくらい、いつ飲むか」という量とタイミングの工夫が、夜中のトイレや胃もたれを防ぎ、睡眠の質を守るうえでとても大切だという点です。第三に、飲み物の工夫は、照明や室温、スマホとの距離、日中の過ごし方など、他の要素と組み合わせることで、数週間単位でじわじわと効果を感じやすくなるということです。
そして何よりお伝えしたいのは、全部を完璧にやらなくていいということです。白湯もハーブティーもホットミルクも、すべてを一度に取り入れる必要はありません。むしろ、選択肢が多すぎると、「今日は何を飲もう」と悩むこと自体が新たなストレスになってしまうこともあります。
まずは、あなたが「これならやってみてもいいかも」と思える、寝る前に飲むと良い飲み物を一つだけ選んでみてください。たとえば、「今夜からは、就寝三十分前に白湯をマグカップ一杯だけ飲む」「一週間だけ、寝る前のスマホ時間を五分減らして、その分ハーブティーを飲む時間にあてる」といった、小さくて具体的な一歩で十分です。
その一歩が習慣になってきたら、少しずつ他の工夫も足していけば大丈夫です。昨日よりもほんの少し、眠りに入りやすくなった自分を認めながら、あなたのペースで「おやすみ前の一杯」と睡眠習慣を育てていってください。
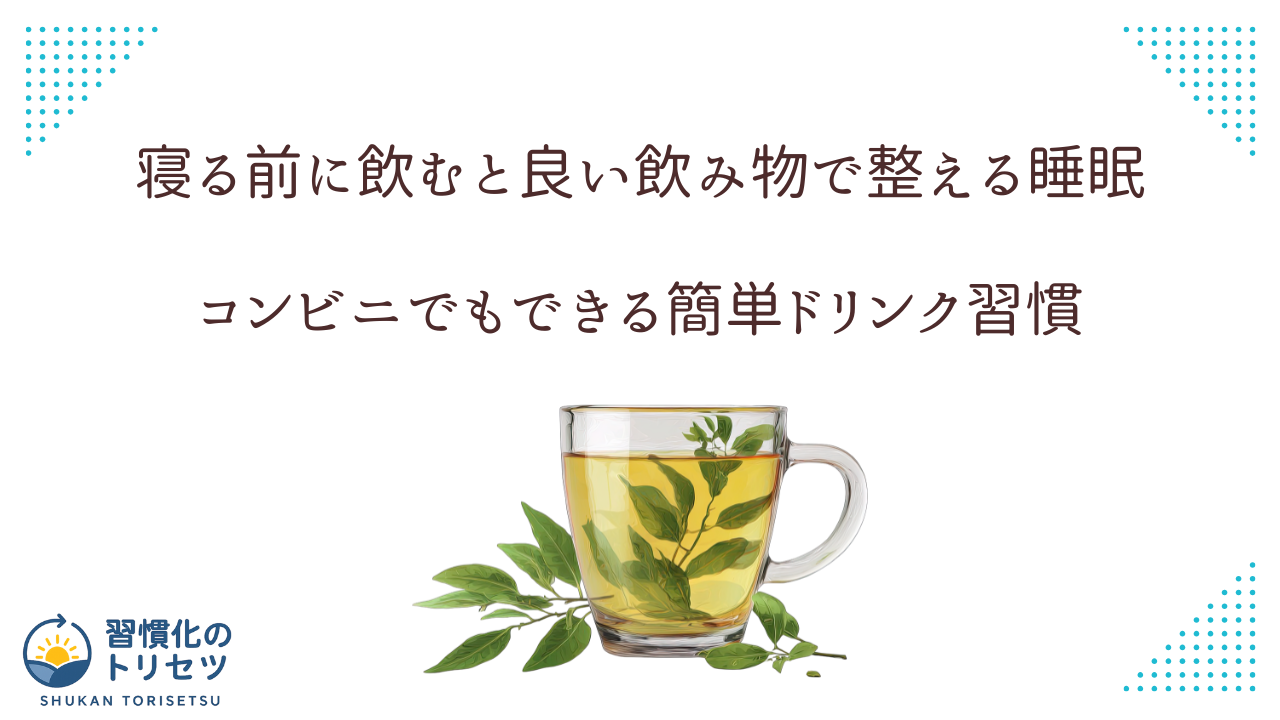
コメント