仕事や学校、家事や育児をなんとか終えて、ふと一息ついた夜。日中はそこまで気にならなかった悩みや不安が、急に大きく感じられて涙が出そうになる。気づけば「自分なんて」「あのときのあの言葉」が頭の中でぐるぐる回ってしまい、なかなか眠れない。そんな夜に気持ちが落ち込む経験をしている方は、とても多いと言われています。
明るい時間帯には前向きに考えられることも、夜になると急にネガティブに見えてしまうと、「自分はメンタルが弱いのでは」「このままおかしくなってしまうのでは」と不安になるかもしれません。けれど、体や脳、心のしくみを少し知ると、「夜に気持ちが落ち込むのには、一定の理由がある」と理解できることも少なくありません。
この記事では、夜に気持ちが落ち込む理由を、体のリズムやホルモン、思考のクセ、生活習慣などの面から整理しつつ、「今日からできる小さな対処法」や「専門機関への相談を検討したい目安」まで、できるだけやさしい言葉で解説します。
最初に、この記事全体の結論を3つにまとめます。
① 夜に気持ちが落ち込むのは、体内時計やホルモン、環境の変化など、心だけでなく体のリズムとも深く関係していること
② 全てを根性で乗り切る必要はなく、「考えすぎない工夫」「からだをゆるめる工夫」「夜向けの情報との付き合い方」を少しずつ整えることで、心の負担を軽くしやすくなること
③ 生活の工夫やセルフケアを続けてもつらさが強い場合は、一人で抱え込まず、医療機関や専門家に相談することがとても大切であること
この3つを軸に、「自分が悪いわけではない」と理解しながら、夜の時間を少しでも穏やかに過ごすためのヒントを一緒に見ていきましょう。
【注意書き・専門性について】
この記事は、メンタルヘルスや睡眠、生活習慣に関する取材・執筆経験を持つライターが、公的機関の情報や専門家への取材内容、信頼性の高い専門書などをもとに、一般的な知識としてまとめたものです。医師や心理専門職による診断・治療を代わりに行うものではなく、あくまでセルフケアと相談のきっかけづくりを目的とした情報提供です。症状が強い場合や長引く場合、自分や他者を傷つけたい気持ちが出ている場合は、必ず医療機関や専門家に相談するようにしてください。
夜に気持ちが落ち込む理由を理解する
体内時計とホルモンのリズムから見た理由
まず押さえておきたいのは、夜に気持ちが落ち込むことには、心だけでなく体のリズムも関わっているという点です。私たちの体には、24時間前後のリズムを刻む体内時計があります。この体内時計は、睡眠と覚醒、体温、ホルモン分泌、気分の波など、さまざまな機能に影響しています。
日中は、活動を支えるホルモンや神経の働きが高まり、外から入ってくる刺激も多いため、「動くモード」「対処するモード」でいられる時間帯です。一方、夜になると、眠りを促すメラトニンなどのホルモンが増え、体温や代謝も下がっていきます。これは本来、休息の準備として自然な変化ですが、同時に、集中力や判断力が落ちやすくなり、物事を客観的に見る力も弱まりやすくなります。
その結果、同じ出来事でも昼間より「重く」「暗く」感じてしまい、夜に気持ちが落ち込むことが起きやすくなります。自分の弱さではなく、「夜はそう感じやすい時間帯でもある」と知っておくだけでも、少し視点が変わることがあります。
昼と夜で「心のモード」が変わる
昼間は、仕事や家事、学校、育児など、目の前のタスクをこなすだけで精一杯のことも多いはずです。周りに人がいて話をしたり、情報がどんどん入ってきたりすることで、心の中に湧いてくる不安や寂しさに、あまり意識を向ける余裕がないことも少なくありません。
ところが、夜になり静かになると、日中「後回し」にしていた気持ちが、一気に前に出てくることがあります。誰とも話していない時間が長くなると、頭の中の声(内的な対話)が大きくなり、「あの発言はまずかったかもしれない」「自分は役に立っていないのでは」など、自己否定的な考えが目立ちやすくなります。
ここで、あくまでイメージとして、昼と夜の違いを簡単な表で整理してみます。
【昼と夜で変わりやすい心と環境の違い】
| 項目 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|
| 周囲の状況 | 人との会話や情報が多く、やることに追われやすい。 | 静かになり、一人の時間が増えやすい。 |
| 体と脳の状態 | 交感神経が働きやすく、集中・行動モード。 | 副交感神経が増え、ぼんやりしやすく、感情が出やすい。 |
| 気持ちの傾向 | 現実対応が優先され、感情は後回しになりがち。 | 感情や過去の出来事に意識が向きやすい。 |
この表はあくまで一般的な傾向ですが、「昼は動くモード」「夜は感じるモード」の色合いが強くなりやすい、と覚えておくと、夜に気持ちが落ち込むときに「今はそういう時間帯でもある」と距離を取るヒントになります。
静けさと暗さが不安や孤独感を増幅させる
夜は静かで落ち着くという人もいれば、静けさがかえって不安や孤独感を強める人もいます。特に、一人暮らしや単身赴任、子どもが寝たあとに一人になる時間が長い人は、周りに話し相手がいないことで、悩みや心配ごとを頭の中だけで繰り返し考えやすくなります。
また、暗さそのものが、過去のつらい記憶やさみしさを連想させてしまうこともあります。夜に気持ちが落ち込むとき、「自分は弱い」「考えすぎ」と責めてしまうのではなく、「静けさと暗さの中で、いろいろな感情が出てきやすいだけ」と受け止めてあげることが、最初の一歩になります。
生活習慣から見る夜に気持ちが落ち込む理由
睡眠不足とリズムの乱れが感情を不安定にする
夜に気持ちが落ち込む理由として、慢性的な睡眠不足や生活リズムの乱れは大きな要因になりえます。睡眠時間が足りない状態が続くと、脳の「感情を調整する力」が弱まり、小さな出来事にも過敏に反応しやすくなると考えられています。
また、平日は寝る時間が遅く、休日は昼過ぎまで寝ているといった生活パターンが続くと、体内時計が乱れ、夜になるほど「だるさ」や「虚しさ」を感じやすくなることがあります。夜に気持ちが落ち込むとき、「自分の性格の問題」と片づける前に、「最近、睡眠リズムはどうだったか」を振り返ってみることも大切です。
夜のスマホ・SNSとの付き合い方
現代では、夜の時間帯にスマホやSNS、動画配信サービスを利用するのはごく当たり前のことになりました。しかし、夜に気持ちが落ち込むタイミングで、他人のキラキラした投稿やニュース、刺激の強いコンテンツを長時間見続けると、自分を責める材料や不安材料を増やしてしまうことがあります。
例えば、仕事終わりで疲れているときに、SNSで同年代の人の成功話ばかり目にすると、「自分だけ取り残されている」と感じやすくなります。また、夜遅くに不安をあおるニュースに触れると、頭の中で最悪のシナリオを想像してしまい、「世界も未来も不安」という感覚が強まることがあります。
夜に気持ちが落ち込むときほど、スマホに答えを求めたくなりますが、「今の自分にはどんな情報が心地よいか」を意識的に選ぶことが大切です。
食事・カフェイン・アルコールの影響
夜の気持ちに影響するのは、光や情報だけではありません。食事やカフェイン、アルコールなど、口にするものも関係してきます。夜遅い時間に重たい食事をとると、胃腸が休めず、体が「消化モード」のままになり、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めてそこから気持ちが落ち込んだりすることがあります。
また、コーヒーやエナジードリンクなどに含まれるカフェインは、摂取から数時間、覚醒作用が続くことがあります。夕方以降もカフェインを多くとっていると、寝つきにくさや睡眠の浅さにつながり、その結果として夜に気持ちが落ち込みやすくなる場合があります。
アルコールも、一時的には不安や緊張を和らげたように感じられることがありますが、その後の睡眠の質を下げ、夜中の覚醒や翌朝のだるさにつながりやすいと言われています。「夜に気持ちが落ち込むから飲む」のではなく、「飲むことで翌日さらに落ち込みやすくなる可能性もある」と意識しておくことが大切です。
夜に気持ちが落ち込むときの具体的なセルフケア
思考のスイッチを切り替える「書き出し」の活用
夜に気持ちが落ち込むとき、頭の中だけで考え続けると、同じ考えがぐるぐる回りやすくなります。そんなときに役立つのが、紙に書き出すセルフケアです。寝る前の10分ほどを使って、「今、不安に思っていること」「怒りや悲しみとして残っていること」を、思いつくままにノートに書いてみます。
書くときのポイントは、「きれいにまとめる」「解決策を書く」ことを目指さないことです。頭の中にあるものを、そのまま外に出すイメージで、「こう思っているんだな」と自分の気持ちを見える形にしてあげるだけでも、感情の圧が少し下がることがあります。最後に、「続きは明日の昼間に考える」と一言書き足し、ノートを閉じて布団に向かう儀式にしても良いでしょう。
からだをゆるめる夜のルーティンを作る
夜に気持ちが落ち込むときは、心だけでなく体もこわばっていることが多いです。肩が上がっていたり、呼吸が浅くなっていたり、歯を食いしばっていたりするかもしれません。そこで、寝る前にからだをゆるめる小さなルーティンを取り入れることが役立ちます。
例えば、照明を少し落とし、深呼吸をしながら首や肩をゆっくり回す、背中を丸めて伸ばす、ふくらはぎを手で軽くさするなどです。動きはどんなものでもかまいませんが、「気持ちよさ」を感じることを大切にし、痛みを我慢するような無理なストレッチは避けます。数分でも、「今日一日の自分の体におつかれさま」と伝える時間を持つことで、「もう休んでいい」というサインを体に送ることができます。
夜向けの情報との距離の取り方を決めておく
夜に気持ちが落ち込むと分かっている人ほど、あらかじめ「夜用の情報との付き合い方ルール」を決めておくと、心の負担を減らしやすくなります。例えば、「寝る1時間前からはSNSを開かない」「夜は仕事のメールを見ない」「不安になるニュースは朝にだけチェックする」といった、ゆるやかなマイルールです。
最初から完璧に守る必要はありませんが、「夜は自分を責めやすい時間帯だから、なるべく自分を追い詰めない情報を選ぶ」と意識しておくだけでも、夜の気持ちの揺れ方が変わってくることがあります。
タイプ別に見る夜に気持ちが落ち込む理由と対策
不安が強く「最悪のシナリオ」を考えやすいタイプ
夜に気持ちが落ち込む人の中には、「もし〜だったらどうしよう」「あの失敗で全部ダメになるかもしれない」というように、まだ起きていない未来の不安を強く感じやすいタイプの方がいます。日中は予定や人付き合いで気を紛らわせていても、夜になると静けさの中で、不安が一気に押し寄せてくる感覚があるかもしれません。
このタイプの方には、「今できること」と「今はできないこと」を紙に分けて書き出し、「今はできないことの多くは、明日の自分や未来の自分が考えること」と意識して切り分ける方法が役立つことがあります。また、「最悪のシナリオ」を想像したあとは、「いちばん現実的なシナリオ」「うまくいくシナリオ」もあえて書いてみると、頭の中が少し広がりやすくなります。
自己否定が強く「自分責め」をしやすいタイプ
夜に気持ちが落ち込むとき、「あのときああ言わなければよかった」「自分なんてダメだ」「どうせ誰からも必要とされていない」といった、自分を責める言葉が浮かびやすい人もいます。このタイプの方は、失敗や他人からの反応を、自分の価値そのものと結びつけやすく、夜になるほど「今日の反省会」が厳しくなってしまうことがあります。
そんなときに試してほしいのが、「自分への声かけを、信頼できる友人がかけてくれる言葉に置き換えてみる」ことです。例えば、「今日もよく頑張ったね」「あの場面ではあれが精一杯だったよね」と、もし友人が同じ状況だったらどんな言葉をかけるだろう、と想像してみます。すぐに心から信じられなくても、「自分責めの声の他に、もう一つ別の声を足してみる」だけでも、心の重さがいくらか和らぐことがあります。
孤独感が強く「誰にも分かってもらえない」と感じやすいタイプ
夜に気持ちが落ち込むとき、「誰にも相談できない」「自分の気持ちを理解してくれる人はいない」と強く感じる方もいます。特に、転職や引っ越し、ライフイベントなどで環境が変わった直後は、周りとのつながりが薄くなったように感じやすく、孤独感が強まることがあります。
このタイプの方には、「完全な理解者を一人見つける」ことよりも、「安心して話せる相手や場所を、少しずつ増やしていく」ことを意識してみるのがおすすめです。友人や家族に一度に全てを話す必要はありません。ちょっとした近況を共有するメッセージを送る、オンラインの相談窓口やピアサポートの場を知っておくなど、「つながれる可能性のある窓口」を少しずつ増やしていくイメージを持ってみてください。
ここで、タイプ別に「夜に気持ちが落ち込む理由」と「試しやすい対策」の例を表に整理します。
【タイプ別・夜に気持ちが落ち込む理由と対策の例】
| タイプ | 夜に気持ちが落ち込む理由の傾向 | 試しやすい対策の例 |
|---|---|---|
| 不安が強いタイプ | 未来の最悪のシナリオを何度も想像してしまう。 | 「今できること」と「今はできないこと」を紙で仕分けし、考えるタイミングを翌日昼に移す。 |
| 自己否定が強いタイプ | 一日の失敗や他人の反応を思い出し、自分を責めてしまう。 | 友人視点の声かけを書いてみる。「今日うまくいった小さなこと」を一つだけ探してみる。 |
| 孤独感が強いタイプ | 一人の時間が長く、「誰も自分を分かってくれない」と感じる。 | 短いメッセージで近況を共有する相手を一人決める。信頼できる相談窓口やコミュニティ情報をメモしておく。 |
| 生活リズムが乱れがちなタイプ | 睡眠不足や昼夜逆転で、夕方以降に気分の落ち込みが強まりやすい。 | 起きる時間をまず固定し、夕方以降のカフェインを控える。寝る前のスマホ時間を短くする。 |
この表はあくまで一例です。「自分に一番近いのはどのタイプか」「この中で今日から試せそうなことは何か」を考えるきっかけとして活用してみてください。
夜に気持ちが落ち込むときに避けたいNG行動と代替案
夜の「反省会」と「答え探し」にハマりすぎない
夜に気持ちが落ち込むとき、多くの人がやってしまいがちなのが、「今日一日の反省会」を長時間続けてしまうことです。「あのとき、もっとこうすれば」「どうして自分はいつもこうなんだろう」と考え続けるうちに、最初の出来事から離れて、過去の別の失敗や、将来への不安にまで話が広がってしまうことがあります。
また、スマホで「夜 気持ちが落ち込む 対処法」などを検索し続け、情報を読み漁っているうちに、「自分は重い状態かもしれない」と不安が強まることもあります。夜は、事実を冷静に整理する力が弱まりやすい時間帯です。答え探しをしすぎるほど、自分を追い詰めてしまうこともある、ということを覚えておきたいところです。
NG行動と代わりにできる行動を比較する
ここでは、夜に気持ちが落ち込むときに陥りがちなNG行動と、現実的に取り組みやすい代替行動を表に整理します。この表を見ながら、「自分はどのパターンをやりがちか」「どの代替案なら試せそうか」をイメージしてみてください。
【夜に気持ちが落ち込むときのNG行動と代替行動】
| よくあるNG行動 | なぜつらさが増えやすいか | 現実的な代替行動の例 |
|---|---|---|
| 布団の中で延々と反省会を続ける。 | 事実より自己否定に意識が向きやすくなり、眠りのスイッチが入らない。 | 反省や振り返りは「明日の昼に10分だけ」と時間を決め、今夜は「ここまで」と区切る。 |
| 不安なワードを何度も検索してしまう。 | 刺激の強い情報にさらされ続け、不安や焦りが増幅される。 | 「今は調べないリスト」を作り、気になることは紙にメモして翌日調べる。 |
| 気持ちをまぎらわせるためにお酒を増やす。 | 一時的に楽になっても、睡眠の質が下がり、翌日の落ち込みが強まることがある。 | 温かい飲み物や香り、音楽など、「体を落ち着かせる代わりの習慣」を探す。 |
| 眠れない自分を責め続ける。 | 「眠れないこと=ダメな自分」と結びつけ、自己否定が悪循環になる。 | 「眠れない夜もある」と認め、「横になって目を閉じているだけでも休息になる」と考え方を緩める。 |
この表は、「NGだから絶対にしてはいけない」という意味ではありません。「やりがちなパターンを少しだけ別の行動に変えてみると、どんな変化があるか試してみよう」という実験のヒントとして使ってみてください。
すぐに変えやすい小さな一歩を決める
夜に気持ちが落ち込むとき、「全部の習慣を一気に変えよう」とすると、かえって疲れてしまいます。大切なのは、「これなら今日からできそう」という小さな一歩を一つだけ決めることです。
例えば、「寝る30分前になったらSNSを閉じる」「夜に気持ちが落ち込んだら、とりあえず3回だけ深呼吸する」「布団に入る前に、今日頑張ったことを一つだけ思い出してから寝室に行く」などです。完璧を目指さず、「できた日が少しずつ増えたら、それで十分」と捉えてみてください。
専門機関への相談を検討したい目安
ここまでご紹介してきた内容は、あくまで一般的な情報に基づくセルフケアのヒントです。生活習慣を整えたり、考え方のクセに少しずつ気づいたりすることで、夜に気持ちが落ち込む頻度や度合いが和らぐ人もいます。一方で、セルフケアだけでは対応が難しい状態も確かに存在します。
相談を考えてよいサインの例
次のような状態が続いている場合は、「まだ受診するほどではない」と我慢するよりも、早めに相談を検討したほうが良い場合があります。ここに挙げるのはあくまで一例ですが、自分の状態を振り返る参考にしてみてください。
夜に気持ちが落ち込む状態が数週間〜数か月続き、日中も気分の落ち込みが強くなってきている。以前は楽しめていた趣味や人付き合いに興味が持てず、「何をしても楽しくない」と感じる日が増えている。眠れない、途中で何度も目が覚める、朝早く目が覚めてそのまま眠れないなど、睡眠の問題が続き、仕事や家事、学業に支障が出ている。食欲が極端に落ちる、または過食が続くなど、体調の変化が目立ってきている。「消えてしまいたい」「自分なんていないほうがいい」といった考えが頭に浮かぶことがある。
こうした状態は、「気の持ちよう」の問題ではなく、心と体がかなり疲れているサインでもあります。一人で抱え込まず、「相談してもいい状態なんだ」と受け止めてあげることが大切です。
どこに相談すればよいかの目安
夜に気持ちが落ち込むことや、気分の不調について相談できる場所はいくつかあります。まずは、普段から受診している内科やかかりつけのクリニックに、「最近夜になると気分が沈むことが多い」「眠れない日が続いている」といった状況を伝えてみるのも一つです。必要に応じて、心療内科や精神科など、より専門的な医療機関を紹介してもらえることがあります。
また、仕事のストレスや職場環境との関係が大きいと感じる場合は、職場の産業医や保健師、メンタルヘルス相談窓口なども利用できます。学生の場合は、学校の保健室やスクールカウンセラー、学生相談室に相談する方法もあります。「どこに相談すればよいか分からない」というときは、自治体の相談窓口や地域の保健センターなどに問い合わせることで、状況に合った支援先を案内してもらえる場合があります。
相談をためらう気持ちへの向き合い方
「この程度で受診していいのか」「病名がついてしまうのが怖い」「忙しいから時間が取れない」など、専門機関への相談をためらう理由は人それぞれです。その一方で、早めに相談したことで、「もっと早く話してよかった」と感じる方も多くいます。
受診や相談は、「自分は弱い」と認める行為ではなく、「これ以上一人で抱え込まない」という選択です。夜に気持ちが落ち込む状態が長く続いているなら、「とりあえず一度話を聞いてもらう」くらいの気持ちで、ハードルを少し下げて考えてみてもいいかもしれません。
よくある質問(Q&A)
Q1. 夜に気持ちが落ち込むのは性格が弱いからですか?
A. 夜に気持ちが落ち込むことは、多くの人が経験することであり、性格の強さ・弱さだけで説明できるものではありません。体内時計やホルモンの変化、生活リズム、ストレス、過去の経験など、さまざまな要因が重なって起きると考えられています。「自分のせい」と一人で抱え込まず、「夜はそう感じやすい時間帯でもある」と知っておくだけでも、少し気持ちが軽くなるかもしれません。
Q2. 夜に気持ちが落ち込むとき、無理に前向きなことを考えたほうがいいですか?
A. 無理に「ポジティブにならなきゃ」と自分を追い立てると、かえって苦しくなることもあります。大切なのは、「落ち込んでいる自分を責めない」ことと、「考え続ける時間に区切りをつける」ことです。紙に気持ちを書き出して閉じる、深呼吸やストレッチで体に意識を向けるなど、「考えることから少し離れる時間」を作ることが、結果的に心の回復につながることがあります。
Q3. 夜に気持ちが落ち込むとき、家族や友人にどこまで話していいか分かりません。
A. どこまで話すかは、その相手との関係性やあなた自身の気持ちによります。「全部話さなければいけない」と考える必要はありません。まずは、「最近、夜になると気分が沈みやすくて」といった、ごく一部だけ共有してみるのも一つです。もし話してみて「安心できる」「少し楽になった」と感じる相手がいれば、その人は今後の支えになるかもしれません。逆に、話してみて苦しくなる場合は、その人に無理をして話し続ける必要はありません。
Q4. 夜に気持ちが落ち込むときのセルフケアは、どれくらい続ければいいですか?
A. セルフケアの効果や体感の変化には個人差がありますが、まずは2〜3週間ほど、「できる範囲で続けてみる」と決めて取り組んでみるのも一つの目安です。その中で、「これは自分に合っていそう」「これは負担が大きい」といった感覚が見えてくることがあります。つらさが強い、あるいは長期間続く場合は、セルフケアだけに頼らず、医療機関や専門家への相談も検討してみてください。
Q5. 夜に気持ちが落ち込むとき、「消えてしまいたい」と感じてしまうことがあります。
A. そのような気持ちが出てくるのは、とてもつらい状態で、心と体が限界に近づいているサインでもあります。「そんなことを考えてはいけない」と自分を責めるのではなく、「それほど追い詰められている自分がいる」と受け止めてあげることが大切です。そのうえで、一人で抱え続けるのではなく、できるだけ早く、医療機関や公的な相談窓口、信頼できる人に気持ちを伝えてほしいと思います。この記事は専門的な治療の代わりにはなりませんが、「相談してもいい」と感じるきっかけになれば幸いです。
用語解説
体内時計
私たちの体の中にある、おおよそ24時間周期のリズムを刻むしくみです。睡眠と覚醒、体温、ホルモン分泌、気分の波などに関わっており、光や生活リズムの影響を受けて調整されています。
メラトニン
主に夜間に分泌されるホルモンで、「そろそろ眠る時間」というサインとして働くと考えられています。強い光やブルーライトを夜に浴び続けると、分泌のタイミングが遅れたり、量が抑えられたりする可能性があるとされています。
交感神経と副交感神経
自律神経を構成する2つの働きです。交感神経は主に日中の活動モードを支え、心拍数や血圧を上げる方向に働きます。副交感神経は主に休息モードを支え、心拍数を落ち着かせ、消化や回復の働きを高めます。夜に気持ちが落ち込むときは、このバランスが乱れていることもあります。
自律神経
心拍、血圧、体温、消化、呼吸などを自動的にコントロールしている神経のしくみです。自分の意思とは関係なく働いており、ストレスや生活習慣、睡眠などの影響を受けます。
セルフケア
自分の心と体の状態に気づき、自分でできる範囲のケアや工夫を行うことを指します。睡眠・食事・運動・休息の工夫や、リラックス方法、相談先を確保することなどが含まれます。専門的な治療の代わりではなく、それを補う大切な土台と考えられています。
まとめ:夜に気持ちが落ち込む自分を責めず、小さな一歩から始める
夜に気持ちが落ち込むとき、多くの人はまず「自分が弱いから」「考えすぎだから」と、自分を責める方向に気持ちが向かいがちです。しかし、この記事で見てきたように、夜に気持ちが沈みやすくなる背景には、体内時計やホルモンの変化、静けさや暗さといった環境の影響、生活リズムや情報との付き合い方、これまでの経験や思考のクセなど、さまざまな要素が絡み合っています。
つまり、夜に気持ちが落ち込むのは、「あなたの性格が悪いから」ではありません。体と心が、「うまく休むきっかけを見失っているだけ」の状態であることも多いのです。
この記事では、夜に気持ちが落ち込む理由を理解する視点、生活習慣やスマホとの付き合い方、書き出しやストレッチなどの具体的なセルフケア、タイプ別の対策、避けたいNG行動と代替案、そして専門機関への相談を検討したい目安までをお伝えしました。どれも大切なポイントですが、全部を完璧にやる必要はありません。
まずは、「これなら今日からできそう」と感じることを一つだけ選んでみるところからで十分です。例えば、「寝る30分前にSNSを閉じる」「布団に入る前に肩と首をゆっくり回す」「夜に気持ちが落ち込んだら、ノートに3行だけ気持ちを書く」といった小さな一歩でかまいません。
それでもつらさが強い、長く続いている、自分や誰かを傷つけたい気持ちが出ているときは、一人で頑張り続けなくて大丈夫です。医療機関や専門家、公的な相談窓口、信頼できる人など、あなたの味方になってくれる人や場所を頼ることは、弱さではなく大切な力です。
夜に気持ちが落ち込む自分を否定するのではなく、「ここまでよく頑張ってきたね」と労わりながら、できる範囲で小さな一歩を選んでみてください。その一歩が、明日のあなたの心を、今より少しだけ軽くしてくれるかもしれません。
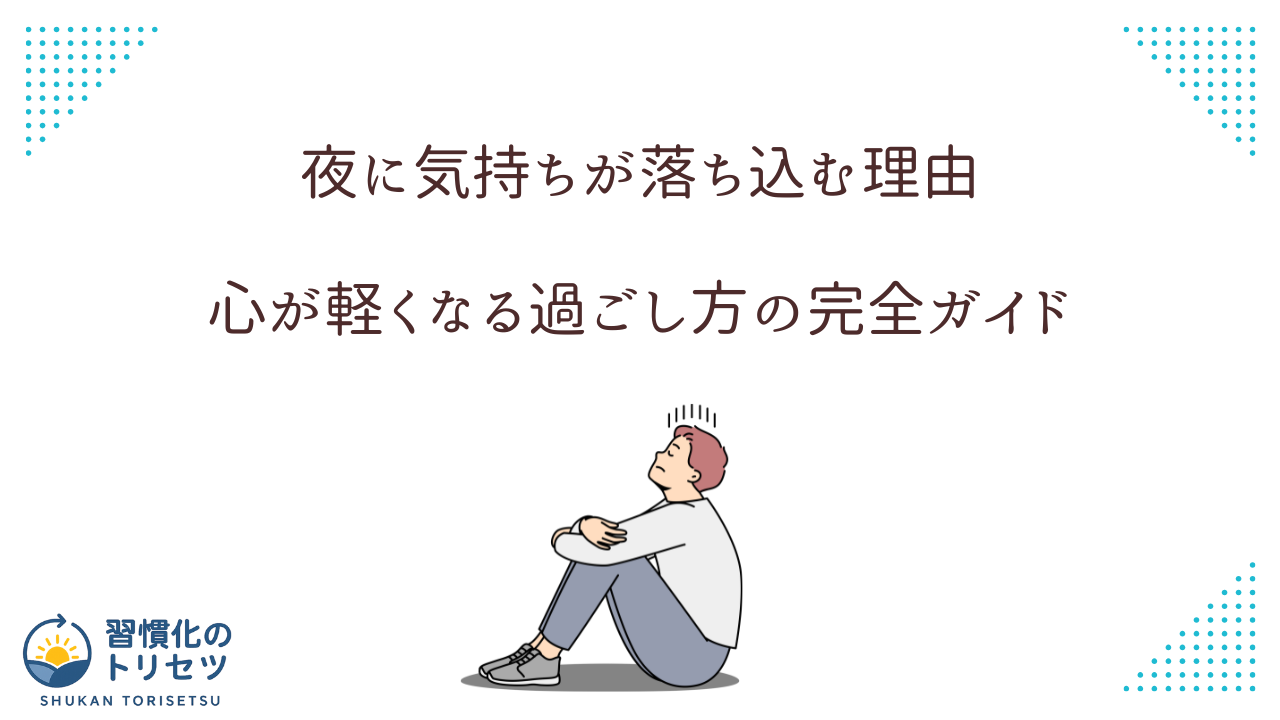
コメント