「布団には入っているのに、なかなか眠れない」「早く寝ようとベッドに入ったのに、逆に目がさえてしまう」。そんな経験はありませんか。
実は、睡眠の質を左右するのは「何時間寝たか」だけではなく、ベッドに入る“時間”そのものです。就寝時間の取り方を間違えると、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりと、かえって睡眠の質が下がってしまうことがあります。
この記事では、ベッドに入る時間がなぜ重要なのか、その原因と具体的な対策を、できるだけわかりやすく解説します。
まず最初に、この記事の結論をシンプルにまとめると、次の3つです。
・「眠気のピーク」に合わせてベッドに入ると、寝つきがスムーズになりやすいこと
・就寝時間がバラバラだったり、ベッドにいる時間が長すぎたりすると、睡眠の質が落ちやすいこと
・起床時間を軸にして、就寝タイミングと夜の過ごし方を少しずつ整えると、今日からでも寝つきを改善しやすいこと
これから、「なぜその時間にベッドに入るか」「どう整えればよいか」を、順番に深掘りしていきます。
『この記事は、睡眠や生活リズムに関する情報を継続的にリサーチし、一般向けに解説してきたライターが、専門書や公的機関の資料などを参考に、非医療・非専門家の立場から一般的な知識としてまとめたものです。具体的な症状や治療については、医療機関など専門家への相談をおすすめします。』
ベッドに入る時間が睡眠に与える影響と原因を理解する
まずは、なぜ「ベッドに入る時間」がそんなに大事なのか、土台となる考え方を整理しておきます。ここを押さえておくと、後半で紹介する具体的な対策の意味がぐっとわかりやすくなります。
体内時計と「眠気の波」のタイミング
私たちの体には、一日およそ24時間のリズムを刻む**体内時計(概日リズム)**が備わっています。この体内時計に合わせて、体温やホルモン分泌、眠気の出方などが変化します。
ポイントになるのは、眠気には「波」があるということです。夜になるとだんだん眠くなり、深夜から明け方にかけて眠気のピークがきて、朝になると少しずつ目が覚めていく。この「眠気の波」が、体内時計とリンクしています。
ところが、夜遅くまで強い光を浴びたり、夕方以降にカフェインをとりすぎたりすると、体内時計のリズムがずれ、本来眠くなるはずの時間帯に眠気がこないことがあります。この状態で「とりあえず早めにベッドに入ろう」としても、体はまだ起きるモードに近いため、寝つきにくくなってしまいます。
つまり、ベッドに入る時間を考えるときには、単に「何時だから」ではなく、自分の体内時計と眠気の波に合ったタイミングかどうかを意識する必要があるのです。
「寝だめ」や不規則な就寝時間がもたらす悪循環
平日は仕事や学校で起床時間が早く、週末はお昼近くまで寝ている。こうした寝だめ生活は、多くの人が心当たりのあるパターンではないでしょうか。
しかし、寝だめを繰り返していると、体内時計は「週末モード」に合わせてずれていきます。すると、日曜の夜になっても眠気がこない、月曜の朝に強い眠気やだるさを感じる、といった状態になりやすくなります。
このとき、「明日は早いから」と無理に早めにベッドに入ると、やはり体はまだ寝る準備が整っておらず、ベッドの中で長く起きている時間が増えることになります。これを繰り返すうちに、
「ベッドに入ってもどうせ眠れない」
「布団に入ると、眠れない不安が出てくる」
といったネガティブな学習が起こり、ベッド=眠れない場所というイメージが強まってしまうのです。
ベッドにいる時間が長すぎると寝つきが悪くなる理由
睡眠の専門分野では、ベッドに入っている時間のうち、実際に眠っている時間の割合を睡眠効率と呼ぶことがあります。一般的には、この睡眠効率が高いほど、睡眠の質が良いと考えられています。
ところが、「早く寝なきゃ」と焦って、実際に眠れる時間よりもかなり早くベッドに入ってしまうと、ベッドの上で起きている時間が長くなり、睡眠効率は下がってしまいます。その結果、
「ベッド=目がさえてしまう場所」
というイメージが脳に刷り込まれ、ますます寝つきが悪くなるという皮肉な状態になりかねません。
この悪循環を断ち切るためには、眠気がある程度高まってからベッドに入ること、そしてベッドの上では「眠る」か「リラックスする」以外の行動を極力しないことが役に立ちます。
ベッドに入る「ベストな時間」を決めるための方法
ベッドに入る“時間”が重要だとわかっても、「結局、何時に寝ればいいの?」と感じる方は多いと思います。この章では、自分に合った就寝時間を見つけるための考え方をお伝えします。
起きたい時間から逆算して就寝時間を決める
まず軸にしたいのは、起床時間です。起きる時間が毎日バラバラだと、体内時計が安定せず、ベッドに入る時間も定まりません。そこで、平日・休日を通して、できるだけ共通の「起きたい時間」をひとつ決めます。
一般的な目安として、大人の必要睡眠時間は個人差がありますが、おおよそ6〜8時間程度と言われることが多いです。そこで、例えば朝7時に起きたい人なら、まずは23時〜1時の間にベッドに入るイメージでスタートしてみます。
最初からきっちり決めすぎると続かないので、**「起床時間をほぼ固定する」「就寝時間は±30分〜1時間のゆるい幅を持たせる」**くらいの感覚で始めると取り組みやすくなります。
睡眠時間の目安と自分の「ちょうどよさ」を探る
必要な睡眠時間は、「年齢」「体質」「日中の活動量」などによって変わります。大切なのは、周りの情報に振り回されることではなく、自分の体感としての“ちょうどよさ”を見つけることです。
ここでは、就寝時間・起床時間・日中の眠気の強さをざっくり記録しながら、数週間単位で自分の傾向をつかむのがおすすめです。例えば、2週間ほど同じ起床時間で生活してみて、
・午前中から強い眠気があるなら、就寝時間を15〜30分早める
・日中は問題なく集中できるが、夜なかなか眠くならないなら、就寝時間を15〜30分遅らせる
というように、小さな調整を繰り返しながらベストな就寝タイミングを探していきます。
平日と休日の就寝・起床時間のズレを小さくするコツ
睡眠の質を保つうえで意外と重要なのが、平日と休日の時間差をどれだけ小さくできるかという点です。ここで、平日と休日のズレと、体への影響のイメージを簡単な表にまとめてみます。
(表1)平日と休日の起床時間のズレと、体内時計への影響イメージ
| 平日と休日の起床時間の差 | 体内時計への影響のイメージ | 感じやすい状態の例 |
|---|---|---|
| 1時間以内 | 比較的安定しやすい | 月曜の朝も大きなだるさは少ない |
| 2時間前後 | ややずれやすい | 連休明けに眠気・だるさを感じやすい |
| 3時間以上 | 大きくずれやすい | いわゆる「社会的時差ボケ」状態になりやすい |
この表はあくまでイメージですが、起床時間の差が1時間以内におさまるように意識すると、体内時計が安定しやすいと考えられます。どうしても休日に寝だめしたい場合も、普段より1〜2時間程度にしておき、「昼寝で調整する」「夜更かしをしすぎない」など、トータルのリズムを崩しすぎない工夫がポイントになります。
今日からできるベッドに入る時間の整え方の具体的な方法
ここからは、**「今日から何を変えればいいか」**という視点で、ベッドに入る時間を整える具体的な方法を紹介します。
就寝90分前からのルーティンを決める
ベッドに入る“時間”を整えるには、その前後の行動もセットで考えることが大切です。特に意識したいのが、就寝90分前からの過ごし方です。
人の体温は、夜になると深部体温(体の内側の温度)が下がり、それに伴って眠気が高まりやすくなります。逆に、寝る直前まで強い光を浴びたり頭をフル回転させていると、体温や自律神経が「活動モード」のままで、布団に入ってもなかなか眠れない状態になりやすいです。
そこで、就寝予定時刻の90分前を目安に、「刺激を減らしていく時間」と「リラックスする時間」に切り替えることを意識してみてください。例えば、
・明るい照明から少し暗めの照明に切り替える
・仕事や勉強の作業を終え、メール・チャットの返信も区切りをつける
・ぬるめのシャワーやお風呂をすませ、あとはゆったり過ごすだけにする
といった流れを作っておくと、その後のベッドに入る時間も自然と安定しやすくなります。
「この時間以降はベッドに行かない」ルールを作る
ベッドに入る時間を整えるうえで、意外な落とし穴になるのが、中途半端なタイミングでベッドに横になってしまうことです。たとえば、夜10時ごろにスマホをいじりながらベッドでゴロゴロし、そのままダラダラと日付が変わってしまうようなケースです。
この状態では、「ベッド=リラックスできる場所」ではなく、「ベッド=スマホや動画を見る場所」というイメージが強くなり、眠気とベッドの結びつきが弱くなってしまいます。
そこでおすすめなのが、「眠るためにベッドに行く時間」をひとつ決めることです。その時間までは、ソファや別の椅子で過ごし、「ベッドは眠くなってから行く場所」として扱います。
最初は違和感があるかもしれませんが、数週間続けていると、ベッドに入る=眠る準備が整ったサイン、というポジティブな条件づけが少しずつできていきます。
ベッドに入る時間を15分ずつ前倒し・後ろ倒しする
生活リズムを変えるとき、いきなり1〜2時間早く寝ようとするのは、体にとって大きな負担になります。そこで、15分単位の小さな調整を心がけるとスムーズです。
例えば、今は深夜1時ごろにベッドに入っている人が、最終的に23時半に寝たい場合、以下のように少しずつ調整します。
(表2)ベッドに入る時間を少しずつ前倒しする例
| 調整期間の目安 | ベッドに入る目標時間 | ポイントの例 |
|---|---|---|
| 1週目 | 0時45分 | 夜のスマホ時間を15分だけ削る |
| 2週目 | 0時30分 | 就寝90分前ルーティンのスタートも15分前倒し |
| 3週目 | 0時15分 | 夕食や入浴時間も少しだけ早める |
| 4週目 | 23時45分〜23時30分 | 起床時間を固定しつつ、最終形に近づける |
この表はあくまで一例ですが、一気に変えようとせず、1〜4週間かけて少しずつ調整することで、体内時計もゆっくりと新しいリズムに慣れやすくなります。
ベッドに入る時間と睡眠の質を下げる習慣の原因と対策
ここでは、ベッドに入る“時間”を乱してしまいがちな、よくある習慣とその対策をまとめます。「自分もやっているかも」と感じるものから、一つずつ見直していきましょう。
夜遅くのカフェイン・スマホが時間感覚を狂わせる
コーヒーやエナジードリンク、緑茶・紅茶などに含まれるカフェインには、眠気を感じにくくする作用があるといわれます。特に夜遅い時間にカフェインをとると、本来眠くなるはずの時間帯に眠気がこなくなり、結果としてベッドに入る時間もどんどん遅くなってしまいがちです。
また、寝る前のスマホやPCの画面から出る**強い光(特にブルーライト)**は、体内時計に「まだ昼間だ」と勘違いさせると言われています。ベッドに入る時間になっても目が冴えてしまい、「あと5分だけ」のつもりが1時間以上たっていた、ということも珍しくありません。
対策としては、就寝3〜4時間前からカフェインを控えること、そして就寝1時間前を目安に、スマホやPC画面から距離を取ることが一つの目安になります。どうしてもスマホを見たい場合は、画面を暗くする・ナイトモードにする・短時間で切り上げるなど、ダメージを減らす工夫をしてみてください。
「とりあえずベッドでゴロゴロ」が不眠を招く
疲れているからといって、夕食後すぐにベッドに移動し、ゴロゴロしながらSNSや動画を見続ける習慣も、ベッドに入る時間を曖昧にしてしまう原因になります。
この状態では、ベッド=休む場所ではなく、**「ダラダラする場所」**として脳に学習されてしまいます。その結果、いざ寝ようと決めても、ベッドに入ると自然にスマホを触りたくなったり、考えごとモードになったりしやすくなります。
もし心当たりがある場合は、**「眠ること」と関係のない時間は、ベッド以外の場所で過ごす」**ことを意識してみてください。たとえば、ソファで動画を見る、机で本を読むなど、ベッドを「寝るためだけの場所」に近づけていくことが、結果として寝つきを良くする近道になります。
残業やシフト制の場合の割り切り方
仕事の都合で残業が多かったり、シフト制で日によって勤務時間が変わる場合、ベッドに入る時間を毎日同じにするのは現実的ではありません。その場合は、**「完全な一定」を目指すのではなく、「できる範囲でリズムをそろえる」**という考え方が大切です。
例えば、シフトが早番・遅番の2パターンだとしたら、それぞれの起床時間と就寝時間の組み合わせを事前に決めておきます。そのうえで、同じパターンが続く期間はなるべく同じリズムで過ごし、休日も大きくずらしすぎないように意識します。
完璧を目指すよりも、**「自分の生活の制約の中で、一番マシなリズムをキープする」**ことが、メンタル的にも現実的にも続けやすいポイントです。
メンタル面から見る「ベッドに入る時間」のマインドセット
ベッドに入る時間は、生活リズムだけでなく、考え方や心構えにも影響を受けます。この章では、夜になると不安や焦りが強くなりがちな方に向けて、マインドセットの整え方をお伝えします。
「早く寝なきゃ」のプレッシャーを弱める
「明日も早いから、早く寝なきゃ」「寝不足になったらどうしよう」という思いが強すぎると、かえって頭が冴えてしまうことがあります。これは、睡眠に対するプレッシャーで緊張が高まり、自律神経が興奮してしまうためです。
この悪循環を断ち切るには、ベッドに入る時間を決めつつも、「眠れなくても大丈夫な範囲はある」と自分に許可を出すことが役に立ちます。例えば、「ベッドに入って30分くらい眠れなくても、それだけで明日が台無しになるわけではない」「少し眠れれば体はある程度回復できる」といった柔らかい考え方を持つことで、気持ちのハードルが下がります。
眠くなるまでベッドに入らないという選択肢
どうしてもベッドに入ると不安や緊張が高まる場合、思いきって**「眠気が出るまでベッドに入らない」**という方法もあります。これは、睡眠の専門領域では「刺激コントロール」という考え方に通じるものです。
具体的には、ある程度の眠気を感じるまでは、ソファや椅子でリラックスして過ごし、強い光や刺激の少ない環境で、静かな音楽やストレッチなどをしながら「眠気の波」を待ちます。そして、「そろそろ眠れそうだ」と感じたタイミングで、初めてベッドに向かいます。
この方法は、ベッド=眠れない場所というイメージを弱め、ベッド=眠気がきたときに行く場所という新しいイメージを作るのに役立つ場合があります。ただし、極端に夜更かしにならないよう、起床時間とのバランスを見ながら取り入れてください。
完璧を目指さず、7割できればOKと考える
生活リズムの改善は、どうしても「毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きなければいけない」という完璧主義になりがちです。しかし、実際の生活では、残業や付き合い、体調の波など、さまざまな要素が絡み合います。
そこで、**「7割くらい守れれば十分」**というゆるさを持つことが大切です。平日のうち3〜4日でも同じ時間にベッドに入れたらOK、休日も起床時間のズレが2時間以内ならまずまず、というように、自分なりの合格ラインを決めておくと、長く続けやすくなります。
専門機関への相談を検討したい目安
ここまでお伝えしてきた内容は、あくまで一般的な生活習慣の工夫です。中には、生活リズムを整えてもつらい状態が続く場合や、医療的なサポートが必要なケースもあります。
以下のような状態が続く場合は、無理に自己流で何とかしようとせず、医療機関や専門家への相談を検討する目安と考えてみてください。
一般的な生活改善をしても数か月以上つらい状態が続く
ベッドに入る時間や生活リズムを見直しても、数か月以上にわたり寝つきの悪さや夜間の中途覚醒が続いている場合は、専門的な見立てが役に立つことがあります。特に、睡眠薬や市販の睡眠改善薬を自己判断で長期間使っている場合は、必ず医師に相談しましょう。
昼間の生活に支障が出ている
睡眠の問題が原因で、日中の仕事や学業、家事・育児などに支障が出ている場合も、専門機関への相談を検討したいサインです。例えば、
・運転中や会議中に耐えがたい眠気におそわれる
・集中力が落ちてミスが増えている
・強い疲労感が続き、日常生活そのものがしんどい
といった状態が続く場合、単なる「夜更かしのしすぎ」だけでは説明できないケースもあります。
こころの不調が強く出ていると感じる場合
夜になると不安が強くなったり、気分が落ち込んで眠れない日が続く場合、背景にストレスや心の不調があることもあります。こうしたケースでは、睡眠だけを整えようとするよりも、心身全体の状態を専門家と一緒に見ていくことが重要です。
繰り返しになりますが、この記事はあくまで非医療・非専門家による一般的な情報提供です。気になる症状がある場合は、早めに医師や専門機関に相談することをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q1. ベッドに入る時間は毎日まったく同じでないといけませんか?
A. 毎日まったく同じである必要はありませんが、できるだけ1時間の幅の中におさまるようにすると、体内時計が安定しやすいと考えられます。例えば、「23時〜24時の間にはベッドに入る」といったゆるいルールでも、続ければ十分な効果が期待できます。
Q2. 早くベッドに入って、布団の中でスマホをしながら眠くなるのを待つのはダメですか?
A. 一時的にはリラックスできるかもしれませんが、長期的には**「ベッド=スマホを見る場所」という条件づけ**が強くなり、寝つきが悪くなるリスクがあります。できれば、スマホを見るのはベッド以外の場所で、眠くなってからベッドに向かうほうが、睡眠の質にはプラスになりやすいです。
Q3. ベッドに入ってからどれくらい眠れなかったら、一度起きたほうがいいですか?
A. 目安としては、20〜30分ほど経っても眠れそうにない場合、いったんベッドを出て別の部屋や椅子で静かに過ごす方法が紹介されることがあります。時計を何度も見ると逆に焦るので、あくまで体感で「そろそろ30分くらいかな」と感じたときに、いったん場所を変えるイメージで試してみてください。
Q4. どうしても仕事や勉強で夜遅くなってしまう日は、どう調整すればいいですか?
A. そんな日ももちろんあります。その場合は、翌朝の起床時間を大きくずらさないことを優先し、睡眠時間が少し短くなっても、次の日以降で少し早めにベッドに入るなど、数日かけてリズムを戻していくことを意識してみてください。一晩で完璧に取り返そうとするより、数日の単位で少しずつ調整するほうが、体への負担は少なくなります。
Q5. 昼寝をすると夜のベッドに入る時間が遅くなってしまいます。昼寝はしないほうが良いですか?
A. 昼寝自体が悪いわけではありませんが、時間帯と長さがポイントになります。目安としては、午後の早い時間に20〜30分程度におさえると、夜の睡眠への影響を比較的少なくしやすいと考えられます。夕方以降の長い昼寝は、夜の眠気を弱めてしまい、ベッドに入る時間が遅くなりやすいので注意が必要です。
用語解説
体内時計(概日リズム)
私たちの体に備わっている、一日およそ24時間のリズムをつくる仕組みのこと。睡眠・体温・ホルモン分泌など、多くの機能がこのリズムに合わせて変化します。
睡眠効率
ベッドに入っている時間のうち、実際に眠っている時間の割合のこと。一般的には、この割合が高いほど、睡眠の質が良いと考えられます。
カフェイン
コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれる成分で、眠気を感じにくくしたり、脳を覚醒させたりする作用があるとされています。
刺激コントロール
睡眠の専門領域で使われる考え方のひとつで、「ベッド=眠る場所」として脳に学習し直していく方法の総称。眠くなるまでベッドに入らない、眠れなければ一度ベッドを離れる、などの工夫が含まれます。
まとめ|全部を完璧にしなくていい。まずは「ベッドに入る時間」を一つ決めてみる
ここまで、ベッドに入る“時間”が重要な理由と、その整え方についてお伝えしてきました。
ポイントをあらためて整理すると、次のようになります。
・ベッドに入る時間は、体内時計と眠気の波に合わせることで、寝つきと睡眠の質が変わること
・平日と休日の起床時間の差を小さくし、起きたい時間から逆算して就寝時間の目安を決めることが大切なこと
・ベッドに入る時間を少しずつ整え、ベッドを「眠るための場所」として再学習していくことで、無理なくリズムを改善できること
とはいえ、生活リズムを一気に変えるのは、誰にとっても簡単ではありません。大切なのは、全部を完璧にやろうとしないことです。
まずは、
「ベッドに入る時間を、今より15分だけ早く(または遅く)してみる」
「平日と休日の起床時間の差を、3時間から2時間に縮めてみる」
など、できそうなことを一つだけ選んで試してみてください。
小さな一歩でも、それを続けることで、少しずつ「眠りやすい自分」に近づいていきます。今日の夜から、ベッドに入る“時間”に、ほんの少しだけ意識を向けてみてくださいね。
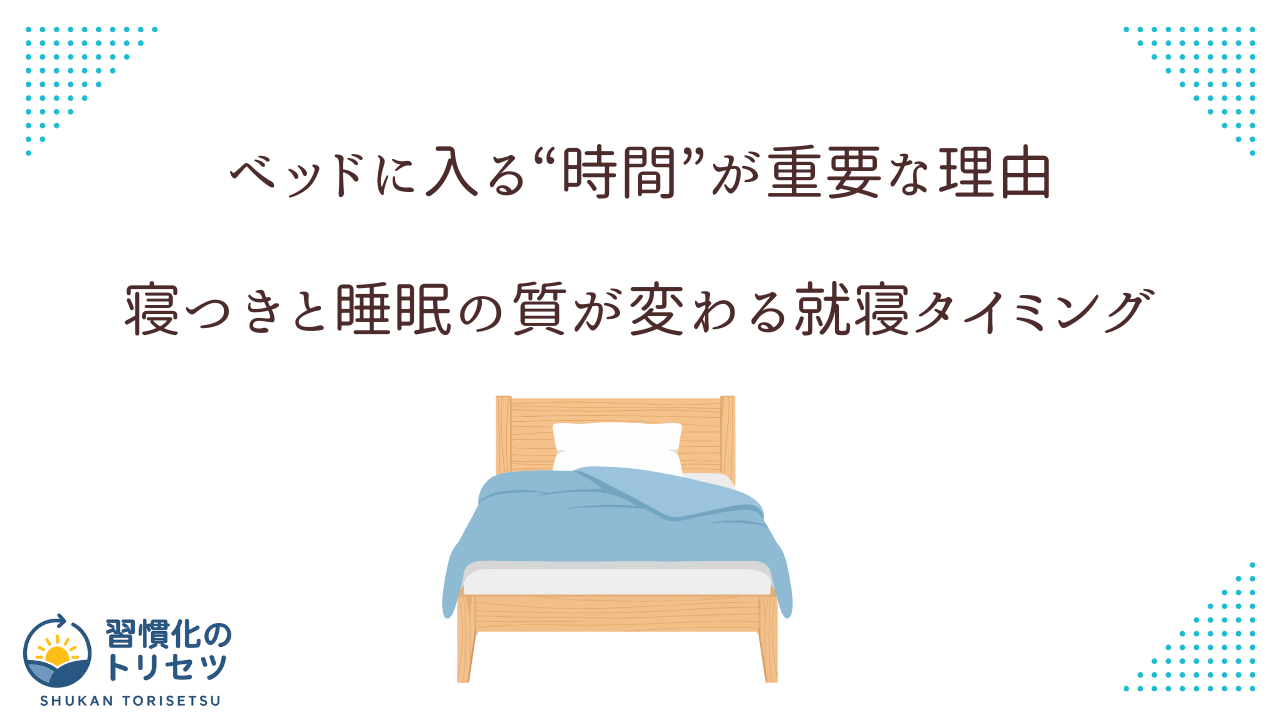
コメント